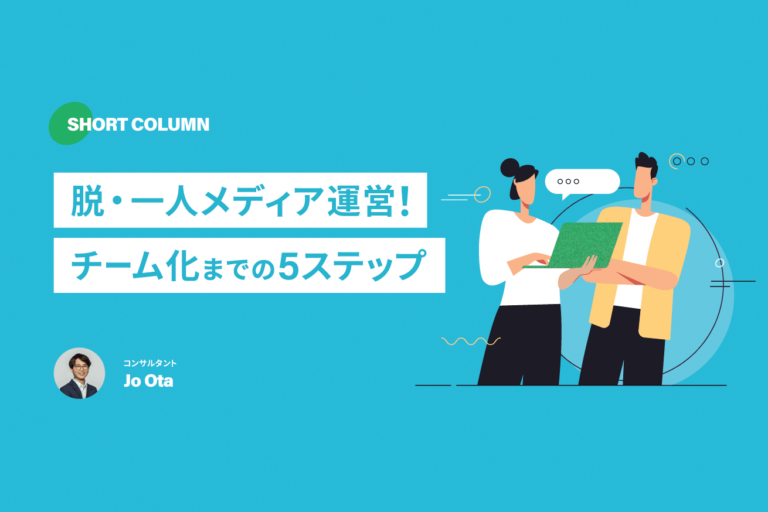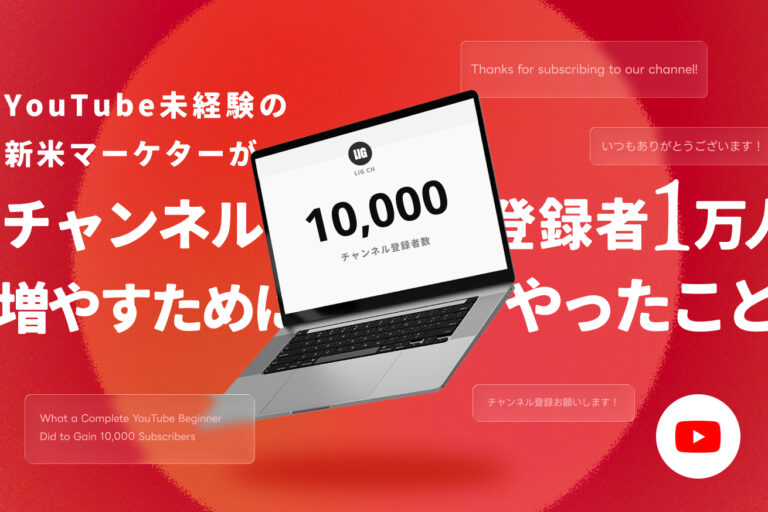インハウスマーケティング部のSEO担当です。
私は2017年頃からコンテンツSEOに取り組んでいるのですが、当時と比較すると検索エンジン上で上位表示させるのは難しくなった印象です。しかしそれでも、コンテンツSEOで得られる成果は多く、やる価値のある施策だと思っています。
この記事では、Webマーケティング初心者に向けて「コンテンツSEOとはそもそも何?」という初歩的な内容から、具体的な進め方やコンテンツの作り方まで徹底的に解説します。
「SEO記事を公開しても成果が出ない」「そもそも作り方が合っているのかが不安」という方は、 ぜひこの記事を参考にコンテンツSEOに取り組んでみてください。
目次
編集部注:2021年に公開された記事を再編集しました。
コンテンツSEOとは
コンテンツSEOとは
コンテンツSEOとは、Googleなどの検索エンジン上で上位表示するコンテンツを作成し、そこから集客をする施策です。
コンテンツSEOを進めるには、ペルソナが検索しそう・かつWebサイトの運用目的を満たすキーワードを選定し、そのキーワードで上位表示するコンテンツを作成します。
例えばWebサイト制作会社がコンテンツSEOで問い合わせを獲得したいなら、「Web制作会社 おすすめ」などのキーワードで上位表示するコンテンツを作成する、といった具合に進めていきます(詳細は後半で解説しています)。
コンテンツSEOは、このようにキーワードにあわせてコンテンツを制作するため、潜在層から顕在層まで幅広いユーザーにアプローチできることが特徴です。
コンテンツSEOとコンテンツマーケティングの違い
コンテンツSEOは、コンテンツマーケティングの一部で、現在のWebマーケティングの世界では主流になっています。
コンテンツマーケティングとは、コンテンツをWebページ、SNS、実際の商談の場も含め、さまざまなシーンで駆使して販売促進する手法のことです。
今日では、IT企業に限らず、あらゆる企業・事業において、コンテンツマーケティングの視点を抜きにした営業は考えられません。
コンテンツSEOで重要な考え方
コンテンツSEOを進めていく上では、ユーザー視点で考えることが何よりも重要です。
「検索エンジンで上位表示させる」と聞くと、テクニカルSEOと呼ばれるような検索エンジンのためのSEO対策をイメージしがちです。もちろんこれも多少は必要な考え方なのですが、そればかりが先行してしまわぬよう注意しましょう。
現在のアルゴリズムは数年前と比較してかなり精度が高くなっており、人間と同じようにコンテンツを理解できるようになっています。また、アルゴリズムの傾向を見ても、ユーザーにとって良質であるかどうかを重視しています。
そのため、コンテンツSEOで成果を出すには、徹底的にユーザーのことを考える必要があるのです。
また、コンテンツSEOは一朝一夕で成果を得られるものではなく、ある程度の数をこなすことも必要であることを頭に入れておきましょう。
コンテンツSEOのメリット
コンテンツSEOにはさまざまなメリットがあります。
売り込みに出かけずとも、問い合わせ獲得や注文獲得ができる
コンテンツSEOを含め、コンテンツマーケティングの最大のメリットは、営業担当者が自社のサービスや製品を売り込みに出かけなくても、コンテンツをきっかけに、お客様のほうから問い合わせをしてくれたり、注文をしてくれるようになることです。
弊社LIGは、オウンドメディア「LIGブログ」を10年以上運営しており、LIGブログのコンテンツをきっかけにLIGの存在を知ってくださったり、Web制作やコンテンツ制作をご依頼くださるお客様が多くいらっしゃいます。まさしくコンテンツSEOの効果を日々実感しています。
集客効果が長期間維持される
長期間にわたって集客力が続くことも、コンテンツSEOのメリットとしてあげられます。
広告の場合、広告を出した直後(もしくは広告を表示している期間)には集客効果を生み出しますが、広告の掲示が終われば効力がなくなります。それに対して、一度公開したWebコンテンツは削除しないかぎり存在し続けるので、良質のコンテンツであれば永続的に集客力が続きます。
自社の信頼度が高まりブランディングに貢献する
良質なコンテンツをきっかけにして、自社サイトを訪問してくれた人からの認知を得ることができます。
ユーザーの興味関心のあるジャンルの専門家が揃っている会社であることや、その分野で実績のある会社であることを知ってもらうことで、少しずつ信頼度が増し、ブランドとしての価値を感じてもらうことが可能です。
そうした認知や信頼が積み重なることで、しだいにサービスの契約や製品の購入へとつながるでしょう。
また、社員が積極的に情報発信していることで、お客様から親近感をもってもらえたり、指名で受注できたりするメリットもあります。
同業他社よりもブランドとしての高い価値をお客様に感じてもらうことができれば、価格競争から抜け出し、割引することなく定価でサービスや製品を販売することができるでしょう。
SNSで拡散して自然な被リンクを獲得できる
コンテンツSEOは、検索からの流入(集客)だけでなく、SNSからの流入も期待できます。良質なコンテンツはユーザーが「面白い」「話題にしたい」「シェアしたい」と思ってくれるので、SNSでも拡散しやすくなります。
そのため記事公開のタイミングに合わせて、必ず自社のFacebookやTwitterのアカウントで投稿して告知するようにしましょう。インフルエンサーに出演してもらった記事の場合は、インフルエンサー個人のTwitterやInstagramでの投稿も期待できるため(註:これは出演時の条件などによります)、いわゆる「バズる」コンテンツになることもあります。
SNSで拡散することにより、自然な被リンクを獲得できるのも大きなメリットです。被リンクが増えればGoogleからのコンテンツの評価が上がり、サイト(ドメイン)全体の評価も高まります。つまりドメインパワーが上がる=サイト内ページ全体の検索順位も上がりやすくなるというプラス効果の連鎖が期待できます。
少ない予算でスタートできる
またコンテンツSEOは、広告に比較すると少ない予算でスタートできます。サイトを運営する会社に専門的な知見があれば、その知見をもとにコンテンツを内製できるので、人件費以外は低コストで実施可能です。
とはいえ、SEO効果の高いコンテンツを制作するのは、未経験者には難しいかもしれません。
その場合は、コンテンツ制作を専門の制作会社に外注することになるでしょう。制作費は内製するよりも高くなりますが、コンテンツが永続的に「働く」ことを考えると、長期的に見ればリーズナブルです。このコストパフォーマンスの高さもコンテンツSEOの大きなメリットのひとつです。
ユーザーから評価される(=Googleから評価される)コンテンツを作成するためには、手間と時間がかかりますが、正しく労働力と費用を投資すれば、大きなリターンがあります。
ターゲットユーザーに効率的にアプローチができる
先ほどお伝えしたように、コンテンツSEOはキーワード単位でコンテンツを制作していくマーケティング手法です。そのため、ニーズが健在している層や、まだ自社のサービスや商品を知らないような潜在層まで、幅広い層にアプローチが可能です。
サイト訪問者にとって役に立つ情報を提供することは、すぐに商品・サービスの売上(コンバージョン)にならなくても、そうした商品やサービスがあることを認知してもらい、顧客にニーズを自覚させ、購入を促す効果が見込めるでしょう。
このような効果を、Webマーケティングでは「リードナーチャリング(Lead Nurturing、顧客育成)」といいます。
多くの消費者は、何かサービスや商品を購入する前に、オンラインで情報収集や比較検討をするため、企業は日頃からWebサイトやオウンドメディア、SNS上で丁寧な情報発信をおこなっておくことで、顧客獲得がしやすくなります。
さらにお客様はあらかじめ、そうした情報をチェックしてからアクションを起こすので、問い合わせの時点で相談や質問のポイントが明確になり、契約・購入までの意思決定がスムーズになるというメリットもあるのです。
コンテンツSEOのデメリット
コンテンツSEOとて万能ではなく、デメリットもあります。コンテンツSEOを実施する際は、以下のデメリットをきちんと理解して、社内で共有しておく必要があります。
コンテンツ制作には労力と時間がかかる
検索上位に表示される良質なコンテンツは、制作するのに手間と時間がかかります。コンテンツを自社で内製する場合、記事の執筆は本来の業務と兼務する場合が多いため、リソースの配分や制作体制の構築に工夫が必要になります。
文章を書くことが得意な社員ばかりとは限りませんし、モチベーションの低い人が片手間に書いた原稿では、ネットの海にさまようムダ記事を量産してるだけ、ということになってしまいます。
サイト(メディア)の規模や更新頻度にもよりますが、内製する場合は、実務経験のある編集者やライターを雇用し「インハウスエディター」「インハウスライター」が運営を主導するのが理想的です。
社内にプロを雇用できなかったり、内製することに自信がない場合は、コンテンツ制作を外注する必要があります。具体的には弊社LIGのようなコンテンツ制作会社に記事制作を依頼するというのが現実的です。
コンテンツSEOを外注すると費用がかかる
コンテンツ制作を外注する場合は、当然ながら費用がかかります。
たとえば、弊社LIGの場合は、以下のような価格設定です。
- 取材なしのSEO記事:1本15万円から
- 取材撮影のある企画記事:1本30万円から(インフルエンサーのキャスティング費用は、別途必要です)
SEOに関する知識やハウツーは日々変化しているので、コンテンツの品質を上げるためには、豊富な経験と最新の知識をあわせもつ人材がおこなうことが不可欠で、制作費もそれなりに必要です。
さらにコンテンツSEOは、制作会社にまかせて終わりではなく、クライアント側も一緒に制作する姿勢が大切です。外注するとしても「丸投げ」というわけにはいきません。
制作会社は、コンテンツの目的、ターゲット、ゴールなど、クライアントの希望を実現するために、詳しくヒアリングをおこないます。その都度、クライアント側もコンテンツについて考えたり調べたりする時間や手間がかかります。
効果が出るまでに時間がかかる
コンテンツSEOは、効果が出るまでに時間がかかることがあります。
Googleのクローラーが新しく追加されたコンテンツを発見し、インデックスするまでには時間がかかることに加え、コンテンツがインデックスされたからといって、すぐに検索上位をとれることはあまりありません。
最近は検索エンジンの精度が向上しているので、ドメインパワーの高いサイトなら記事の公開から早いときは2日〜1週間ほどで上位表示されることもあります。
とはいえ、たいていは1ヵ月から数ヵ月かけて上がってきますし、なかには1年ほどかけてじっくり上がってくる記事もあります。
そのため、コンテンツSEOに取り組むときは、「即効性が出なくても焦らない」という心構えが必要です。
とくにサイトをスタートしたばかりの頃はコンテンツ数が少ないため、効果が見えず、不安になるかもしれません。しかし、コンテンツの数量が増えるにつれて効果が出てくるので、アクセス数が伸びなくても諦めずにコツコツとコンテンツ制作を積み重ねる根気が必要です。
あらかじめ社内の関係者のあいだで、「コンテンツSEOはすぐに結果が出るものではない」という認識を共有しておくことが大切です。
メンテナンスが必要
コンテンツは、一度公開したら、それで終わりではありません。おいしい糠漬けを作るためには、毎日糠床をかき混ぜる必要があるように、公開した後も、こまめに記事をメンテナンスして更新し続けることが大切です。
検索結果の順位は日々変動します。ライバルも同じように上位表示を狙っているので、いったん上位をとれても安心できません。そのまま放置していては、しだいに順位が低下してしまいます。新しい情報があれば追記し、よりよいコンテンツへとバージョンアップを続けましょう。
コンテンツSEOのやり方を5ステップで解説
それでは、コンテンツSEOの具体的な手順について解説します。
- コンテンツSEOのやり方5ステップ
-
- 自社商品・サービスの整理
- ペルソナの設定
- キーワード選定
- キーワードからニーズを読み解く
- コンテンツを作成する
ステップ1. 自社の製品・サービスの分析
まずは、自社の製品やサービスを書き出して、それぞれの強みや特徴を洗い出します。強みや特徴は、「自分たちにできることを言語化する」ことを意識してみましょう。競合他社のページを参考にするのもおすすめです。
当たり前ですが、商材が違えば顧客や狙うキーワードも変わります。この作業が、のちのちのキーワード選定に役立つため、ぜひしっかりと取り組んでみてください。
ステップ2. ペルソナの設定
続いて、書き出した自社商品やサービスごとに、ペルソナを設定します。ペルソナとは、「商品やサービスを実際に利用する顧客の架空の人物像」という意味を持つマーケティング用語です。
ペルソナを作る時は、氏名や年齢、家族構成や住んでいる場所などの基本情報から、趣味・価値観などのライフスタイルまで細かく設定するのがポイントです。さらには、「その商品・サービスが必要な人はどんな要望を持っているのか?」「どんなお困りごとを抱えているのか?」を掘り下げて考えてみてください。
細かく設定することで、より効率よく効果的なマーケティング戦略や施策を立てやすくなります。

ペルソナとは?マーケティング初心者にもわかる作り方や事例を解説
ステップ3. キーワード選定
続いておこなうのは、キーワード選定です。このステップでは、ペルソナが検索しそう・かつWebサイトの運用目的にあうキーワードを選定し、さらに作成するキーワードの優先順位を決めていきます。
ステップ1であげた強みや特徴、ステップ2で設定したペルソナをもとに、想定されるキーワードを書き出していきましょう。
例えば、システム開発事業をおこなう会社が、問い合わせ獲得を目的としてコンテンツSEOに取り組む場合を考えてみます。
- システム開発事業の特徴
-
- オフショア開発で海外の情報にアクセスしやすい、リソースを確保しやすい
- 戦略や企画の上流工程から、運用保守まで一貫してサポートできる
- できること
-
- 戦略コンサルティング
- システム開発(Shopifyのリプレイス、ECサイト制作、マッチングシステムの開発、業務システムの開発など)
以上の点から、ペルソナが検索しそう・Webサイトの運用目的にあうキーワードを考えてみると
- オフショア開発 会社(オフショア開発先を探している)
- ITコンサルティング 会社(システム開発の上流工程を任せられる会社を探している)
- Shopify 制作会社(Shopifyを使ったECサイト制作ができる会社を探している)
などが挙げられます。このようにして、考えうるキーワードを洗い出していきましょう。
キーワードを挙げていくときは、上記のような自社サービスから導き出す方法の他に、関連キーワード取得ツールを活用したり、競合サイトがターゲットとしているキーワードも参考にしてみるとよいでしょう。競合サイトの流入キーワードは、ahrefsなどの有料ツールで調査可能です。
キーワードを一通り洗い出したら、作成するキーワードの優先順位を設定します。
優先順位を決めるときは、検索ボリューム数を考慮し目的に近いものから作成していきます。
- Webサイト立ち上げ間もない場合
- コンテンツ数がまだ少ないWebサイトは、まずは1つのトピックに関するコンテンツを拡充させることを最優先させます。これは、そのトピックに対する専門性が高いWebサイトだとGoogleに認識してもらうためです。
たとえば「オフショア開発 会社」というキーワードだけ作成しても、サイトの専門性が弱いと判断されれば、上位取得がむずかしくなる可能性が高いです。
そのため、「オフショア開発とは」「オフショア開発 事例」といった関連トピックのコンテンツも拡充していく必要があります。
ステップ4. キーワードからニーズを調査する
作成するコンテンツのキーワード選定ができたら、そのキーワードから検索ニーズを調査していきます。
例えば「英会話教室 おすすめ」と検索した人のニーズを考えてみると、表面的なニーズとしては「おすすめの英会話スクールが知りたい」ということがわかります。だからといってただ英会話スクールを羅列するだけでは、潜在的なニーズまで満たすことはできません。
「英会話 おすすめ」で検索する人は、「自分にあった英会話スクールを知りたい」「いいところが見つかれば英会話スクールを契約したい」「恥をかかない英語力を身につけたい」といった潜在的なニーズがあることが予測できます。このようなニーズを満たすには、費用や通う頻度、オンラインか通学か、講師の質はどうか等の、さまざまな要素が必要です。
よってコンテンツでは、どんな人におすすめの英会話スクールなのか、費用や講師に関する基本情報をまとめる等、ユーザーがどの英会話スクールが自分にあっているのかを判断できるような内容にすることが求められます。
また、同じような内容を掲載しているライバルサイトをチェックすることも、ニーズ調査のヒントになります。上位表示されているページは、ユーザーの満足度が高い(とGoogleが評価している)ページですので、参考にしない手はありません。
とはいえ、同じような内容のコンテンツになってしまえば、評価されるのは難しいです。オリジナルの内容であり、他の競合ページより抜きん出た内容にする必要があります。内容をコピーするなどは、以ての外ですので、絶対にしてはいけません。
ステップ5. コンテンツの執筆
キーワードのニーズ調査ができたら、いよいよコンテンツ執筆に移ります。
コンテンツには、
- タイトル
- リード文(導入文)
- 本文
があります。SEOライティングについては、以下の記事を参考に進めてみてください。

SEOライティングの基礎|初心者向けに書き方のコツをわかりやすく解説
ちなみに、私の場合は、Googleドキュメントで原稿を書きます。推敲して原稿を完成させてから、CMS(Contents Management System)にテキストと写真を入稿します。ちなみにLIGブログの場合、CMSはWordPressです。
文字数はどれくらいがベスト?
どれくらいの文字数すべきかは、キーワードによって変わります。上位に来ているコンテンツの平均文字数を一つの目安としてみると良いでしょう。
タイトル、メタディスクリプション、見出しについて
タイトルは全角30文字前後にします。スマホの場合、表示されるのは約32文字で、パソコンの場合は約28文字なので、記事の主題と副題を30文字前後に収めるようにしましょう。
また、SEO対策では、タイトルとメタディスクリプションも重要です。タイトルは、CMSの入稿画面で、h1タイトルとは別に「SEOタイトル」を設定できることが多いので、SEOタイトルには、SEO効果を最大限にするタイトルを入れます。
公開した記事が上位表示されない場合、メンテナンスとして、SEOを意識したタイトルに修正しただけで、上位に表示されることもあります。
メタディスクリプションは、検索結果に表示される記事の説明文です。記事の概要を伝えるとともにユーザーがおもわずクリックしたくなる文面を考えましょう。文字数は100字程度で作成します。
評価されるコンテンツとは?
Googleは独自のアルゴリズムをもとにページを評価して、記事に順位をつけて検索結果に表示しています。GoogleのSEOについての解説は、Google検索セントラルにまとめられているので、こちらをしっかり読むことをおすすめします。
現在のアルゴリズムで重要視されているポイントについては以下にまとめたので、参考にしてください。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たしているか
かつては、PVを稼ぐことだけを目的とした真偽の不確かな記事が量産されたことがありましたが、Googleのアップデートにより、そうした記事は評価されなくなっています。そして現在、コンテンツSEOにおいてもっとも重要になっているのが「E-E-A-T」です。
「E-E-A-T」とは、
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness (権威性)
- TrustWorthiness (信頼性)
この頭文字をとったもの。そのジャンルの権威者が経験をもとに執筆もしくは監修していること、内容やサイトに高い専門性と信頼性があることが評価の指標となっています。
とりわけ「YMYL」と呼ばれるジャンルのコンテンツには、専門性、権威性、信頼性が必須です。YMYLとは「Your Money or Your Life」の略語で、人生に深い影響を与えるもの、具体的には「お金、健康・医療」などのジャンルです。Googleは、YMYLに該当するコンテンツには特に、高度な専門性・権威性・信頼性を求めています。
これは私の実感ですが、同じ内容・クオリティのコンテンツでも、権威性のある著者が執筆・監修しているかで評価がかなり変わってくるなと。つまり、その分野の専門家ではない人が書いた記事は、内容自体がよかったとしても、上がりにくくなってきたことを感じます。
オリジナリティ(独自性)があるか
コンテンツを検索結果に上位表示をさせるためには、そのコンテンツならではのユニークな内容、オリジナリティ(独自性)があるかどうかも重要です。
特にコンテンツSEO初心者の方がやりがちなのが、上位表示されているコンテンツを真似てコンテンツを作成することです。書き手が自らの目と耳で調査・取材したり、検証したりすることなく、すでにネット上にある情報や憶測を寄せ集めた信頼性のない記事は、まず上位表示はしないでしょう。
情報が最新であること
最新情報を伝えている記事が上位表示される傾向にあります。そのため、常に更新して、最新の情報にアップデートする必要があります。
網羅性があること
Googleはコンテンツを評価するときの指標として滞在時間を見ています。滞在時間が長い(じっくり読まれている)ことが評価につながります。ユーザーにとって内容が薄かったり、期待した内容と違ったりすると離脱率が上がるので「詳しいこと(網羅的であること)」と同時に、その内容が「わかりやすいこと」が大切です。
また、コンテンツにはなるべく自社サイト内の関連記事を紹介して内部リンクを張ることも効果的。これは「もっと詳しく知りたい」というユーザーのニーズに応えられるので、ユーザビリティ(ユーザーにとっての利便性)の高いサイトとしてSEOに効果があります。また、内部リンクを設置することでGoogleのクローラーがサイト全体を巡回しやすくなるため、しっかりとした評価を得ることができるでしょう。
コンテンツSEOで成果を出すためのポイント
定期的な見直し・リライトを行う
コンテンツSEOで成果を出すには、記事を公開して終わりではなく、メンテナンスやリライトをしていく必要があります。リライトとは、さらに記事のクオリティを上げ、情報をアップデートするために書き直す作業のことです。
SEOのためのリライト方法は、まずSearch Consoleで、その記事が実際にどのようなキーワードで上位表示されているかをチェックします。
たとえば、この記事を例に説明します。
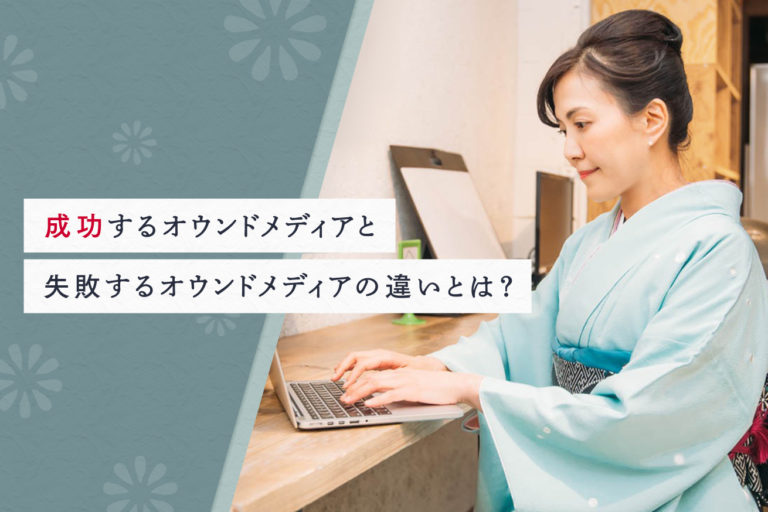
成功するオウンドメディアと失敗するオウンドメディアの違いとは? 編集者の個人的経験による考察
URLをSearch Consoleの「検索結果」で調べると、以下のような情報が出てきます。

チェックするポイントとしては、「表示回数」が大きいのに「クリック数」が少なく上位表示できていないクエリ(キーワード)を探します。この場合は「オウンドメディア 失敗」「オウンドメディア 個人」「オウンドメディア 失敗事例」がそれに該当します。掲載順位が5〜10位くらいで止まっているキーワードで、あらためてユーザーの検索意図を考えて、ソリューションになるような情報や文章を追加することにより、その記事の掲載順位を1〜2位に上げていく、ということをします。
継続的なコンテンツ配信
コンテンツSEOは、継続的にコンテンツを発信していくことで成果が得られるマーケティング手法です。そのため、最低でも半年以上はコツコツと更新を続ける必要があります。
逆に言えば、成果がでない中でもやり続けなくてはいけない時期が必ずあるということです。続けるには経営層の理解も必要ですし、何より運営に携わるメンバーの強い意志が必要です。
ぜひこれからコンテンツSEOを始めるには、この点にも留意して、運用をスタートさせてください。
【随時更新】SEOの最新&有益情報を提供してくれるフォローしておきたいTwitterアカウント
SEOに関係する最新&有益情報を発信されているTwitterアカウントをご紹介します。いつも参考にさせていただいております(大感謝!)。まだフォローしていない方は、フォローするのが吉!
- 鈴木謙一さん @suzukik
- 辻正浩さん @tsuj
- SEOおたく@LANYさん @seootaku
- おおきさん @ossan_mini
- 小川卓さん @ryuka01
【随時更新】コンテンツSEOのワザ!最新情報まとめ
コンテンツSEOの成功を左右するGoogleのアルゴリズムは、どんどんアップデートされていくので、常に最新情報にアンテナを貼っていないと遅れをとってしまいます。日々刻々とルールが変わっていく、それがこのコンテンツSEOの世界です。
というわけで、最新のSEO情報を、自分のためにもメモとしてここに記載していきたいと思います。
できるだけ早く、ユーザーのニーズを解決する
Semrush Blogによると、2023 年に最も効果的な高度なSEO戦略として、ユーザーが疑問を解決するまでの時間を短縮することを紹介しています。
コンテンツを充実させるための予備知識は、後半に持っていくなどして、ユーザーのメインニーズの答えにすぐ辿り着けるような構成を目指しましょう
戦略的な内部リンク
同じくSemrush Blogでは、被リンクについても言及されていました。意味的にもトピック的にも関連性のあるページから、最も重要なページにリンクを張ることを推奨しています。
また、その歳のアンカーテキストについて、リンク先のページの主要キーワードと同じ検索意図を持つ、説明的なアンカーテキストを使用する必要があります。
つまり、そのアンカーテキストを読んでリンクに飛んだユーザーが、コンテンツを読み進めたときにギャップがないようにすべき、ということですね。
LIGは自社メディア「LIGブログ」で培ってきた経験をもとに、オウンドメディア立ち上げ初期の企業様のお手伝いをすることができます。オウンドメディア運用でお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。