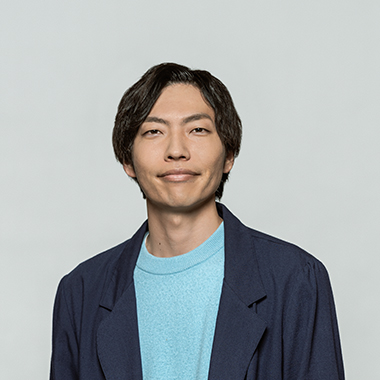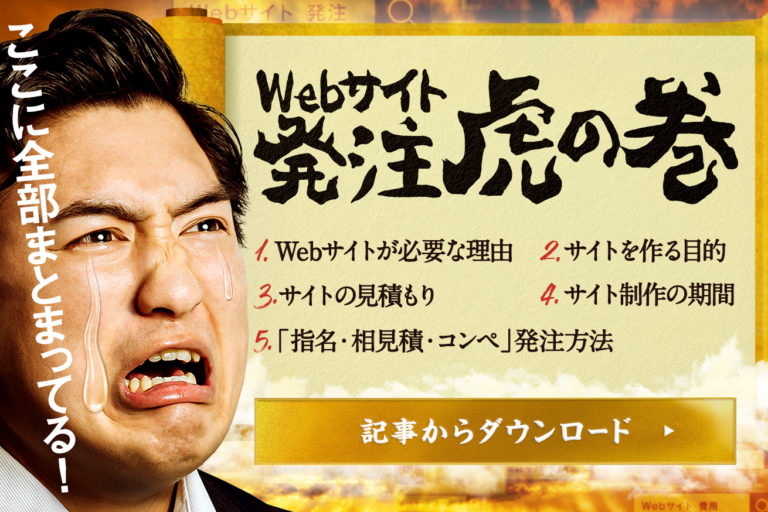みなさんこんにちは。LIGの経営企画室のきゃしー大西です。
今日は、「そろそろ人事労務もしっかりやらなきゃなあ」と経営者が思ったときにぜひ読んで欲しい大事なことをまとめました。
社員を雇う場合、ただ給料日がきたらお金を振り込めばいい、というものではありません。もしやるべき人事労務をやらなかった場合どうなるでしょう。
一番のリスクは「労務訴訟」です。
もし社員と揉めて裁判になったとき、会社としてやるべきこと、決めるべきこと、手続きすべきことを怠っていた場合、負ける可能性が高いのは会社側です。そうならないために大事なことは、たとえ社員が1人しかいなかったとしても、最低限会社としてやらなければいけないことはきちんと押さえておくことです。
今回は、人を雇った時に会社としてやらなければいけないことをまとめているのでぜひ読んでみてください。
目次
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する
人を雇ったらまず押さえたいのが「労働保険の加入」です。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称を言います。労働保険の管轄は労働基準監督署、ハローワークで、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、人を1人でも雇ったら必ず加入しなければいけない会社の義務。そして、労働保険に加入しておくと「もし社員に何かあったとき」に非常に安心な制度です。
労災保険
社員が仕事や通勤が原因でけがなどをした場合や、病気で亡くなった場合に社員やその家族を保護するための給付をしてくれる制度です。療養補償給付、労災年金などがあります。
雇用保険
社員が失業した場合に、失業期間の生活の安定のためと再就職の促進を図るための給付をしてくれます。雇用保険には社員全員が加入するわけではなく、加入条件があり、失業手当、再就職手当、教育訓練給付金、育児休業給付、介護休業給付などがあります。
業務中に怪我をしたとき、通勤途中に事故にあった場合などは、「会社の責任」を問われます。もし社員が半身不随になるような大怪我をした場合、どれだけの損害額になるかわかりません。労災保険に加入しておけばそちらからの手当が支給されますが、もし加入していなかったら会社がその補償をしなければならなくなります。
加入した場合の保険料負担ですが、労災保険は全額会社負担、雇用保険は事業主と社員の両方が負担します。おおよそどれくらいの保険料になるかは以下の通りです(料率は令和2年を使用しています)
- 例)
- 年収350万円(情報通信業の場合の料率を使用)
料率:労災保険率=3.0/1000 雇用保険率=9.0/1000
年収350万円× ( 3.0/1000 + 9.0/1000 ) = 42,000円/年
(うち雇用保険は事業主負担6.0/1000、従業員負担3.0/1000)
会社としての経費負担は決して小さくはありませんが、万が一何かあったときの補償として、きちんと手続きをしておきましょう。
労働条件通知書(雇用契約書)を作成して社員に交付する
次に大事なことは入社する社員に「労働条件通知書(雇用契約書)」を交付することです。労働契約を結ぶときには、会社が社員に労働条件を明示し、口約束ではなくきちんと書面を交付する必要があります。
これは労働基準法第15条に定められた義務です。この労働条件を明示した書面のことを労働条件通知書といいます。
労働条件通知書の雛形は厚生労働省HP主要様式ダウンロードコーナーの労働基準法関係主要様式「労働条件通知書」の中にあるので、そちらを参考に作成してください。
労働条件通知書には以下のようなことを記載します。
- 契約期間
- 更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかた
- 仕事をする場所
- 仕事の内容
- 仕事の始まりと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど
- 賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期
- 退職に関すること
- 社会保険・雇用保険の加入の有無
一方で、労働条件通知書に盛り込んではいけない内容もあります。
- 社員に違約金を支払わせることや、その額をあらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
- 労働を条件として社員に給与を前貸しし、毎月給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
- 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
1の社員の違約金については、たとえば「1年未満で会社を退職したときはペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止しているものです。
しかし、社員が故意や不注意で、会社に損害を与えてしまった場合についての損害賠償請求が全くできない、という意味ではありません。まず就業規則に「会社に損害を与えた場合は、その損害の金額を請求することがある」と書いてあることが大前提で、社員に賠償請求できるのはあくまで事故が起きた後の実損額(のうちの一部)です。
2については、社員が会社からの借金のために辞めたくても辞められなくなることを防止するためのものです。しかし社員のほうから頼まれて、会社が社員にお金を貸し付けることは可能です。この場合は、労働を条件とした前借金ではなく、「社内貸付制度」を利用してお金を貸し付けることになります。
該当社員と会社が毎月の給料から天引きによる返済に合意し、かつその合意が社員の自由意思に基づくものであることが必要です。あくまで自由意志なので、月5万円返済と取り決めをしていても、「今月は給与が少ないので3万円のみ返済したい」という希望が出ることもあります。いずれにしても、会社と社員との間で「労使協定」を取り交わすことが必要です。
3については、社員旅行など社員の福利厚生のためでも「強制的に」積み立てさせることは理由に関係なく禁止されています。ただし、社内預金制度がある場合など、社員の意思に基づいて会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。さきほどの社員旅行も労使協定を結んでいる場合はOKです。
就業規則を作成して提出する
次に大事なことは、就業規則を作成して労働基準監督署に提出することです。就業規則とは、会社のルールを定めた服務規程と、待遇を定めた労働条件が記載されたものです。従業員を常時10人以上雇用している会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署への届出が原則として義務づけられています(労働基準法第89条)。
ただ就業規則を定めればどのような取り決めも効力を発揮するわけではありません。就業規則に定めていても、労働基準法を下回っている内容のものは無効ですし、社会通念上、合理性に欠く内容も無効になる場合があります。
就業規則については下記をぜひお読みください。
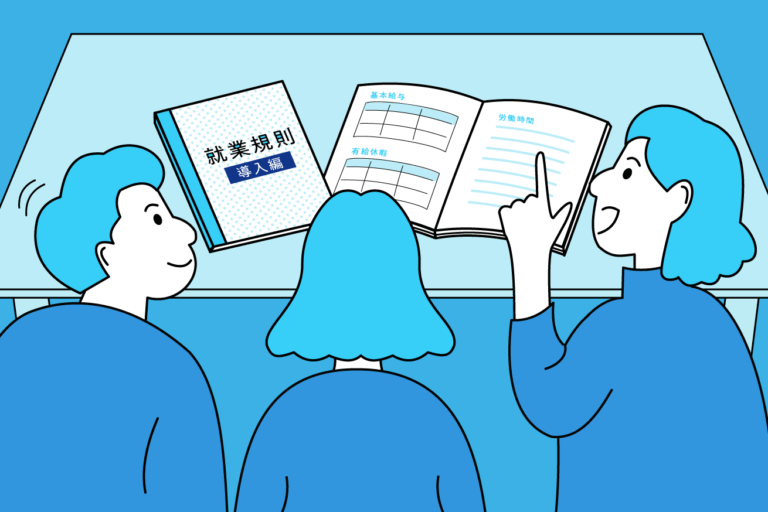
就業規則作成の実務のポイント(導入編)
36協定(さぶろくきょうてい)を締結し、提出する
次に、「36協定(さぶろくきょうてい)」を締結し、提出します。36協定とは、会社が社員に「残業」を命じたい場合に提出する書類のことです。労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間・1週40時間以内」とされています。これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて社員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出をするのが決まりです。もし、36協定を締結せずに法廷労働時間外の残業をさせると、労働基準法違反となり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。通常はいきなり罰則が科されるわけではなく、是正勧告が先にあることが一般的ではあります。
そして2018年6月に労働基準法が改正され36協定で定める時間外労働に「罰則付きの上限」が設けられました。
時間外労働(残業)の上限
- 時間外労働の上限は月45時間・年360時間
- 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない
- 月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
36協定の書類自体はA41枚なので、それほど作成に時間はかかりません。雛形は厚生労働省HP労働基準法関係主要様式の「時間外労働・休日労働に関する協定届」をダウンロードして作成してください。
社会保険に加入する
社会保険とは健康保険(介護保険)・厚生年金保険の総称で、管轄は社会保険事務所、年金事務所です。
会社にとっては労働保険よりもさらに金額の負担が大きいので、人を新たに雇うときには社会保険料負担分も考えて賃金設定をしなければいけません。社会保険の加入義務のある会社は以下の通りです。
社会保険適用対象の事業所
- 事業主(社長)を含む社員1人以上の会社や法人
- 常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所
社会保険の強制加入の対象者(被保険者)
- 法人の代表者
- 役員
- 正社員
- 試用期間中の社員
- 外国人社員
- 加入要件を満たしたパート・アルバイト
社会保険事務所は定期的に会社に対して調査を実施していて、その頻度は場合によっては税務調査よりも多い、とも言われています。もし立入検査等で未加入が発覚した場合は、過去2年分の保険料が徴収されます。また、罰則として「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されることも。罰則があるからというわけではありませんが、きちんと加入しましょう。
おおよそどれくらいの保険料になるかは以下の通りです(料率は令和2年を使用しています)。
- 例)
- 月給25万円(40才未満、東京の場合)
・健康保険料 社員負担:12,831円 会社負担:12,831円
・厚生年金保険料 社員負担:23,790円 会社負担:23,790円
労働者名簿・出勤簿・賃金台帳
人事労務関係の書類の中には、労働基準法107条から109条によって作成・管理が義務付けられているものがあります。それが法定三帳簿とも呼ばれている「労働者名簿・出勤簿・賃金台帳」です。
実際、実務においても利用する頻度が非常に高く、きちんとした形で作成・保管しておくことは経営にとってもプラスしかありません。最近ではシステムでこの3つを網羅していることが多いですが、エクセルなどで管理してもOKです。もし雛形が必要な場合は、こちらも厚生労働省HP主要様式ダウンロードコーナーの「労働者名簿」をダウンロードして作成してください。
労働者名簿
労働者名簿とは、その名の通り社員の情報が記載された名簿です。基本的にはどこかに提出する書類ではありませんが、社会保険事務所や税務署、雇用関係など調査に入られた時などは提出を求められます。
また、年末調整や入退社、社会保険の加入脱退などは、労働者名簿の情報を元に書類を作成するので、常に最新の状態にしておくと良いでしょう。
労働者名簿記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 社内での履歴(特に法令ではその記載範囲について明確には示されていないので、自由に記述できます)
- 性別
- 住所(転居などで住所変更した場合などは、その都度更新。現住所と住民票住所は別で記載しておくと良いです)
- 従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業では、記入は必須ではありません)
- 雇用年月日
- 退職や死亡年月日とその理由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を明記する必要があります)
出勤簿
出勤簿については、労働基準法の条文において作成に関する明確な規定はありません。出勤簿に含める社員は雇用形態に関係なく全員ではありますが、「管理監督者」は必ずしも記載する必要はないとされています。ただしこの場合の管理監督者とは、経営者と同等の権限を持ち、基本的には出勤の義務そのものがない自由裁量が認められている立場の人のみとなります。
昨今では、未払い残業代の請求などの問題もあるので、登記された役員以外の社員は全員記載するのが望ましいでしょう。システムを導入するなどして、本人の勤怠実態を正しく反映した出勤簿にすることが大切です。
出勤簿記載事項
- 各労働者の出勤日と労働日数(出社・退社時刻を含む)
- 日別の労働時間数
- 時間外労働を行った日付と時刻・時間数
- 休日労働を行った日付と時刻・時間数
- 22時から翌5時までの深夜労働を行った日付と時刻・時間数
賃金台帳
賃金台帳もその名の通り、社員の給与についてまとめた台帳です。こちらは記入すべき項目が決まっています。源泉徴収票や離職票の作成などは、賃金台帳の情報を元に行います。作成はエクセルなどでも大丈夫です。
ただし理想としては、勤怠情報がシステム化しているのであればその情報を読み込み、残業代などを正しく賃金台帳に反映すると良いと思います。社員数が多くなってきたら勤怠と給与を連携したシステムの導入を検討するのも良いでしょう。
賃金台帳記載事項
- 氏名
- 性別
- 該当月(何月分給与)
- 労働日数
- 労働時間数
- 残業時間・休日・深夜労働時間数
- 基本給・諸手当・その他の賃金ごとの金額
- 社会保険や所得税など税金の控除額、その他控除
おわりに
最低限抑えたいことをまとめてみましたが、実際にはやっておくべきことはもっともっとたくさんあります。人を雇う時に会社のリスクとして一番大きいことは「揉め事」です。これを回避するためにも、会社として最低限やらなければいけないことはきっちり押さえておきたいですね。
そして、社員数が増えてきたらシステムを導入するなどして、かかる工数も減らしていくと良いでしょう。もっとも、システムを導入することで逆に増えてしまう工数もあるのですが……それはまた別の機会に。