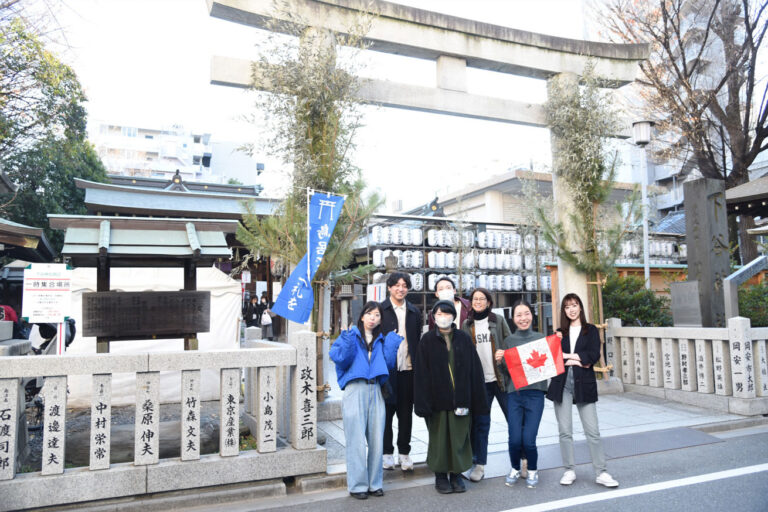下町の路地裏。赤錆びたトタン、古い民家、電線が交差する空の下で、静かにシャッターを切る音がします。

「被写体の“利き顔”を探したり、身につけているものに目を向けたり。撮る前に、自然といろんな情報をキャッチしてますね」
そう話しながら、私にもカメラを向けてくれたミケロンさん。
軽く帽子に触れるような仕草を促されると、不思議と表情がやわらかくなっていくのを感じました。
 ▲実際にミケロンさんが撮ってくれた、筆者写真。
▲実際にミケロンさんが撮ってくれた、筆者写真。
「ちょっとしたコミュニケーションで、写真に動きやアクセントが生まれるんです」
撮影現場での所作や言葉には、プロのフォトグラファーとしての経験と感性がにじんでいます。そんなミケロンさんの現在の職業は、実はWebディレクター。
「正解のない仕事だからこそ、これまでの経験が自分の“色”になる」
研究者、エンジニア、フォトグラファー。そしてWebディレクターへ。多彩なキャリアを歩んできたミケロンさんに、自分の“色”を活かす仕事について聞きました。

|
LIG Creative部 Webディレクター 村上 慶太朗(ミケロン)大学では分子遺伝学を学び、卒業後はSEとしてシステム開発に従事。その後、師匠との出会いをきっかけにプロのフォトグラファーとして活動を開始し、広告撮影や雑誌媒体などで経験を積む。現在はLIGで企業サイトや採用サイトの制作ディレクションを担当し、技術とクリエイティブをつなぐ“舵取り役”として優しくチームをリードしている。👉️メンバーページ |
|---|
研究者、SE、フォトグラファーという異色の経歴
── 学生時代は、動物の研究をされていたんですよね?
 ▲この日は炎天下での取材でした。容赦なく降り注ぐ太陽。
▲この日は炎天下での取材でした。容赦なく降り注ぐ太陽。
はい。大学・大学院では農学部に通っていて、動物の保全をテーマに研究していました。大学は神奈川でしたが、沖縄が好きで、琉球大学の先生とつながって、西表島や石垣島などに定期的に通っていました。
「リュウキュウイノシシ」という沖縄固有の種を研究していたのですが、論文も何本か書いて、学術誌に掲載されたこともあります。「やれるだけやったな」と思えたタイミングで、研究の道は一度離れることにしました。
── 研究の道を離れて、最初に就職したのはどんな会社だったんですか?
富士ゼロックスという会社でした。当初はプログラミングを担当していましたが、徐々に上流工程に関わるようになり、業務設計や効率化の提案などがメインになっていきました。
たとえば工場の製造ラインで、「ムリ・ムダ・ムラ」を削減するために導線を見直したり、紙ベースの工程をシステム化したりといった提案をしていました。今でいうDXに近いことをやっていたと思います。
── そこから一転、写真の道に進まれたきっかけは何だったんですか?
SE時代に手がけていたのって、あまり人目に触れない仕事だったんですよ。工場のシステムって、一般の人が直接見るものではないですし。でも、自分は「人に喜ばれる仕事がしたい」「リアクションが見える仕事がしたい」とどこかで思っていたんです。
そんなときに出会ったのが、フィルム時代から活躍されていた写真家の師匠でした。雑誌の第一線で活躍されていた方で、1年間、弟子入りのような形でみっちり教えてもらいました。機材の扱いから構図の考え方、現場での振る舞いまで、すべて出し惜しみなく伝えてくれたんです。
── そこから、会社を辞めて本格的に?

はい。一眼レフを初めて買ったのが2017年で、翌年には会社を辞めました。最初はカルチャー誌のスナップやアーティスト、芸人さんなどの撮影を運良く任せていただいて、その後はWebメディア用の写真、ルックブック、広告ビジュアル、映画やドラマのスチールなど、幅広いジャンルに携わるようになりました。
── 撮影時に大切にしていることはありますか?
「写真ってセンスがすべて」と思われがちですが、実はロジカルな要素も大きいんです。たとえば“3分割構図”という基本があって、被写体を中心から少し外した位置に置くことで、余白をどう活かすか、背景にどんな意味を持たせるかが変わってきます。構図を意識することで、写真に情報やストーリーが生まれるんです。
── 実際、私も撮っていただきましたけど、自然な表情を引き出すのがすごく上手だなって……!

ありがとうございます(笑)。ちょっとしたコミュニケーションで、印象って大きく変わるんです。たとえば「帽子のこのあたりを軽く触れてみましょう」とか具体的な声かけをしたり、モデルさんとちょっと雑談して打ち解けたり。ほんの少しのことで、当たり障りのない写真から、その瞬間にしか撮れない写真になるんですよ。
Webディレクターとしての現在
── フォトグラファーとして順調に活動されていた中で、なぜWebディレクターという道を?

きっかけはコロナでした。撮影の仕事が一気に減って、このままではまずいと感じ「もう一つ軸を持とう」と考えました。Webサイトの撮影を多く手がけていたこともあり、「サイト自体も作れるようになれば強みになる」と思ったんです。
── もともとSE出身ですし、親和性はありそうですね。
そう思って独学で始めたのですが、思った以上にWebの世界は深くて……。ちゃんと学ぼうと制作会社に転職し、一から現場で経験を積みました。その後、もっと上流の提案やクリエイティブにも関わりたいと思って、LIGへの転職を決めました。もともとLIGブログの読者だったので、思い切って応募しました。
── 現在はどんな案件を担当されているのでしょうか?
コーポレートサイトや採用サイトのリニューアルなど、比較的規模の大きなクライアントの「新規制作」と「運用保守」の両方に携わっています。ディレクターとしては、クライアントの要望を整理して制作チームに橋渡しする舵取り役を担いながら、社内外の調整や進行管理を行っています。
── ディレクターとして、大事にしているスタンスはありますか?

「ディレクターがぜんぶ決めすぎない」ことです。デザイナーさんはセンスと感性のかたまりだし、エンジニアさんは技術の探求者。僕はその道のプロではないので、それぞれが最大限のパフォーマンスを出せるよう、制作チームからの提案を受け入れる余地を残しながら、お客様とのコミュニケーションを心がけています。
── チームでベストを出すための、空気づくりというか。
まさにそうですね。最大限のパフォーマンスを発揮し、良い成果物を生み出すには、社内のコンディションもすごく大事。みんなが前向きに楽しんで仕事できるような空気をつくるのも、ディレクターの大事な仕事だと思っています。
あなたは、どんな“色”のディレクター?
── 今後、どんなディレクターを目指していきたいと考えていますか?
Webサイトって、あくまで手段のひとつだと思っていて。もちろん重要な役割を担うものだし、価値も大きいんですが、クライアントの課題を解決するためには、それだけじゃ足りない場面も増えてきています。
── たしかに、SNSや広告、AIなども絡んできますよね。
そうなんです。検索もAIに代替されていく時代に、何が本質的な課題なのかを見極めて、それに対して複合的に提案できるようになりたいと思っています。「サイトを作る人」ではなく、「課題解決のために伴走できる人」として存在したいんですよね。
── まさにWebディレクターという職種の枠も広がっていきそうですね。

そうですね。研究者時代に身についた「事実ベースで判断する」習慣や、SE経験によるエンジニアさんとの円滑なコミュニケーション、そして自分でも写真を撮ることで培った現場感覚が、それぞれディレクション業務に活かされている……と、手前味噌ながら感じています。
── 経験が強みになっているんですね。そうした多様な背景を持つ人たちと一緒に働けるのも、LIGの魅力の一つかもしれません。最後に、LIGで働くことに興味を持ってくれている人にメッセージをお願いします。
これまでのキャリアは、間違いなく僕にしかない“色”です。Webディレクターという仕事は、その人のキャリアや個性がそのまま武器になる職種なんだと思います。
だから、自分の色をどう活かせるかを考えてみてほしい。そしてもしその色が、LIGという場所で輝くと感じたなら、ぜひ一緒に働けたらうれしいです。

さいごに
撮影のあいだ、何度も「すごく自然ですね」と声をかけてしまいました。それは表情やポーズだけでなく、ミケロンさんの人柄そのものに対して感じていたのかもしれません。
相手の“利き顔”を探りながら、そっと背中を押すように導いてくれる姿には、彼が大切にしている「平和を好む性格」がにじんでいました。撮る側も、撮られる側も、どちらもリラックスしていられる……そんな柔らかな空気をつくれる人なのだと、あらためて感じました。
そしてどの道も「趣味」や「少しかじった」で終わらせることなく、プロとしてやりきってきたからこそ、それぞれが強みとして今に活きている。そんなふうに思います。
次はあなたも、LIGという環境で自分らしい色を発揮してみませんか?