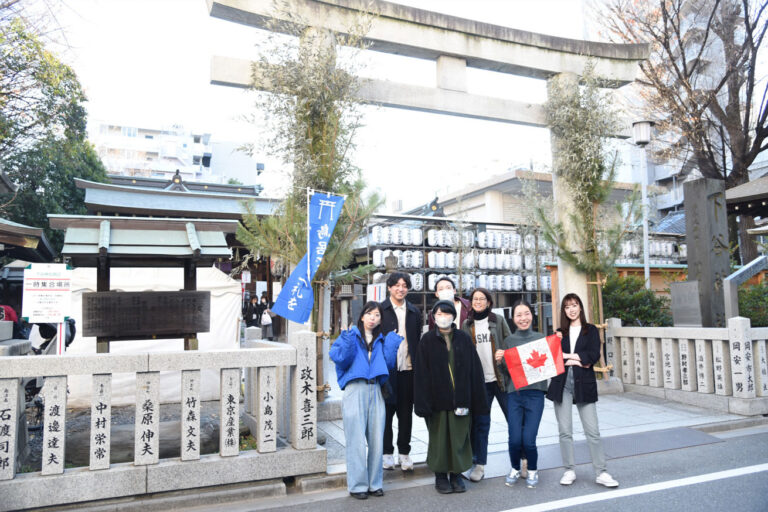「言語ができるだけでは、日本の企業で働くには足りない」
そう語るのは、ベトナム出身でトリリンガルのブリッジディレクター・ジャンさん。アニメへの憧れから始まった日本語学習を経て、現在は日本とセブの開発チームをつなぐ架け橋として活躍しています。
大学時代に日本の組織文化の違いを痛感し、入社後は今度はセブと日本の文化の違いに直面。そうした異文化間のコミュニケーション課題を解決する「ブリッジディレクター」としての仕事術を教えてもらいました。
日本で働きたいと考える海外の方や、言語力を活かしたキャリアを目指している方の参考になれば幸いです。

|
LIG DX事業部 ブリッジディレクター Le Hoang Giang(ジャン)ベトナム・ハノイ出身。高校卒業後に来日し、日本語学校を経て日本の大学へ。経営学部で組織論を専攻し、大学祭実行委員会やアルバイトを通じて日本の組織文化を学ぶ。2022年にLIGに新卒入社。現在は大手ファッションECサイトの開発案件で、日本とセブの開発チームをつなぐブリッジディレクターとして活躍中。👉️メンバーページ |
|---|
アニメから始まった日本語学習の道のり
――ジャンさんは日本語・英語・ベトナム語のトリリンガルとして活躍されていますが、そうした語学力はどのような環境で育まれたのでしょうか?

ベトナムのハノイで生まれ育ちました。両親が教育関連の仕事をしていて、教育に対する意識がとても高い家庭だったので、幼い頃から語学教育に力を入れてくれていたんです。
中学校までは英語をメインに勉強していたのですが、高校に入ってからアニメや漫画にハマって。『SLAM DUNK』や『君に届け』などを見ているうちに、いつか字幕なしでアニメを楽しめるようになりたいと思い、日本語の勉強を始めました。
――アニメがきっかけというのは素敵ですね。実際に日本に来るまでの経緯も教えてください。
当時すでに日本語能力試験のN2を取得していたので、そのまま日本の大学に入学できるコースもありました。でも、まずは日本語学校でしっかりと基礎を固めてから大学に進学したいと考えたんです。
ところが、日本語学校は周りがみんな外国人留学生で、日本語のレベルもそれほど変わらず、時には英語で会話してしまうこともありました。いざ大学に入って日本人学生と話してみると、若者言葉がまったく理解できなくて。「やばい」という言葉一つとっても、何を意味しているのかさっぱりわからない状態でした。
――どのような学生生活を送られたんですか?
印象に残っているのは、大学祭実行委員会での3年間の活動です。外国人は私一人だけという環境で、会話はすべて日本語。土日には朝から夜までミーティングが行われることもあり、最初は内容を理解してメモを取るだけでも精一杯でした。
ただ、この大学での経験が私の日本語力を飛躍的に向上させてくれましたし、なにより日本人や組織運営の特徴を肌で感じることができました。
――実際に日本人の組織に身を置いてみて、どのような特徴が印象的でしたか?
一番驚いたのは、グループワークで誰も最初に自分の意見を言わないことでした。みんな周りの様子を伺いながら、「そうですね」「たしかに」といった相槌は打つのですが、積極的に自分の考えを発信しようとはしないんです。
私はそのことを知らずに、沈黙が続いたタイミングで「私の意見ですが……」と話し始めたところ、場の空気が一変してしまって。あとから「あの子、主張が強いよね」という評価をされていることを知り、日本の組織文化の難しさを痛感しました(笑)。
――LIGとの出会いのきっかけはなんだったんですか?
実は、LIGからオファーを受けていたベトナム人の友人が紹介してくれたんです。「こういう会社からオファーが来たけど、あなたに合いそうだから見てみたら?」と。それでWantedlyからあらためて自分でアプローチして、説明会に参加することになりました。
――その友人、ナイスですね(笑)。説明会に参加してみて、どうでした?
社員のみなさんが、趣味や遊びも全力で楽しみながら、仕事に対して真摯に取り組む姿勢に、魅力を感じました。また、セブとベトナムの拠点があるということで、トリリンガルとしての強みを活かせる環境だと感じたんです。
失敗から学んだブリッジディレクターの真価
――現在はどのような業務を担当されていますか?

大手ファッションECサイトの保守・運用と新機能開発を担当しています。クライアントからの要件をお聞きしたあと、必要に応じて要件の詳細調査や設計を行い、海外拠点のセブ(CODY)に実装とテストを依頼するという流れです。
一般的なディレクター業務に加えて、いわゆる「ブリッジ」の役割も担っています。通常、他のメンバーは翻訳ツールを使ってSlackでやり取りしているのですが、それでは伝わりきらない複雑な内容や、リアルタイムでの議論が必要な場面では、私が間に入ってコミュニケーションをサポートしています。
――ブリッジディレクターとして働く中で、印象に残っている出来事があれば聞かせてください。
入社間もないころ、あるプロジェクトで日本チームとセブチームの間で深刻なコミュニケーション不全が起きてしまったことがあります。
当時の私はシステムに関する知識が乏しく、他のメンバーも翻訳ツールを使ってコミュニケーションを取っていたのですが、うまく伝わらなくて。その結果、セブ側から上がってくる成果物が日本側の期待とはかけ離れたものになってしまったんです。
一番辛かったのは、日本側は「セブに問題がある」と感じ、セブ側は「日本側の指示がはっきりしていない」と感じるような、お互いを責める状況になってしまったことです。
――大変でしたね。そういうすれ違いって、なぜ起きてしまうのでしょうか?
結局のところ、指示が曖昧ということに尽きると思います。システムの知識不足で具体的な指示が書けないということもありますし、日本では当然なことがセブでは当然ではないということもあります。言わなくてもわかるだろうと思って依頼したら、想像と違うものが上がってきてトラブルになるパターンですね。
――いわゆる「よしなにやっておいて」ってやつですね。
まさにそうです。たとえば「これを調査して原因を書いておいて」という依頼でも、日本人なら調査レポートや修正方法まで含めた包括的な対応を期待しますが、セブ側には文字通りの意味しか伝わりません。
そもそも品質管理に対する意識も違います。日本人は非常にレビューが厳格で、細かな部分まで徹底的にチェックします。それがあるからこそ高い品質を保てているわけで、これは日本の素晴らしい特徴だと思います。
一方、セブのエンジニアは開発スピードが非常に速く、技術力も高いのですが、確認作業に関しては日本ほど細かくチェックしない傾向があります。
――なるほど。そうした課題に対して、現在はどのような改善を図られているのでしょうか?

誰が読んでも同じ理解に到達できる明確な指示書を作ることを徹底しています。受け手によって解釈が分かれる余地のない、具体的でわかりやすい文章を心がけています。
加えて私が意識しているのは、温度感の共有や背景情報の説明です。日本側では共通認識として進んでいる話でも、その前提がセブ側に十分伝わっているとは限りません。「この情報も必要だろう」と先回りして判断し、詳細な説明を付け加えています。
――すごく細やかなコミュニケーションをされているんですね!
「なぜその作業が必要なのか」を理解してもらえると、メンバーの取り組み姿勢が格段に変わるんです。モチベーションも上がりますし、結果として成果物のクオリティも向上します。
真の国際人材になるために必要なこと
――現在のお仕事にもやりがいを感じていると思いますが、今後はどのようなキャリアを考えていますか?
将来的にはPM(プロジェクトマネージャー)として活躍したいです。システムの知識もしっかりと身につけて、設計から開発チームのマネジメントまで、プロジェクト全体を統括できるような存在になりたいんです。
現在はディレクターとして働いていますが、正直まだシステム面での知識が不足していると感じています。なので、技術的な理解を深めながら、案件の進捗管理といったマネジメント業務にも少しずつ挑戦していこうと思っています。
――最後に、日本で働きたいと考えている海外の学生や、語学力を活かしたキャリアを目指している学生にメッセージをお願いします。
ちょっと厳しいことを言うかもしれませんが、最近外国人の方の採用面接にも参加させていただく中で実感するのは、日本語の読み書きや会話ができるだけでは、日本企業で活躍するには不十分だということです。
ぜひ学生のうちに、大学のサークル活動や部活、アルバイトなど、日本人が多い組織で実際に働く経験を積んでください。そして、その中で日本人の考え方や組織の動き方を意識的に観察し、学んでほしいと思います。
語学力はたしかに武器になりますが、それだけでは足りません。日本の組織文化を理解し、その中で力を発揮できる経験こそが、本当の強みになると思います。

さいごに
ジャンさんのお話を聞いていると、ブリッジディレクターの本当の価値が単なる言語の翻訳ではなく、お互いが歩み寄れる信頼関係を築くことにあることが伝わってきます。
実際、ジャンさんはプライベートでセブに渡航してチームメンバーと交流を深めたり、週末にはメンバーとキャンプに出かけたりと、非常にフットワークが軽く、積極的に人間関係を築かれています。
オフショア開発において、技術的なスキルと同じくらい重要な「人と人をつなぐ力」。ジャンさんの体験談が、同じような道を歩もうとする学生のみなさんの参考になれば嬉しいです。

多様性を重視するLIGで、あなたらしいキャリアを築いてみませんか?
▶︎ 採用情報はこちら
▶︎ カジュアル面談のお申し込みはこちら