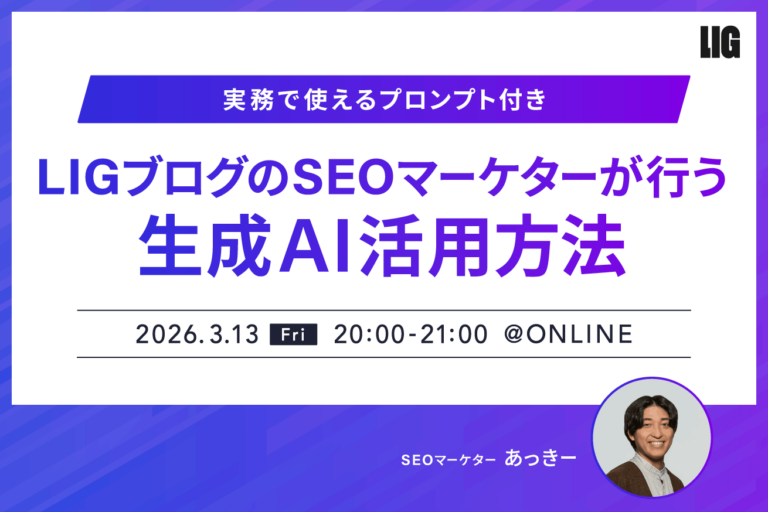LIGエージェントのキャリアドバイザー、大澤です。
クリエイターの方々の採用を支援させていただくなかで、企業の担当者様から「デザイナー向けの評価制度は必要?」「どうすれば適切な評価ができるのか教えてほしい」という悩みをお聞きすることがあります。
評価制度は給与体系やキャリアパスにも大きく関わるため、ひいては定着率にも影響を及ぼします。そこで今回はLIGエージェントでさまざまな企業のクリエイター採用を支援させていただいている私が、デザイナーの評価制度について作り方や注意点などを解説します。
目次
デザイナーの評価制度が重要な理由
デザイナーの評価制度が重要な理由として、以下3つの観点で解説します。
- 1.定性的な評価に偏りすぎることを防止できる
- 2.キャリアステップの設計やモチベーション向上に役立つ
- 3.採用競争力を強化できる
1.定性的な評価に依存しすぎてしまうから
デザイナーの業務は、セールス部門のように明確な数値だけで評価しにくい側面があります。その結果、評価が評価者の印象に左右されるなど、定性的な要素に偏ってしまうことがありがちです。また、人事担当者としても、評価の客観性や説明責任を問われた際に、明確な根拠を示しにくいのも問題です。
こうした状況を避けるためにも、明確な評価基準を設けることは重要です。そうすればデザイナー自身も納得感を持って業務に取り組め、スキルや業績を給与、役職といった処遇を客観的に判断しやすくなります。
2.キャリアステップの設計やモチベーションの向上に役立つから
評価制度は給与体型だけでなく、キャリアステップ設計のためにも重要です。デザイナーのキャリアパスが不明確だと「この会社で本当に成長していけるのかな……」と不安になり、離職の原因になってしまうかもしれません。また、日々の頑張りがどのような形で評価され、どんな形で還元されるのかが見えづらいと、仕事に対するモチベーションも左右されてしまいます。
デザイナーにとって、明確な評価基準やそれにもとづいた役職・キャリアパスを設計することは、成長の道しるべとなります。「ジュニアデザイナーにはこのスキルが必要」「シニアデザイナーにはこのくらいの成果を求めたい」など、具体的な目標を設定すれば、本人のキャリア開発を促す効果も期待できます。
3.採用競争力を強化できるから
レバテック株式会社が発表した「ITエンジニア・クリエイター 転職/フリーランス市場レポート(2023年12月)」によると、現在即戦力デザイナーの有効求人倍率が7.4倍。つまり、1人のデザイナーを7社で取り合っている採用市場になっています。IT企業や広告代理店だけでなく、他業界もデザイナーを必要としており、採用競争が激化する一方です。
そんな状況下では給与や福利厚生といった条件面だけでなく、デザイナーが「この会社で働きたい」と思えるような本質的な魅力が重要だと私は考えています。評価制度の内容も、デザイナー自身が納得感をもって働けるかの判断基準になります。長く働き続けたいと思える会社にするためにも「明確な評価制度がない」という状態は避けるべきです。
💡デザイナー採用が難しい背景や対策を詳しく知りたい方はこちら デザイナー採用の難しさを感じている人事担当者のみなさまへ

デザイナー評価制度設計の4ステップ
具体的にデザイナーの評価制度はどのようなステップで設計していけばよいのか。ここではゼロから作る場合の一例を解説します。
- ステップ1:評価の目的と基本方針を決める
- ステップ2:評価項目の洗い出しと設定
- ステップ3:評価基準とウェイト付けの具体化
- ステップ4:評価方法とプロセスの設計
ステップ1:評価の目的と基本方針を決める
具体的な評価項目を設定する前に、まずは「何のために評価制度を導入するのか」「評価を通じて何を実現したいのか」という目的を明確にします。たとえば「本人の要望に応じたキャリアステップを提供するため」「納得感のある処遇を実現するため」「事業成果への貢献を可視化するため」など、様々な目的が考えられるかと思います。
また、すべてを数値で評価しようとせずに「何を評価し、何を評価しないのか」という基本方針を定めることも重要です。たとえば「制作物の数を評価基準にすべきか」という声を私もお聞きすることがありますが、自社の事業内容や業務内容によります。たとえば広告運用において、クリエイティブの制作や更新が大量に必要な業務内容だとします。たしかにいかに数をこなすかも重要ですが、単に提出した制作物の数量だけで評価を決めてしまうと、デザイナー自身の本質的な成長からは遠のいてしまう可能性があります。
そのような状況を避けるためにも、自社の事業やデザイナー自身の成長につながる指標を初期段階で定めておけば、制度全体の整合性が取りやすくなります。
ステップ2:評価項目の洗い出しと設定
評価の目的と方針が明確になったら、具体的な評価項目を洗い出します。項目の出し方に迷った場合は、一般的に評価制度の設計で使われる「成果評価」「能力評価」「情意評価」の3つの観点をもとに考えてみてください。
役割や業務内容に応じてそれぞれの項目は変わりますが、以下は一例です。
| 評価の種類 | 説明 | 評価項目例 |
|---|---|---|
| 成果評価 | 業務上の成果を定量・定性で評価すること。 |
|
| 能力評価 | 本人の持つ具体的なスキルや資格をもとに評価すること。専門スキルやポータブルスキルで評価することも多い。 |
|
| 情意評価 | 主に仕事に取り組む姿勢や意欲を評価すること。 |
|
ステップ3:評価基準とウェイト付けの具体化
評価項目に「S・A・B・C・D」のような段階評価を用いる場合、各段階がどのような状態を示しているのかを明確に定義しましょう。「S評価の人はこういうスキルがある」「A評価ならこういうことができる」などの基準を設け、評価と連動させることが求められます。
最終的に点数で評価を算出する場合は、評価項目の重要度に応じて、ウェイト(重み付け)を設定することもよく使われる手法です。たとえば若手デザイナーであれば能力開発や行動面を重視し、シニアデザイナーやマネージャークラスであれば成果や事業貢献のウェイトを高める、といった調整が考えられます。
ステップ4:評価方法とプロセスの設計
最後に、評価をどのように行うか具体的なプロセスを設計します。一般的には被評価者となる社員自身が期初に目標を立て、上長に承認してもらう流れが多いかと思います。
「目標を立てたけど何もアクションできず終わってしまった」「目標が高すぎた……」ということもありがちです。形骸化を防止するためには、定期的に目標の状況を確認・修正することが大切です!
たとえば期初に目標設定を行い、期中での進捗確認(中間レビュー)、そして期末に最終評価とフィードバック面談を実施するなど、ルールを設けるとよいでしょう。
評価方法は自己評価と上司評価が基本となりますが、より多角的な視点を取り入れるために、同僚や他部署のメンバーからの評価(多面評価、360度評価)を導入することも検討できます。ただし、運用コストや評価者の負担も考慮して判断しましょう。
【インタビュー動画】市場価値の高いデザイナーを育成する評価制度のポイント
評価制度の重要性は理解しつつも、クリエイターという専門職の評価に悩む企業は少なくありません。そこで、Web制作会社として業界内で高い評価を受ける株式会社ZIZO DESIGNの代表、坂口隆俊氏に、LIGの人事部長である斎藤がインタビューを実施。クリエイターが納得し、市場価値を高められる評価制度のポイントについて伺いました。
※以下はインタビューの一部を抜粋し、編集したものです。
――クリエイターの評価、特に定量化が難しいという点で悩む企業は多いです。ZIZO DESIGNさんでは、具体的にはどのような制度を運用されているのですか?
坂口さん:ZIZOでは、大きく2つの軸で評価をおこなっています。
一つは定量的な評価で、デザイナーやエンジニア、役員まで含む全社員が「粗利目標」を持っています。この目標の達成度がボーナスに直接反映される仕組みです。評価者による曖昧な評価をなくすために、ボーナスの計算式もすべてWebサイトで公開していて、誰が見ても納得できる透明性を大切にしています。
もう一つが定性的な評価です。会社のビジョンである「ワクワクすることをひとつでも多く!」を実現するために、具体的な行動を「ミッションツリー」という形で定義しています。社員はその中から自分がコミットしたい目標を選んで、半年間取り組む。これによって、個人のスキルアップや会社への貢献も評価できるようになっています。
――どのような考えをもとにこの評価制度を設計されたのでしょうか?
坂口さん:前提として、100点の評価制度をつくるのは難しいことですし、私たちも今の制度が絶対正解だとは思っていませんが何にウェイトを置くかを考えて今の制度にしています。もちろん新しいメンバーにも採用面接時に説明して、納得してもらったうえで入社してもらっています。
最初はどうしてもギャップを感じてしまうかもしれませんが、自分の価値を発揮するためにどうすればいいか、自然と考えられるようになってきます。例えば、デザイナーが窓口に立ってお客様と話をし、その内容をディレクターに振る、なんてこともあります。自分の「好き」や「得意」を活かして、自ら仕事を取ってくることもあります。好きなことに携わっているときって、パフォーマンスは絶対に高くなるじゃないですか。その人の中にナレッジが溜まっている状態なので、そこから繰り出すアイデアはお客さんにも響くんです。
僕たちは「価値がある」ということと「価値を発揮する」ということは違うことだと考えています。例えば、英語が話せるとか、デザインができるとか、おしゃべりが上手とか、それらは全部とても「価値がある」ことです。でも、それをビジネスの場でお客さんからお金をいただく、つまり「価値を対価に変える」という視点が、僕たちの評価制度の根っこにあります。
――ZIZO DESIGNさんのような評価制度を導入したいと考えたとき、経営者が気をつけるべきポイントはありますか?
坂口さん:100点の評価制度はないように、私たち自身もこの評価制度が絶対解だとは思っていません。ただ、一つ前提として大事にしていることがあります。それは、社員の対外的な評価、つまり市場価値が、社内の評価基準より上であってほしいということです。
社内の評価制度は、あくまでその会社の中だけのもの。転職したり独立したりした時にも生きる評価ではありません。デザイナーなら、自分が憧れるデザイナーから評価されるとか、アワードで賞を取るとか、そういうことのほうが絶対に嬉しいはず。その前提に立って評価制度を考えると、社内の評価と対外的な評価をうまく取り入れたほうが、動きやすいのではないかと思います。
- 💡ZIZO DESGINの評価制度のポイント
-
- 「価値」を「対価」に変えることを重視
スキルを持つこと(価値がある)と、それをビジネスの成果に繋げること(価値を発揮する)は別物。評価制度では、個人のスキルをいかにして「対価」に変えられたかを重視し、デザイナーやエンジニアも粗利目標を設定している。 - 定量と定性の2軸で評価する
粗利目標という定量的な指標で事業への貢献度をはかりつつ、会社のビジョンに紐づく「ミッション」に対する取り組みで個人の成長や意欲など定性的な評価もおこなう。 - 個人の「好き」や「得意」を価値発揮に繋げる
社員が自らの強みを活かして仕事に取り組めるよう、裁量を与える。好きなことに携わることでパフォーマンスが向上し、それが結果的に顧客への価値提供に繋がるという好循環を目指す。 - 社内評価と市場価値のバランスを意識する
会社の評価基準だけでなく、社員の対外的な評価(市場価値)を考慮。社外でも通用する評価を得られる環境が、本質的な成長につながる。
- 「価値」を「対価」に変えることを重視
【テンプレートあり】デザイナー評価シートの例
最後に、弊社のデザイナーが作成した新人デザイナー向けキャリアシート(評価シート)の例もご紹介します。どんな項目を設定しているか、参考としてぜひご覧ください。
テンプレート(エクセル)をダウンロードする
- キャリアシートの対象者
-
- 実務未経験の新人デザイナー
- 主にアイキャッチやバナーなどのビジュアルデザインを担当するWebデザイナー向け
- キャリアシートの目的
-
- 新人デザイナーが「一人立ち」までに何をすべきかがわかるようになる。
- 1on1などでの振り返りと次月の目標設定がしやすくなる。
- 正しく自分の位置を把握できるようになり、今どこを伸ばすべきなのかがわかる。
- 新人デザイナーの自己評価、先輩からの評価のずれをできるだけなくし、基準を揃える。共通認識を持てるようにする。
※このキャリアシートができるまでの経緯は以下の記事をご覧ください。 新人デザイナー育成のためのキャリアシートを作成しました【資料あり】
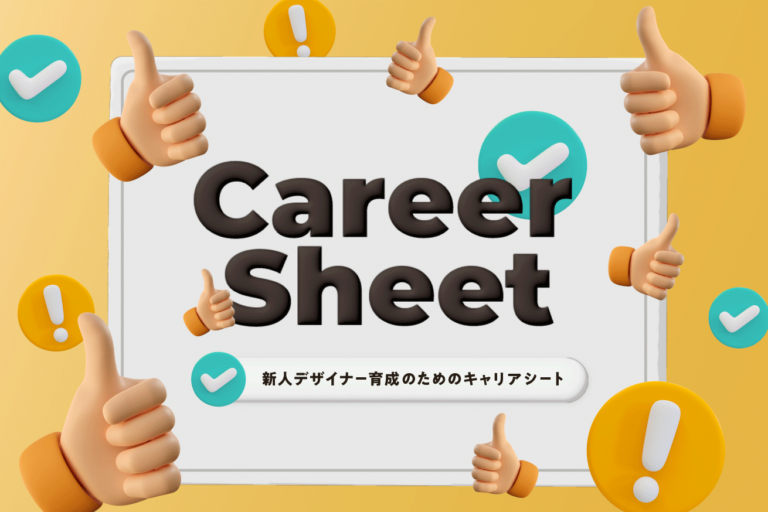
まとめ
デザイナーのキャリア設計やモチベーション向上、そして事業目標達成への貢献のためにも、評価制度は不可欠です。最初の一歩として、まずは以下のことから始めてみてはいかがでしょうか。
- 自社のデザイナーに求める役割や期待値を明確にする
- 既存の評価制度の課題について、デザイナーやマネージャーにヒアリングする。
- この記事で紹介した設計ステップを参考に、評価の目的や基本方針をチームで議論する。
今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ貴社ならではの評価制度の実現を目指してください。
私たちLIGエージェントは、制作会社のノウハウを活かした採用支援をおこなっています。求人の掲載だけでなく、課題に応じた人材紹介やクリエイターの求める福利厚生のアドバイスなど、貴社の課題解決のために伴走いたしますのでぜひご相談ください!