これは新人サラリーマン菊池の出社に密着したドキュメンタリー・テキスト・ゲームです。途中で選択肢が出てきますので、正しい選択肢を選んで菊池を出社させてあげてください。間違った選択肢を選ぶと菊池は死にます。ちなみにどれも三つ目が正しい選択肢です。
SCENE1 布団から起き上がろう
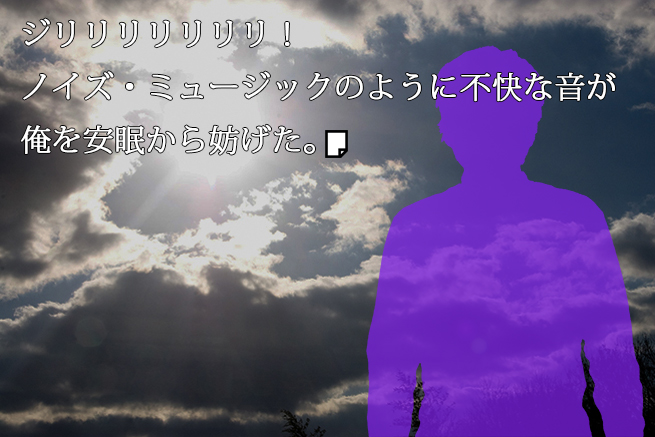
ジリリリリリリリ!
不快なノイズ・ミュージックが俺を起こした。テレビの中で福澤朗が「時刻は八時十九分」と伝える。やれやれ。朝はいつも俺をウンザリさせる。
俺の名前は菊池良。上野にあるウェブ制作会社「LIG」に務めるメディア・クリエイターだ。いわゆる会社員ってやつ。まったく、やってらんねーぜ。
俺は目覚まし時計を止めるとすぐさまベッドに戻った。寝ぼけた頭で「出勤しなきゃいけねーな」と考える。あーあ、就職しちまったばっかりに……。
だけど、無慈悲な始業時間はこっちの都合を考えちゃくれない。俺は……
選択してください。
1. シャワーを浴びる
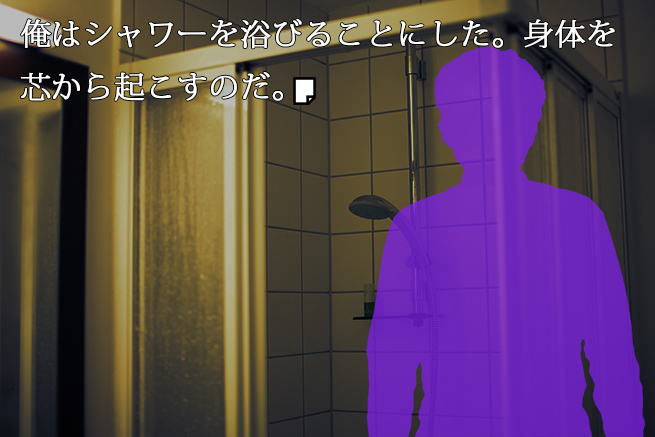
俺はシャワーを浴びることにした。身体を芯から起こすのだ。服を脱いで浴室に入ると、蛇口をひねる。その瞬間、ゴォーっというエンジン音がバスルームを充満しだす。
「何の音だ……?」
見上げると、針のついた天井が落ちてきていた。このままいくと鋭い切っ先に身体をすり潰されながら絶命してしまう。
ふと窓を見ると、忍び装束を着た男が睨んでいた。通称「針天井のテツ」だ。どうやら伊賀の里の者が裏切り者の俺を追って俺の家まで来たらしい。夜行バスに揺られてよく眠れなかったのか、目の下に隈ができている。ミスチルが好きな乙女座のB型。
急いで逃げ出そうとするが、低くなって天井が引っかかってドアが開かない。床がお湯で満ちてきた。さっきつけたシャワーだ。排水口を詰まらせているようで、どんどん溜まっていく。温度は62度に固定されていて、地味に熱い。
「上は洪水、下は大火事……か」
俺はメビウスに火を付けると、最後の一服をゆっくりと楽しむ。
「年貢の納め時だな」
火を消そうとタバコを落とすと、一面が引火した。……お湯じゃない!? それはガソリンだったのだ。俺は劫火に包まれながら、プロディジーの「ファイヤースターター」を口ずさんだ。

2.朝ご飯を食べる
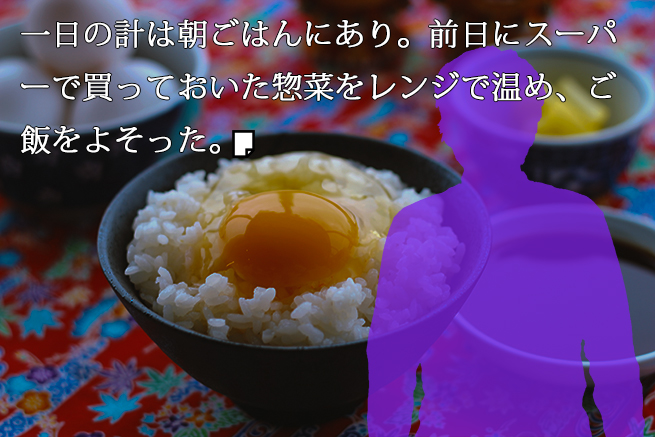
一日の計は朝ごはんにあり。前日にスーパーで買っておいた惣菜をレンジで温め、ご飯をよそった。ニュースショーに合わせられたチャンネルをザッピングしていく。
おかずを口に運びながら、ミュージシャンが麻薬所持で続々と逮捕という報道を眺めていた。まさかさだまさしがね……。
「……ん?」
ザザッザッと画面にノイズが走った。次の瞬間、古い井戸が画面に写る。
「あ、これ、『リング』で見たやつだ……」
貞子はいつもの長い髪を垂れ流しながら、頭を前にしてテレビから出てくる。足から出たくなる日はないのだろうか。薄いメンチカツを齧りながら、そんなことを考えた。
急いで逃げなくてはいけないのに、足が言うことを聞かない。なぜならコタツに入っているから。菊池家ではこたつはオールシーズン活躍している。ぬるま湯のような快感に浸りながら、迫りくる貞子を眺めていた。メンチカツを頬張って。
こっちの都合はおかまいなしに、貞子は首を締めてくる。まだメンチカツを飲み込んじゃいないのに。まったくせっかちなやつだよ。こうなるともう食べ物は喉を通らない。
俺は不意に貞子にKISSをした。彼女の顔がとても寂しそうだったから。薄れゆく意識の中で、メンチカツを口移しする。彼女が笑った気がした。

3. ゴリラに餌をやって二度寝する
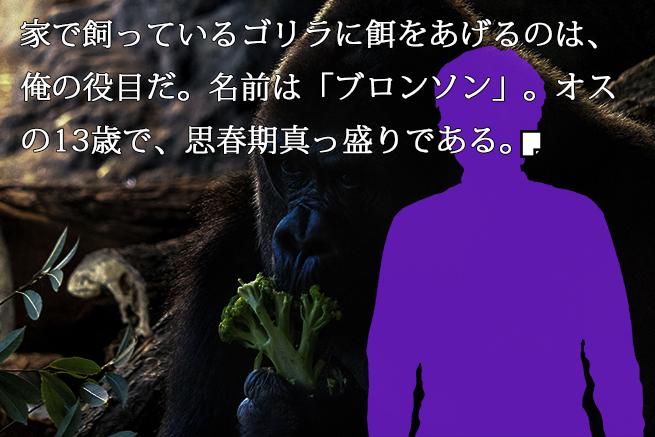
家で飼っているゴリラに餌をあげるのは、俺の役目だ。名前は「ブロンソン」。オスの13歳で、思春期真っ盛りである。誰も使わなくなった六畳の和室を活用しようと、2年前に飼い始めた。うちのマンションはペット禁止だが、まだ近隣住民にはバレていない。
ゴリラといったらバナナを与えておけばいい、と考えるのは素人だ。本物のゴリラは実にグルメで、味にうるさい。
「わさび醤油を出してもらえないか? このソースは出来損ないだ」
フランス人シェフが出した鴨のステーキにそう言ったときは、冷や汗が出た。
そんなブロンソンの最近のお気に入りは、納豆そばだ。そばに納豆をかけるだけというシンプルな作りが、彼の舌に合ったようだ。
冷蔵庫から納豆を取り出す。ゴリラの一食で20人前食べるから、かき混ぜるだけで一苦労だ。これが原因で手首を壊してしまったので、電動ドリルを使っている。ドリルの音が15分以上つづくので、近所からは苦情が殺到し、大勢の住民が武器を持って押しかけたこともある。ドリルで何とか一網打尽できたが、あのときは危なかった。
「ほら、できたよ」
「ありがとう。都会の闇は深い。笑顔を忘れてしまった子どもたちよ」
テレビのニュースばかり見せているので、こんなことを言うようになってしまった。時計の針を見ると、まだ八時五十分。九時十五分に出れば間に合うので、一休みしよう。戦士の休息だ。
SCENE2 駅まで向かおう

朝のリフレッシュをした俺は、家を出た。だが、思いのほか寝てしまったので、このままじゃ電車の時間に間に合わない。ダッシュすれば確実に間に合うが、疲れるのは嫌だ。いったい、どうしようか。俺は……
選択してください。
1. 遅延を祈ってゆっくり歩く

東京じゃ電車の遅延は日常茶飯事だ。毎日のように遅延証明書が配られている。いつかアメリカのSF作家がこんなこと言っていったっけ。
「日本人はタイムマシーンを発明した。電車の遅延証明書があれば、遅刻を帳消しにできる。これは二〇世紀で最も重要な発明だ。次点はいちご大福。とろけるようないちごと餅の華麗なハーモニー」
彼はいつもワープロ片手にいちご大福を食べていた。数々の傑作がそうやって生まれてきたのだ。最後にトーキョーへ来たときは、俺の家に泊まっていった。ゴリラを題材にした小説が書きたいからだそうだ。ゴリラの腕力は地上最強だと言われている。ならば、宇宙戦争が起きた場合、地球代表として戦うのはゴリラではないだろうか? そんな発想から『ゴリラと宇宙戦争』は書かれた。
小説を書き終えた彼は、帰国する前日、俺に「あるもの」を託した。大量のいちご大福だ。ざっと三〇キロはある。食べ飽きてしまったので、もう見たくないのだという。
今、俺はそれをむしゃむしゃ食べながら歩いている。いつも朝ごはん代わりにしているのだ。三〇キロを食べきるのは大変だ。
甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。甘い。美味い。あま……うま……。
蓄積した糖分が、俺の身体を蝕んでいた。血糖値は極限まで高まり、そうして──俺の身体は爆発音をあげ、辺りに肉片をまき散らした。鳥が群がってくる。俺は食物連鎖の一部となり、永遠に地球の上を巡り続けるのだ。

2. タクシーに乗って会社へ急ぐ
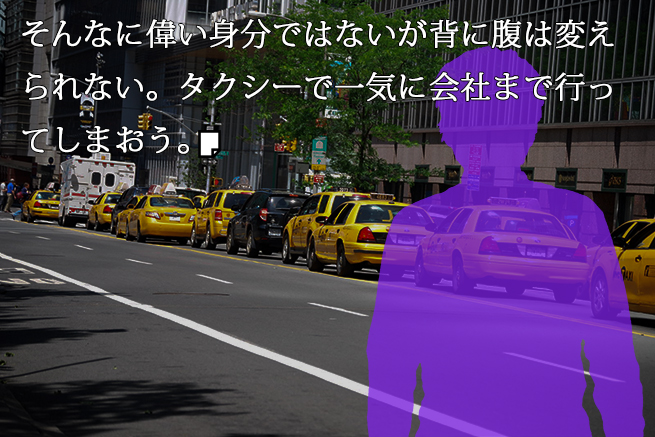
タクシーで一気に会社まで行ってしまおう。頼めば法定速度を越すサービスもやってくれるはずだ。お客様は神様なのだから。
大通りに出て、意気揚々と手を挙げる。その瞬間──振り上げた片腕が、綺麗に切断された。
「!? ……そうか、ここは車通りが激しいから、かまいたちが起こっているんだな」
早く止血しなければ絶命だ。そうなったらスケジュールが大幅に狂うので、みんなに迷惑をかけてしまう。
血をシャワーのように浴びていると、目の前にタクシーが停まった。後部座席のドアーが開く。切り取られた腕を拾ってから乗り込んだ。
「お客さん、どちらまで?」
「運転手さん、上野駅まで行ってくれ。できるだけ早く」
「それはスピード違反をしてくれ、ってことかい」
「自由に解釈してくれて構わない」
そういうと運転手は、車を急発進させた。年格好からいって40代半ばだろうか。ネームプレートには「吉松」と書かれている。あだ名は「よっしー」か、それとも「まっつん」か。座席が血で生暖かくなっていく。
「何か話してくれ。なんでもいい」
そうしなければ、すぐにでも気を失いそうだった。
「……お客さん、私ね、『運転手』って言われることに違和感があるんですよ」
「それはいったいなぜ?」
「マッサージ師とか、弁護士とか……ほとんどの職業は『師』や『士』とか、人間らしい漢字が付けられているんですよ。なのに、運転手は『手』ですよ。まぁ、確かにハンドルは手で握ってますがね。でも、足でブレーキ踏まなきゃ大事故になるし、より良いルートはないか常に頭も働かせている。楽しい雰囲気を作るためにこうやって喋ったりもする。なのに、運転『手』って言われると、なんだかハンドルさばき以外の仕事を否定された気がするんですよね」
確かに一理あるかもしれない。
「車田正美が良いこと言ってましてね」
車田正美……? 『聖闘士星矢』や『リングにかけろ』で有名な漫画家だ。
「『俺は漫画家じゃねえ。漫画屋だって』」
……それが何の関係があるのだろうか。頭が回らないから関連性に気づけないのか、それとも本当に関連がないのかわからない。
「だから、お客さんも私のことをこう呼んでくだせえ」
運転手が振り向く。
「『運転屋』ってね」
渾身のドヤ顔を作って、言い放った。
「あ、あ、あ……」
「ん? どうしたんで?」
「前を見てくれ!」
目の前の交差点で、トラックが横断しようとしていた。俺たちのタクシーは、そこへ時速130キロのスピードで突っ込んでいった。

3. CIA調査官からの着信に出る

プルルルルルルル……。
iPhoneの呼び出し音が鳴る。画面を見ると、CIA調査官のチャーリー・マクマホンからだ。
「やぁ、ミスター・キクチ。久しぶりだな」
「ああ、『戦慄の土曜日事件』以来だな。時間がないんだ、用件を早く言え」
「そう急かすな。きみの爆弾処理士としての腕を見込んで頼みがある」
すぐにピンときた。全米を騒がしている「サランドラ・ボマー」のことだ。
「ご名答。実はサランドラから東京を一週間で廃墟にするという声明が届いた。まずは足立区を吹っ飛ばすそうだ」
そこで元爆弾処理士の俺に白羽の矢が立ったらしい。確かに爆弾処理準一級の資格を持っている。
「できるか?」
「もちろん」
俺は即答すると、すぐにクローゼットからかつての仕事道具を取り出した。対戦車用のパワード・スーツだ。これを身にまとえばミサイルを直接浴びても耐えることができる。
俺はGoogleマップで足立区全域を表示する。昔から怪しいと思っていた場所があった。
足立区のコンビニを線で結ぶと、綺麗な五芒星になるのだ。爆弾を仕掛けるとしたら、ここしかない。俺はすぐさま現場に向かった。
・
・
・
・
・
案の定、爆弾はそこに設置されていた。四角い箱に「危険」と書かれている。すぐさま開けると、複雑な配線でごった返していた。
「赤と青……いったいどっちだ!?」
俺は意を決して赤の線を切った。すると、爆弾は爆発し、その周囲30キロは壊滅状態となった。俺はパワード・スーツのおかげで何ともない。
「任務完了だな」
しかし、もう遅刻は確定だ。社会人失格である。
「安心しろ。キミのために特別車両を用意した」
チャーリーが言う。
「なんだって?」
「新幹線のぞみだ。時速400キロで走るから数分でつく」
俺はのぞみに乗って西日暮里まで行くと、山手線に乗り換えた。
SCENE3 電車に乗って会社に行こう

山手線に乗り換えて、上野駅を目指す。それほどは混んではいない。椅子に座ってスマートフォンを操作していると、すぐについた。駅員の案内とともに、電車のドアーが開け放たれた。周囲の乗客が降りていく。
そこで、俺は……
選択してください。
1. このまま電車に乗って山の手線を一周しよう

山手線は居眠りするのに持って来いだ。どこまでいっても最初の地点に戻ってくることができる。
「輪廻転生、か……」
俺は山手線に乗り続けることにした。窓から射してくる陽光が暖かくて、眠気を誘ってくる。抗うことなく、目を閉じた。合気道の精神だ。
夢を見た。俺はまだ小学生で、アルプスの草原を楽しそうに走り回っている。それを現在の俺が眺めているのだ。この頃は、何にも考えずに遊ぶことができたな。俺の視線に気づいた少年時代の俺が、無邪気に近づいてくる。
「お兄ちゃん、誰?」
「観光客さ。きみはここに住んでいるの?」
「うん! 一緒に遊ぼうよ!!」
そういえば、こんなことがあったような気がする。あのときの青年は、俺だったのか──。
いつまでも寝ていることに気がついた駅員が近づいてくる。身体を揺すられると、俺はそのまま力なくゴロンと床に転がった。驚いた駅員が揺さぶるが、何も反応がない。
「し、死んでる……」
夏はもうすぐだ。

2. 上野駅に降りて会社に向かおう
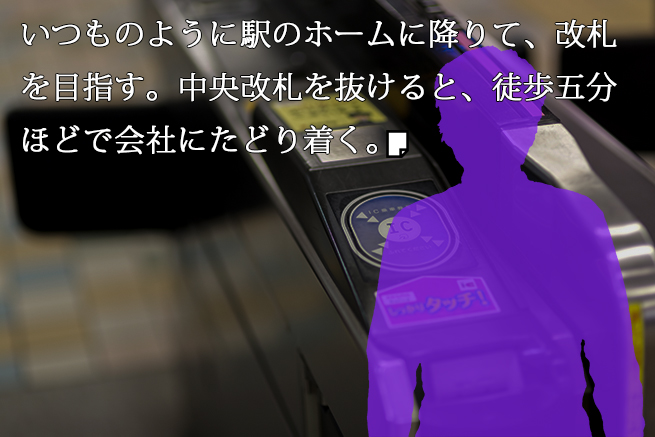
いつものように駅のホームに降りて、改札を目指す。
ジーンズのポケットからスイカを取り出し、自動改札機に押し当てた。その瞬間、耳をつんざくような警報音が鳴り響く。改札機が冷たく言った。
「チャージしてください」
ちっ。どうやら運賃が足りないようだ。精算機を見つけて近づくと、異常事態に気がつく。
財布が──存在しない。
一瞬で理解した。部屋に忘れたのだ。財布がないから、チャージができない。だが、チャージができないので、戻っても改札を出られない。
「終わった……」
その場で崩れ落ちた。もう二度と改札を出ることはできない。何もかも諦めようとしたその時だった。視界の隅でキラリと光るものが見えたのだ。手を伸ばしてみると、一円玉だった。そうだ、こうやって小銭を集めていけば、チャージができるのでは……?
「泣いている場合じゃねえか」
俺は立ち上がり、駅の中を歩き回った。希望の光を求めて。
そうして、20年以上の月日が経った。俺はまだJRから抜け出せていない。だが、いつかきっと脱出してみせる。もう一度、あの太陽と空を見上げるために。俺は小銭を集め続ける。いつかチャージ分が貯まるのを夢見て。
俺は諦めない。

3. やっぱりUターンして家に帰ろう
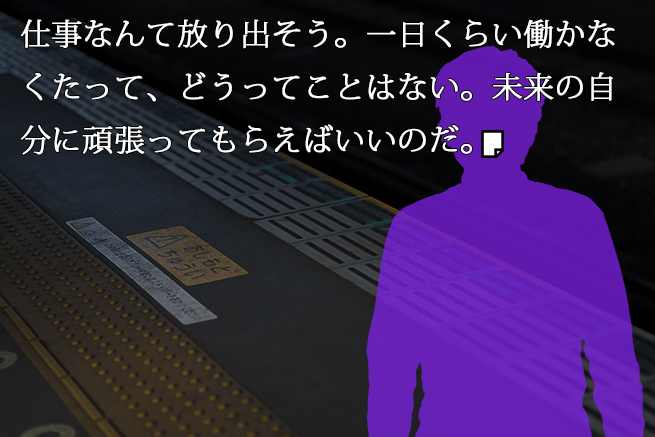
駅のホームは騒然としていた。男の怒号が聞こえてくる。
「俺らのお茶が飲めねえっていうのか!?」
見ると水筒を持った青年が腰まで伸びた黒髪の女に食ってかかっていた。その後ろには同じ色のバンダナを付けた男が何人もいる。カラーギャングがナンパを無視されたようだ。
「やめろ、嫌がっているじゃないか。ガキが粋がってんじゃねえよ」
「ああ!? 誰だ、おめえは?」
「通りすがりの名も無き男さ」
「電車男を気取ってんじゃねえぞ!」
男が懐からバタフライナイフが取り出して、突進してくる。素早く避けると右拳を打ち込む。「ゴブっ!」という音とともに地面に沈んだ。
「さぁさぁ、次にダンスをするのは誰だい? シュッシュッ!(シャドーボクシングの音)」
「や、やべえ、『バタフライドラゴンのナオヤ』が殺られたぞ! 逃げろ!」
カラーギャングは蜘蛛の子を散らすように去っていった。見かけ倒しな奴らだ。さて、本番はここからだ。
「お嬢さん、怪我はないですか? お礼はいいので、ラインの交換をしましょう」
と、ハンカチを差し出す。そのとき、俺は初めて彼女の顔を見た。

ゴリラだった。腰までの髪に見えていたのは、全身の毛だったのだ。俺としたことが、ゴリラの匂いを嗅ぎ分けられないとは。
「ウッホホ!」
ゴリラの右ストレートが綺麗に入った。

・
・
・
・
・
おかしい。これじゃいつまでたっても出社できないじゃないか。

 「それに何で俺は半透明の紫色をしているんだ?」
「それに何で俺は半透明の紫色をしているんだ?」
 「どうやら気づいてしまったようだね」
「どうやら気づいてしまったようだね」
 「!?」
「!?」

 「誰だ、お前は!?」
「誰だ、お前は!?」
 「私の名は創造主」
「私の名は創造主」
 「プログラマー?」
「プログラマー?」

 「そう、この世の摂理を作るもの」
「そう、この世の摂理を作るもの」
 「ここはいったいどこなんだ?」
「ここはいったいどこなんだ?」

 「精巧に作られた仮想現実空間さ」
「精巧に作られた仮想現実空間さ」
 「仮想、だって? 偽物ってことかい?」
「仮想、だって? 偽物ってことかい?」

 「違う」
「違う」
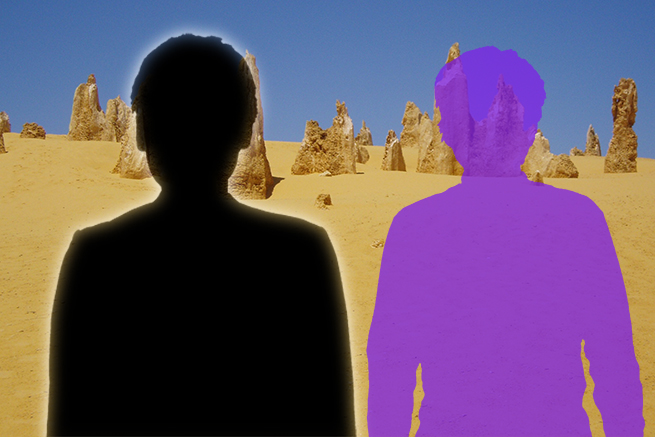
 「この世に本物なんて存在しない。すべては借り物なんだ」
「この世に本物なんて存在しない。すべては借り物なんだ」
 「そんな……」
「そんな……」

 「この構造に気がついたのはきみが初めてだよ」
「この構造に気がついたのはきみが初めてだよ」
 「嘘だ!」
「嘘だ!」

 「さぁ、おとなしくもう一度寝るんだ」
「さぁ、おとなしくもう一度寝るんだ」
 「やめろ……嘘だと言えよ……!」
「やめろ……嘘だと言えよ……!」
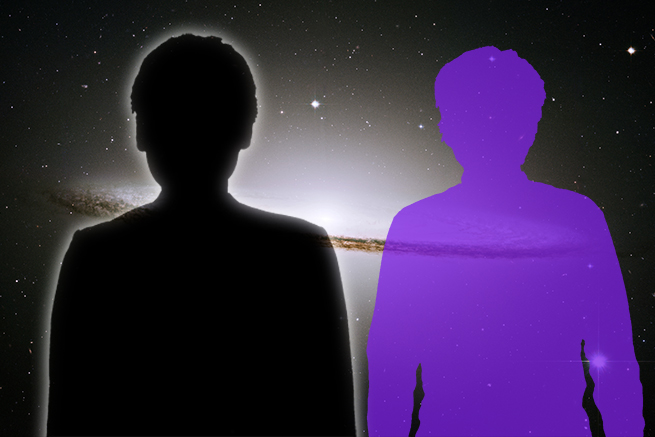
 「これは悪夢なんだよ」
「これは悪夢なんだよ」
 「う、うわあああああああああ!」
「う、うわあああああああああ!」

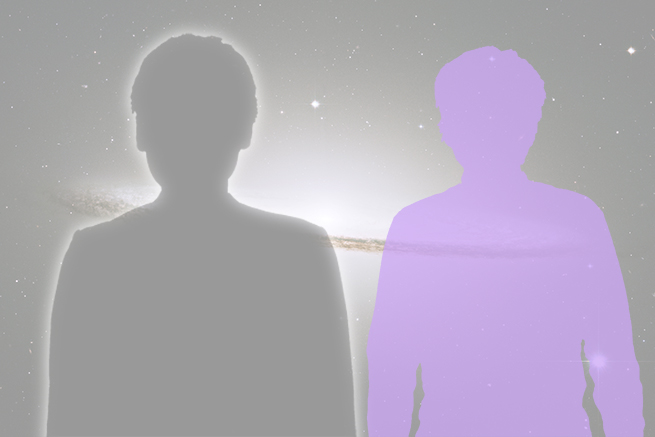

・
・
・
・
・
ジリリリリリリリ!
不快なノイズ・ミュージックが俺を起こした。テレビの中で福澤朗が「時刻は八時十九分」と伝える。やれやれ。朝はいつも俺をウンザリさせる。
俺の名前は菊池良。上野にあるウェブ制作会社「LIG」に務めるメディア・クリエイターだ。いわゆる会社員ってやつ。まったく、やってらんねーぜ。
俺は目覚まし時計を止めるとすぐさまベッドに戻った。寝ぼけた頭で「出勤しなきゃいけねーな」と考える。あーあ、就職しちまったばっかりに……。
だけど、無慈悲な始業時間はこっちの都合を考えちゃくれない。俺は……












