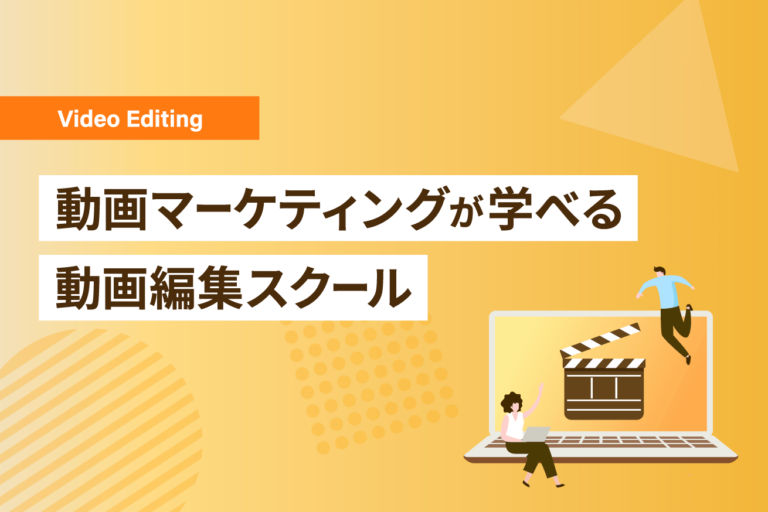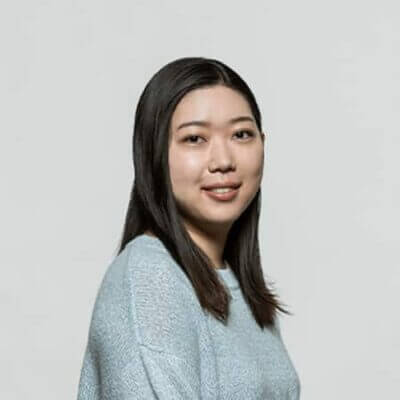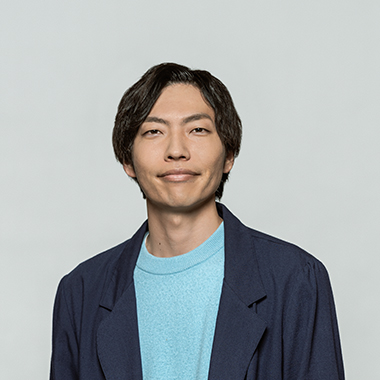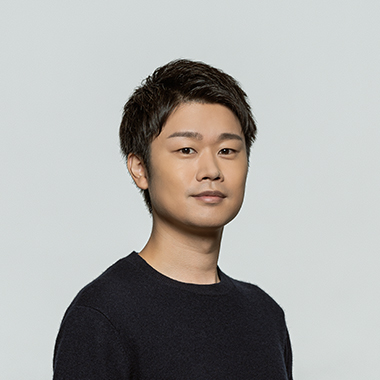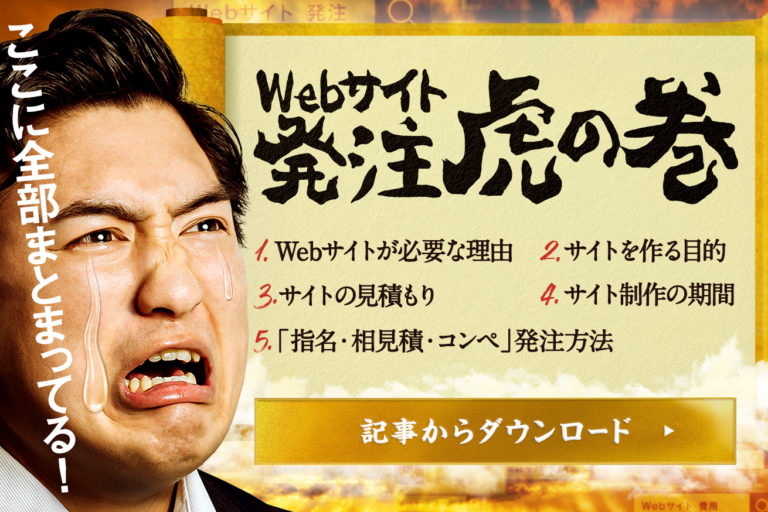こんにちは、LIGブログ編集部です。
プロモーションという言葉を聞いたことはあるけど、意味を正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。今回はプロモーションの意味やPRとの違い、手法などをご紹介します。
プロモーションの意味があやふやな人や初めてプロモーション担当になった人はぜひ参考にしてください。
目次
プロモーションとは
- プロモーションとは
- マーケティング戦略の一部として行われる販売促進のためのあらゆる活動
プロモーションという言葉についてはさまざまな定義がありますが、マーケティング戦略の一部として行われる販売促進のための宣伝活動、あるいは広報活動という意味で用いられることが多いです。
また、プロモーションをおこなう主な目的としては以下の3つなどがあります。
- 新規顧客の獲得
- 商品やサービスの認知拡大
- 既存客に対する販売の動機付け
そのため、プロモーションとは広く解釈すれば、販売促進のためのあらゆる活動となります。
プロモーションとPRの違い
- プロモーションとPRの違い
- プロモーションの一部としてPRという手法がある
先ほどマーケティング戦略の一部としてプロモーションが行われると解説しました。PRをプロモーションの略と思っている人が多いかもしれませんが、実はPRはPublic Relations(パブリックリレーションズ)の略で、プロモーションの一部です。つまり、マーケティングの一部としてプロモーションが行われ、プロモーションの一部としてPRがあります。
少しわかりやすく解説すると、マーケティング目標を達成するためのひとつの方法としてプロモーションミックスというのがあります。これは「広告宣伝活動」「広報(PR)活動」「販売促進活動(セールスプロモーション)」「人的販売」を効果的に組みわせることです。ここの「広報(PR)活動」がよく耳にするPRです。
ちなみに先ほどプロモーションのことを「広く解釈すれば、販売促進のためのあらゆる活動」と説明しましたが、狭義だと「販売促進活動(セールスプロモーション)」にあたります。
もし、プロモーションについて人と話す場合は、相手が話しているプロモーションはどちらの意味で使用してるのかを確認しないと話がずれていく可能性があります。
プロモーションの手法
プロモーションの手法は先ほど紹介したものに1つ加えた、以下の5つがあります。詳しく解説していきます。
- プロモーションの手法
-
- 広告宣伝活動
- 広報(PR)活動
- 販売促進活動(セールスプロモーション)
- 人的販売
- SNSや口コミ
広告宣伝活動
プロモーションのなかで代表的なのが広告です。テレビや雑誌などのオフライン広告、Web上のバナー広告やディスプレイ広告、SNS広告などが挙げられます。特にWeb上の広告では細かいターゲティングができるため、費用はかかりますが狙ったターゲットに広告を届けることができます。
広報(PR)活動
PRは雑誌や新聞、テレビ、Webの記事などを作成している会社にアプローチしていくことを指します。情報発信という意味では広告と似ていますが、第三者の視点が入ること、実際に情報を発信できるかどうかはわからないこと、細かいターゲティングができないことが相違点です。広告に比べると費用がかかりにくいことも特徴です。
販売促進活動(セールスプロモーション)
広告やPRは認知が主な目的でしたが、販売促進活動は読んで字の如く、商品やサービスを販売することを主な目的とした活動です。具体的には、店頭のPOPやポスター、イベント、サンプリング、キャンペーンなどがあります。
広告やPRと比べて、より直接的に顧客に働きかけることで購買意欲をさらに刺激することができます。
人的販売
営業業務や展示会での接客、実演販売など消費者に直接アプローチすることを人的販売といいます。営業担当者が直接、顧客に商品の魅力を伝えることができるので、濃いアプローチをすることができます。
しかし、顧客がその商品に興味がないのに、営業担当者がずっと話していると、押し付けられているように感じてしまうので、注意が必要です。
SNS・口コミ
SNSが普及した現代ではSNSで顧客とコミュニケーションを取ることは欠かせません。インフルエンサーの活用やSNS広告などが代表です。顧客と距離が近いSNSは親近感を持ってもらいやすいため、企業ブランディングに向いているといえるでしょう。
プロモーションの効果測定方法
- プロモーションの効果測定方法
- KPIを設定しておく
プロモーションには“成功だったのか失敗だったのか判断がしづらい”という面があります。商品が売れなかったこととプロモーションが失敗していたこととが、イコールにならない場合があるためです。
そのため、売り上げやコンバージョンといった達成目標とは別に、KPIという目標達成の度合いを測るための補助数値(重要業績評価指数)を設定しておく必要があります。
LIGでおこなうWebプロモーションの場合は、担当したページやサイトのPV数やSNSでのシェア数などを設定する場合が多いです。
これらがないと、その商品が売れなかった(または、売れた)結果に対し、プロモーションがどう貢献したかを測定することができません。次回以降のプロモーションに活用するためにも必ず設定をしましょう。
プロモーションの成功事例
後に成功事例として、「髭剃り」で有名なジレット社がインドでおこなったプロモーションの事例を紹介したいと思います。
市場調査
ジレット社がアメリカでヒットした髭剃りをインドで販売したところ、当初は全く売れませんでした。
そこでマーケティング担当者が「なぜインドでは売れないのか?」について調査をしたところ、「インド人は価格に敏感で、替刃が安価でないと売れない」「多くの男性がヒゲを生やした方がカッコイイと思っている」などの消費者の生活事情がわかりました。
商品開発
そこでジレット社はアメリカでの成功モデルを一旦捨て「インドの消費者が髭剃りに対して真に望んでいるものは何か」というニーズを満たす商品の開発に乗り出したのです。
市場調査の結果、ジレット社は伝統的に開発してきた「高級で性能の高い髭剃り」ではなく、部品を減らし、コストを抑えることで替刃が安価に購入できる「マッハ3」という商品の開発・販売に踏み切りました。
プロモーション
販売開始時には、インド人の「議論好き」という国民性を活かし「ヒゲは剃るべきか、剃らざるべきか」という論争が各地で起こるようにメディアを利用したプロモーションを仕掛け、髭剃りへの興味・関心を煽りました。
ムンバイの映画界で活躍する女優を起用するなどのプロモーションもあたり、「マッハ3」は爆発的な大ヒット商品となりました。
その後、インドでジレット社の名前が浸透した2010年には「マッハ3」よりさらにコストを抑え、プラスチック製カバーと一枚刃で作られた“激安価格で、それなりの商品”である「ジレット ガード」を販売し、またもや大ヒットとなります。
結果として、現在のインドにおけるジレット商品の市場シェアは50%を超えると言われています。
このエピソードについては、こちらの本で紹介されていた事例を参考にさせていただきました。プロモーションについてもっと詳しく知りたい、という方はぜひお読みください。
広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は初めてプロモーションなどを担当することになった人に向けての内容のため、基本的な項目のみを簡単に紹介させていただきました。
とはいえ、プロモーションは商品やサービスがあってこそです。まずは自社商品の強み、メリットなどをしっかりと理解したうえで、今回の記事で紹介したようなポイントをおさえつつ、今後の業務に活かしていただければと思います。