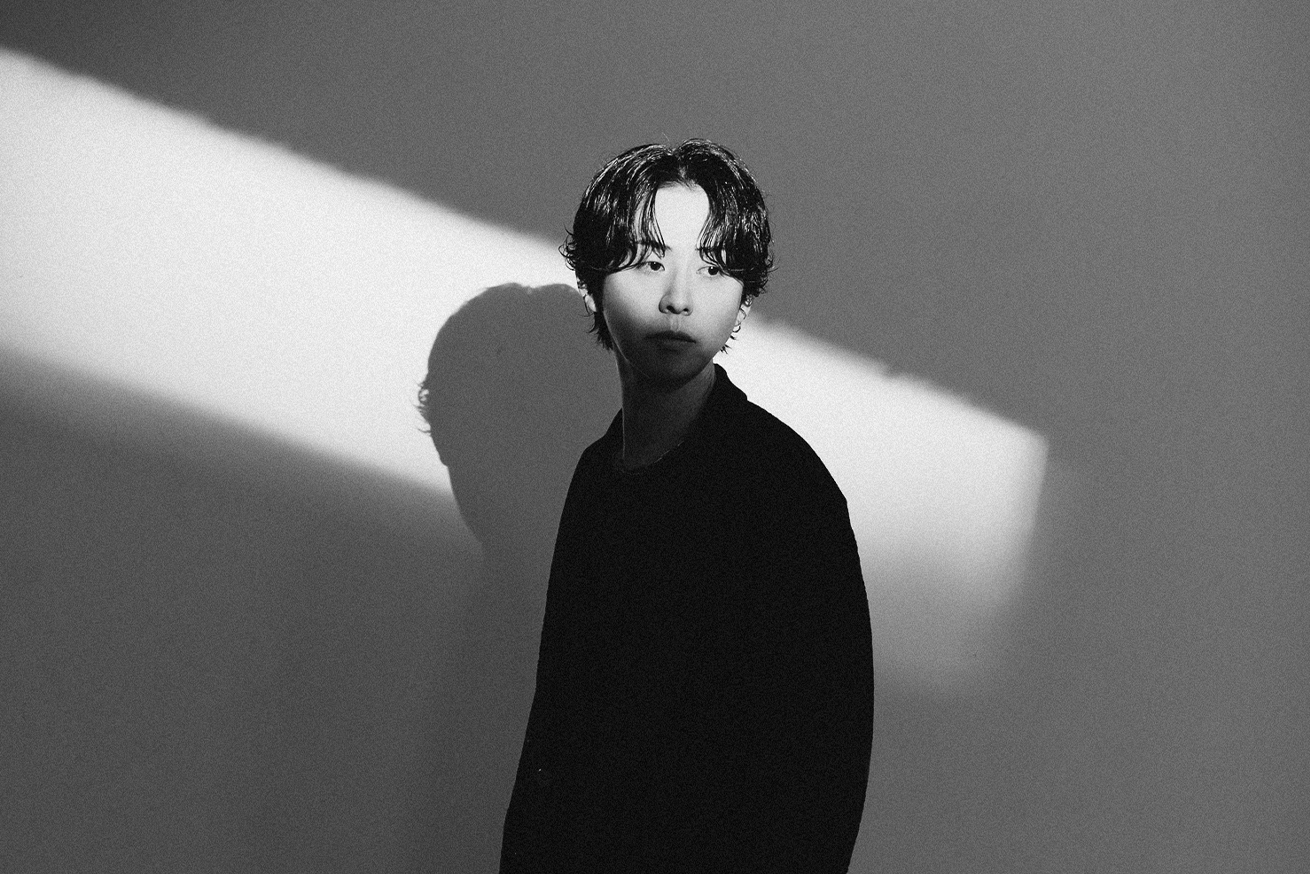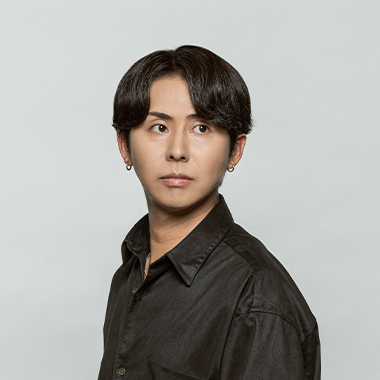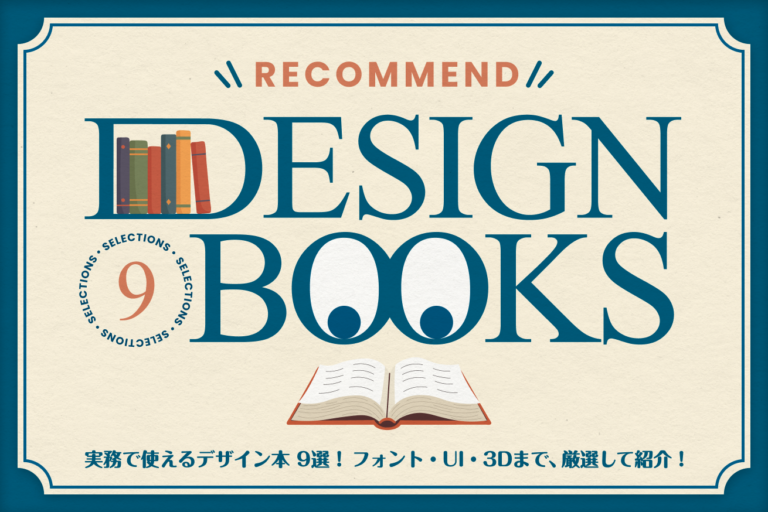LIG Creative部 マネージャーのユースケです。
最近、「デザインの単価が下がっている」という話をよく耳にします。僕からすれば、これは「誰でもデザインできる時代」の光と影が表れた結果だと思っています。ノーコードツールの普及や、スマホでの動画編集など、たしかにデザインのハードルは下がっています。でも、本当にそれでいいのでしょうか?
ツールが便利になったことで、「クオリティの高いものじゃなくていい」「とりあえず形になればいい」と考える人が増え、そのニーズに応えるかたちで、経験の浅いデザイナーが「なんとなく」価格を安く設定してしまう。これが業界全体の価格の基準を崩す原因になっているのではないかと思うのです。
「ちゃんと価値を届けられるデザイナー」になるために、これからデザイナーとして独立される方、これからデザイナーを目指すみなさんに、マネージャーとして現場で感じていることをお話ししたいと思います。
|
|
株式会社LIG Creative部 Designer/Manager 半田 佑允1987年生まれ。大学ではプロダクトデザインを専攻。その後、グラフィックデザイナーとしての活動を約5年間経たのち、デジタル媒体のクリエイティブに移行。現在はUI/UXのデザイナーとしてWebデザインを主軸に活動中。受賞歴:Awwwards特別賞(HM)/CSS WINNER STAR/CSS Design Awards SPECIAL KUDOS OCT |
|---|
目次
なぜ「なんとなく」の価格設定になってしまうのか?
原因1:実績がないから、価格を下げてしまう
よく見かけるのが、「実績作りのために安く引き受けます」というアプローチ。気持ちはわかります。でも、これがデザイナーである自分自身の価値を下げることになっているんです。
たとえば、Webサイト制作の場合。フリーランスでも本来なら50万円くらいの価値がある仕事を、「実績作り」という名目で数万円で請けてしまうことがあります。
ディレクター、デザイナー、エンジニア、3人分の仕事を1人でやるわけですから、場合によっては100万円相当の仕事になることだってある。なのに「1人だから」と20万円で請けてしまう。これは「割引」ではなく、もう「破綻」した金額なんです。
こうした価格が積み重なることで、「このくらいでやってくれる人が他にもいたよ」と言われる土壌ができてしまい、次の世代のデザイナーにも影響が出る。結果として、業界全体の価値が薄まっていくように感じています。
原因2:「見た目」だけがデザインだと思っている
デザインというと、つい「見た目=ヴィジュアルデザイン」に注目しがちですが、実際には、そこにたどり着くまでにたくさんのプロセスがあります。
- クライアントへのヒアリング
- 情報の整理と設計
- 提案とすり合わせ
- 進行や納品までの調整
これらもすべて、デザインの一部です。にもかかわらず、「見た目だけ」を基準に価格を考えてしまうと、大部分の作業が見積もりに含まれない状態になってしまいます。
とくにフリーランスの場合、「ヴィジュアルデザインだけできればいい」という発想ではやっていけません。営業もディレクションも制作も、すべて自分で担うことになるからです。
こうした視点が抜けてしまうと、価格設定に必要な感覚も育ちません。
原因3:気持ちが先に立って、友達価格にしてしまう
知り合いの紹介だったり、応援したいプロジェクトだったり、気持ちが先に立って、「値段なんてどうでもいい」と思ってしまうこともあります。
でも、それが続くとどうなるか。
- 修正の線引きが曖昧になる
- お金が発生しないぶん、相手も真剣度が下がる
- 関係性に「遠慮」が混じってしまう
つまり、「信頼関係」が築きづらくなるんです。
そしてなにより、クライアント自身の発注者としてのリテラシーが育たなくなる。たとえば、「デザインってこのくらいでやってくれるもんでしょ?」という感覚がそのまま次の発注先にも持ち込まれたら、あなたのやさしさが、誰かの負担になってしまうかもしれない。
「なんとなく」を脱却するための3つのヒント
ヒント1:安く請けるのではなく、時間をかけて届ける
「未経験だから安く」ではなく、「未経験だからこそ丁寧に」届ける。その姿勢は、確実に伝わります。時間がかかるのは悪いことじゃない。でもそのぶん、リサーチや構成、提案の密度で補えばいいんです。
「未経験だから」と値段を下げるのではなく、時間をかけてでも品質で応えるという覚悟のほうが、よっぽど信頼されます。
世の中の安価で成り立っているサービスや商品には、優れたビジネスモデルや仕組みがあります。たとえば、テンプレート化や自動化、工数の最小化などによって、品質を保ちながらコストを抑える工夫がされているのです。
その努力をせずに、個人の都合で「安い=雑でもOK」というロジックに置き換えるのは、プロとして無責任です。
ヒント2:制作を俯瞰し、工数を正確に把握する
価格設定の精度を上げるには、「制作全体を俯瞰して見られる視点」が欠かせません。
どこまでを自分で担い、どこからを外注すべきかを判断する力は、自分の作業量を正しく把握するためにも必要です。「ぜんぶ自分でやりたい」という気持ちは自然ですが、デザインはあくまでクライアントのためのもの。その視点を欠くと、いつの間にか「自分のための制作」になってしまいます。
この視点を育てるには、まずはやるべき工程のイメージを持つこと。そのためには、実務に近い環境で学び、先輩やチームに揉まれる経験が非常に大切です。
僕の実感でいえば、「この工数にはこれくらいの負荷がかかる」という感覚は、現場でしか身につきません。制作会社などで、プロセスやクライアントの温度感に晒される期間が、地力を育ててくれると思います。
では、自分の仕事量をどう可視化するか? 以下のステップで整理してみましょう。
- まずは全体の流れを分解する(ヒアリング、設計、デザイン、やりとりなど)
- 実際に取り組んだ案件や課題で、それぞれにかかった時間を記録する
- 目安となる時給(最低賃金、自分なりの設定値)をかけて「基本コスト」を算出する
- そこに「スキルの価値」や「信頼性」といった付加価値をどうのせるかを検討する
こうした手順を経ることで、「なんとなく」ではない、自信をもった価格設定ができるようになります。
価格は「相場」ではなく、「納得感」で決めるもの。根拠のある価格設定が、自分の価値を守る第一歩です。
ヒント3:関係性がある相手ほど、線を引く
親しい相手に相談されたら、きっと親身になって考えると思いますよね。クライアントに対しても、そういう誠実な気持ちで向き合うことは大切です。
でも、仕事として引き受ける以上、「友達だから0円でいいや」という判断は避けるべきです。自分の時間とスキルには価値があるし、相手の期待に応えることが責任であり、信頼関係の基盤にもなります。
そして、付き合いが続く中でクライアントも成長し、求めるクオリティや規模が変化していくことがあります。そんなときには、無理に自分が抱え続けるのではなく、適切なタイミングで「紹介する」「他に合う人へつなぐ」といった手放す選択をすることも、プロとしての誠実さです。
大切なのは、線引きをすること。たとえば「今回はこういう条件で」「次からはこの金額で」といった合意を交わすことで、信頼ある関係を築きつづけることができます。
自分の価値は、自分で守っていくしかない
価格を決めるのは、自分自身です。でもそれは、「好きなように決めていい」という話ではなく、ちゃんと責任を持つということ。
「この価格で請ける」という判断は、「この価格分の価値を届ける」という約束でもあります。
「なんとなく」の価格設定から抜け出し、自分の仕事に納得できる対価をつけていく。それが、フリーランスとして、長く信頼されるために必要なことだと思います。