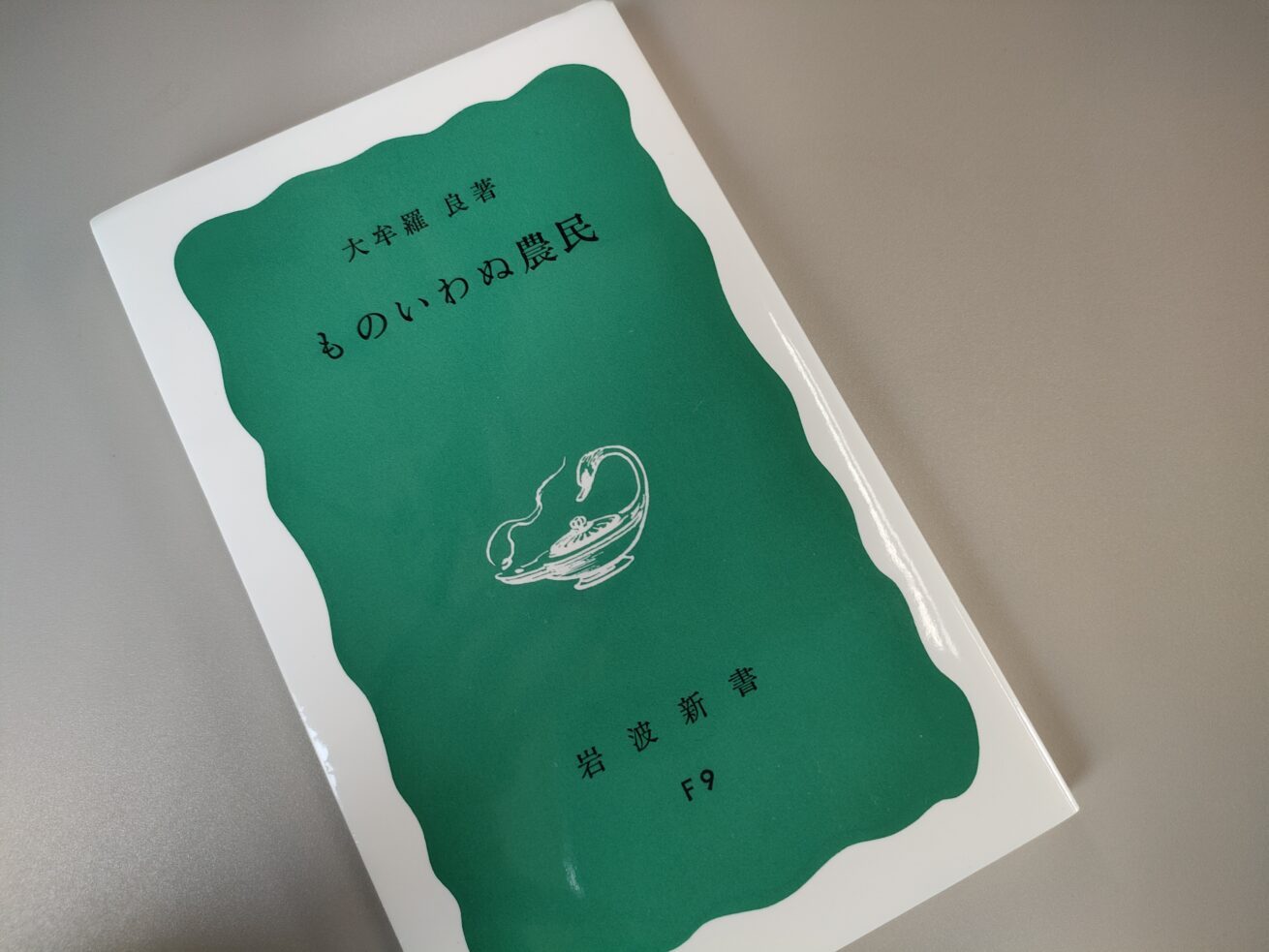こんにちは、エディター(編集者)ののぞみーるです。
突然ですが、みなさんの今の職業を選んだ理由はなんですか?
わたしがなぜ編集者になったのかその理由を問われたら、正直なところ「なりゆき」と答えると思います……。就職活動中にはまだ明確にやりたいことがなく、いくつか面接を受けていた中でたまたまエンタメ雑誌を出していた出版社に受かったので、そこで働いてみるか、くらいの気持ちでした。
「なりゆき」でこれまで編集者を続けてこれたのですから、こちらの道を選んで正解だったと思いたいものです。弁護士事務所の秘書なども受けていたので、今思うとドジなわたしが秘書なんて適性なさすぎて、一体どんな人生になっていたことか……。
最近、実はわたしの祖父も戦後に編集者として7年間働いていたことを知りました。
なぜ今まで知らなかったのかというと、祖父は本を数冊出版していたため、「作家」だと思い込んでいたのです。しかも岩波文庫という子どもには少しハードルの高い出版物だったため、今まで読む機会がなく……。ですが、少し前に読売新聞の誌面に祖父が紹介される機会があり、そこには祖父が県国民健康保険団体連合会の機関誌「岩手の保険」の編集者として活動していたということが綴られていました。
そして、わたしは改めて祖父の編集者としての姿を追うために、祖父が書いた本を読んでみることにしたのです。
『ものいわぬ農民』を読んで
祖父が「大牟羅良」名義で書いた『ものいわぬ農民』には、戦争から帰ってきた祖父が編集者となり、岩手の農民たちの声をリアルに伝えたいと試行錯誤した姿がありました。
- この本の内容
- 「日本のチベット」といわれた岩手県――その山村で,貧困と因襲を背負いながら黙々と働く農民たちは,いろり端で,行商してあるく著者に対して,自分のことばで,その生活の喜びや悲しみを語った.嫁姑の確執,二・三男問題,土地への愛着,子供や老人の姿等々.日本社会の最も深い鉱脈をなす農民たちの語る言葉に耳を傾けよう.
たった一人ではじめた雑誌編集・編集者1年目
昭和26年2月、祖父は『岩手の保険』にまったくはじめての仕事として携ることになりました。また、編集長兼たった一人の編集部でした。祖父はまず県内の書いてくれそうな人や県にゆかりのある人に原稿依頼の手紙をせっせと書き、雑誌としてまとめていったそうです。
企画した記事に詳しいライターさんに執筆依頼する編集者あるあるです。
原稿を書き慣れている人が書いた原稿は「よくまとまった原稿」でしたが、祖父は違和感を覚えたそうです。
しかし、行商生活で農村を歩き回った私には、農民に訴える雑誌として、如何にもそらぞらしいものに思えてなりませんでした。もっと農民に身近かなもの、それは何か、私はいろいろと考えてみました。すると、何か思い当るものがありました。それは私が行商の旅できいたいろり端の話、その話の中にこそ、農民のくらしや、そのものの考え方が、そのまま顔を出していたのではなかったか、それをこそとり上げるべきだと思ったのです。
引用:『ものいわぬ農民』P128
この部分を読んだとき、Webコンテンツの企画を考えるときに「ターゲット」を必ず設定するので、同じだ! と声を上げずにはいられませんでした。そして、祖父はさらにこの「農民に訴える雑誌」としての役割を突き詰めていきます。
雑誌に対する感想や批判から考える・編集者3年目
祖父は農民のくらしの声を雑誌の流し込むため、農村に出かける機会があるたび農家を訪ねて歩き、よもやまの雑談をしていったそうです。それを取材っていうんだよおじいちゃん! 取材することで、農民のリアルな声を自ら拾い上げ、雑誌に載せていきました。
その頃になって雑誌に対する批判が多くなっていきました。
(中略)
「暗すぎて雑誌を手にとるのも嫌だ」「保険雑誌から逸脱して、出来の悪い綜合雑誌化している」「編集者が思想的に危険性がある」等々、これらには善意よりも悪意にみちたものの方が多かったようです。
(中略)
するとあちこちから力付の手紙がとどくのでした。中にはノートの端切れに”編集者よがんばれ!”と書いた村の青年たちの激励もありました。
(中略)
こんな手紙を手にする時、四十も半ばに達した私が、全く乙女のような感激と共に、このような人々と共に農村の問題を考え合い、その人々のくらしの声を活字していける幸福をしみじみ感ずるのでした。
引用:『ものいわぬ農民』P132-133
記事や文章に対して賛否両論の意見が見れるってSNSじゃん!! 昭和20年代の話ですが、当時も令和の時代もコンテンツへの反応って変わらないんだなあ……。そして、自分が編集したコンテンツに対して感想がもらえると編集者はうれしい! っていうのも変わりません。
雑誌の売り上げとは違い、一つひとつに対して制作費が発生するWebコンテンツはPV数や問い合わせ数が重要になりますが、単純に自分が作ったものに対しての反響が大きいとうれしいものです。
「共感」が多くの協力者をつなげた・編集者7年目
農民たちのリアルの声を引き出すために座談会を企画しては来客用の言葉を引き出せずに失敗したり(座談会はわたしもよく企画します)、批判を受けたりしながらも4年目にもなると、雑誌は「農民のいろり端」のようになっていったそうです。地道に「農民に訴える雑誌」としての認知を広げ、依頼をしなくても村人たちから原稿が送られてくるような状態に。
そうして、祖父は7年間の間に、戦後の動きを交えながら、編集者として農民の生活を書いてきました。
くらしの声に耳を傾けているということは、実はその声の背後のくらしをみつめていることでもある。この現実の凝視、それは国の政治をみつめる目ときっとつながらずにはいられまい。政治は政治家によって動かされるのではなく、大衆の力がその基礎になって政治家を通じて行われるべきものではないのか、私はここまで考えつくと、やっぱり“くらしの声”をこつこつ集め、そして活字にしていけばいいのだと思うのです。
(中略)
その間素人編集者の私に、まったく予想もしない多くの人々が協力して下さったのです。その中にはもちろんいろいろな人がいます。農民もいればそれ以外の職業の人もいます。しかしいずれも農村をよくするために、農村のくらしをあたたかい目で見守り続けている人です。
引用:『ものいわぬ農民』P175
だとすれば働く農民と都市の労働者を結びつけることが何にも増して重要なことではないでしょうか。
(中略)
私はまず、お互いの立場を真に理解することから始めなければならぬと思うのです。それにはお互いが、くらしの中のよろこびや悲しみ、のぞみやなげき、それらを自分自身の言葉で、自分自身の筆で記し、それをお互いに交流することが大事ではないかと思うのです。そのことを通じて働く農民も都会の人も、その人間としての願いとするところが、遠くへだてるものではないことを発見できるでしょう。そして都市と農村の生活条件のちがいを乗り越え、同じ人間としての共感が、温い心の交流をもたらしてくれるのではないかと思うのです。
引用:『ものいわぬ農民』P207
農民の貧しく冷たい現実を伝えることはどういうことなのか、それは農村のくらしをよくするため。そしてそれには多くの人たちに「共感」を得ることが必要であると祖父は考えたと言います。
まとめ:編集者の原点は「メッセージを伝え誰かを動かすこと」
この本に影響を受け、岩手の農民・県民たちの実態を把握するべき、という人たちが現れ、県民の意識改革のため雑誌を創刊した若者たちがいたそうです。祖父の想いは確実に誰かに伝わり、誰かを動かすことになったのです。
祖父はわたしが小学校低学年のころに亡くなったのであまり記憶はないのですが、立派な本がある書斎でたまに書き物をしたり、新聞を読んでいたりした静かでやさしい黒縁メガネの祖父が大好きでした。
今「同じ編集者しているよ」って伝えたら、どんな顔するでしょうか。雑誌編集からこの業界に入り、現在はWeb編集者として働いているわたしですが、長年編集者として続けてきても、自信を失ったり、時には向いていないんじゃないかなあ……と落ち込むことがあります。そんな悩みを相談したら、どんな言葉で励ましてくれたでしょうか。
「なりゆき」で選んだと思っていた編集者という職業は、もしかしたら祖父に導かれたのかもしれないーーなんて、昭和20年代に編集者として奮闘していた祖父の姿は、タイムスリップして今のわたしを励ましてくれました。
わたしも編集者として、コンテンツに伝えたいメッセージを込めて制作し、それが誰かの行動へとつながるように発信し続けていきたいと思います。