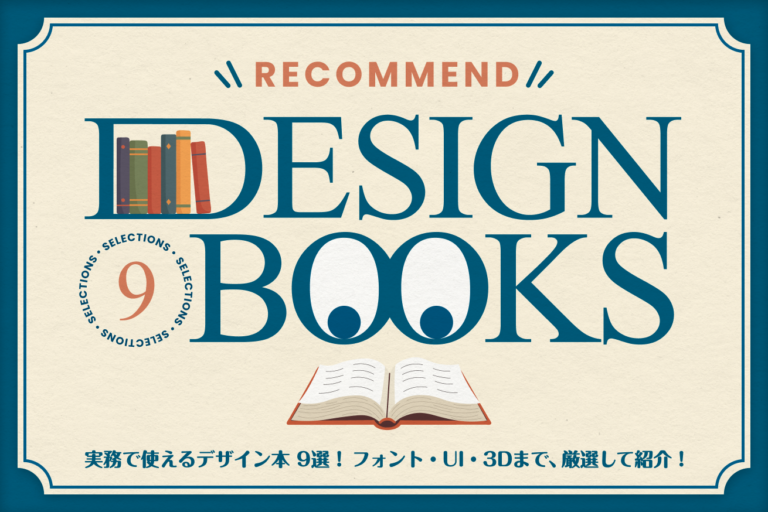※本記事はYouTube動画を元に編集しています。動画では、マーケターのまこりーぬが、採用サイトについて率直な疑問を次々にぶつけています。記事とあわせて、ぜひ本編もご覧ください!
こんにちは、LIG CH ディレクターのりこぴんです!
「採用サイトってどんなところに注意して制作すればいいの?」
「新卒と中途でデザインに違いはあるの?」
「求職者はどんな情報を求めているの?」
など、採用サイトならではの悩みポイントも多いのではないでしょうか。
今回はそんな採用サイト制作のあれこれを、採用戦略に強いWeb制作会社である株式会社ベイジ・代表取締役の枌谷さんに伺いました。
現在採用サイトを制作しているデザイナー・ディレクターの方や、採用担当者の方はぜひ最後までご覧ください!

|
株式会社ベイジ 代表取締役 枌谷 力(そぎたに つとむ)氏1997年に株式会社NTTデータ入社。2001年にデザイナーに転職し、2つの制作会社でデザイナー、ディレクターとしての経験を積んだのち、2007年にフリーランスとして独立。2010年にベイジ起業。デザイナーとしてのキャリアを軸にしながら、BtoBマーケティング、UX、オウンドメディア、SNS、コンテンツ、経営、採用、キャリア、組織作りなど、様々なテーマで活動。2021年にはインフラ構築やシステム開発を手掛けるクラスメソッドのCDOにも就任。 |
|---|
目次
NG① 抽象的な言葉ばかりを並べる
 悪い採用サイトっていうのは、「求職者がこんな情報欲しいなと思って来たのに載っていない、あるいは載っているけど見つけられない、見つけるまでにすごく邪魔が入るサイト」と定義をしています。
悪い採用サイトっていうのは、「求職者がこんな情報欲しいなと思って来たのに載っていない、あるいは載っているけど見つけられない、見つけるまでにすごく邪魔が入るサイト」と定義をしています。
一方で良い採用サイトとは、「求職者が欲しいと思う情報がちゃんと載っていてそれが使いやすく、すぐ手に入るサイト」と定義しています。
悪い採用サイトの共通点には「求職者が求めている情報が十分に満たされていない」という特徴があります。
ファーストビューに「Challenge to the future」のようなキャッチコピーを置いているサイトは多くありますが、求職者からすると「で、具体的にどんな仕事をするの?」と疑問に思うはず。情緒面を優先し過ぎて、必要な情報が載っていない、なんてことは避けるようにしましょう。
求職者が知りたいと思っている情報として……
-
- 募集要項
- 具体的な仕事内容
- キャリアパス
- 教育制度
- 福利厚生
- 一緒に働く社員の声
などがあげられます。
たとえば、エンジニア職であれば、どんな開発環境で、どんな技術スタックを使って、どんなプロジェクトに携われるのか、といった情報が重要になります。
営業職であれば、どんな顧客を相手に、どんな商材を扱い、どんな目標を達成するのか、といった情報を具体的に示す必要があります。
抽象的な言葉を並べるのではなく、具体的な情報を提供することで、求職者は入社後のイメージを持ちやすくなり、応募意欲が高まる傾向にあります。
NG② デザインギャラリーサイトを鵜呑みにする
 「良い採用サイトをギャラリーサイトから探す」という行動がデザイナー・採用担当者の中で一定数起こっているのですが、ギャラリーサイトはあまり見ないほうが良いです。
「良い採用サイトをギャラリーサイトから探す」という行動がデザイナー・採用担当者の中で一定数起こっているのですが、ギャラリーサイトはあまり見ないほうが良いです。
ギャラリーサイトに載っているサイトは、「デザイナーが見てビジュアル的に優れている」という判断をしているわけであって、採用サイトの基本コンセプトである「求職者が欲しい情報をきちんと載せている」という観点で評価されてるわけじゃないんですよね。
デザインギャラリーサイトに掲載されているWebサイトは、たしかに見た目が美しく、洗練されたものが多くあります。
しかし各サイトのデザインには、それぞれ明確な意図があり、計算された設計がなされていることがほとんどです。見た目の印象だけを真似するのではなく、その背景や目的を理解するようにしましょう。
また、ギャラリーサイトに掲載されているサイトは、ブランディングを重視した採用サイトや大手企業のサイトも多く、中小企業や知名度の低い企業にとっては参考にならない場合もあります。
デザインギャラリーサイトを参考にすることは、クリエイティブのヒントを得るという意味では有効です。しかし、それを鵜呑みにして、自社のターゲットや目的を考慮せずにデザインを決定してしまうのはNGです。
NG③ 募集要項がわかりづらい場所にある
 弊社で大規模アンケートを行ったり、クライアント支援するたびにインタビューを実施していて、トータルで1万を超えるデータが残っています。その結果から、「募集要項を真っ先に見る」というのが多くのケースで見られる傾向です。
弊社で大規模アンケートを行ったり、クライアント支援するたびにインタビューを実施していて、トータルで1万を超えるデータが残っています。その結果から、「募集要項を真っ先に見る」というのが多くのケースで見られる傾向です。
採用サイトとは、募集要項の拡大版です。募集要項をちゃんと見せる、真っ先に見せる、たくさん見せる、ということが何よりも大切ですね。
採用サイトのなかには、ページの下の方に小さく募集要項を設けているというケースも多いのではないでしょうか? しかし、枌谷さん曰く、そのような採用サイトの作りはあまり好ましくないそうです。
ユーザーにとって一番関心のある募集要項。ナビゲーションやファーストビューのすぐ下に募集要項を載せるなど、求職者の目に留まりやすいポイントに募集要項を設置するようにしましょう。
また、ラベリングも大事で、
 ちゃんと言葉として「募集要項」ってラベルが必要なんですよね。
ちゃんと言葉として「募集要項」ってラベルが必要なんですよね。
たまにあるのが、Join us。この先に何あんだろうみたいに思います。
また正解か不正解かの間にあるのが、Entry。エントリーって書かれると、エントリーする気のある人は見に行くんですけど、ちょっと見たいけどエントリーはまだなんだよなって人はエントリーの先に募集要項が載っているとは思わない、ってケースがあるんですよね。
採用サイトの目的は、求職者が欲しい情報を提供することです。そのためには、曖昧な表現を避け、具体的な言葉を使うように心がける必要があります。
「募集要項を見る」「応募する」「詳細はこちら」など、そのボタンの先にどのような情報があるのか、明確に伝えるテキストを使うようにしましょう。求職者が外国人である場合を除き、極力英語の使用は避けるほうが良いです。
NG④ 新卒採用サイトで過剰なアニメーションを使用する
 学生を子ども扱いしすぎじゃないかなと思っています。
学生を子ども扱いしすぎじゃないかなと思っています。
絵本のようなサイトとかすごいアニメーションとかゲームのようなサイト作るけど、22・23歳ってそんなガキじゃないんですよね。大人と同じようにビジネス書も読めるし、理解できるし、言うほど子どもじゃない。
必要な情報というのは、異業種の未経験者の人と接するときと似てくると思います。
大学生は社会人経験はないものの、ビジネス書を読んだり、将来について真剣に考えていたりする人も多いです。そのような学生に対して、子ども扱いするようなデザインは、逆効果になる可能性があります。
新卒採用サイトの情報量は、「異業種の未経験者の人と接するときに必要な情報とほぼ情報似てくる」と枌谷さんはおっしゃっています。そのため新卒採用サイトでは、派手なアニメーションよりも、その業界の基本知識や仕事内容をわかりやすく説明することのほうが重要です。
NG⑤ 戦略フェーズを疎かにする
 Webサイト作りたいって言われて、いきなりワイヤーフレームとかデザインから入るとだいたいうまくいかないじゃないですか。
Webサイト作りたいって言われて、いきなりワイヤーフレームとかデザインから入るとだいたいうまくいかないじゃないですか。
大切なのは、どういうターゲットに向けて、その企業のどんな価値を表現していくのかという方向性の認識合わせです。どういうターゲットに向けて採用サイトを作るかをちゃんと明確にしておかないと、後の工程が全部うまくいかなくなってしまいます。
それに加え、そもそも成果の定義がちゃんとしているかというのも重要です。エントリー数が課題なのか、内定承諾率が課題なのか、求めている人物像がなかなか来ないなど、企業によって問題点はさまざまです。
採用フローのどの部分に課題があって、どういう解決をしたいから採用サイトを作るという考え方をしないと、成果が出なかったのはそもそもそこが問題じゃなかったからね、となってしまいます。
採用サイト制作において、戦略フェーズは非常に重要なプロセスです。誰に向けて発信したいのか、どんな価値を持っているのか、といった根本的な部分を明確にすることで、その後の制作工程がスムーズに進み、効果的なサイトを作ることができます。
戦略フェーズでは、以下のような項目を明確に定義する必要があります。
- KPI:採用サイトの目標を数値化し、効果測定を可能にする。
職種定義:募集職種の優先順位を明確にする。
ターゲット:どんな人材を採用したいのかを明確にし、ロールモデル社員を具体的に設定する。
訴求ポイント:企業の強みや魅力を洗い出し、ターゲットに響く価値を明確にする。
これらの項目を定義せずに、いきなりデザインに着手してしまうと、ターゲットに響かない効果の低いサイトになってしまう可能性があります。
NG⑥ 求める人物像を現場からヒアリングしない
 社長の考える求める人物なんかだいたい外れていますよね(笑)。
社長の考える求める人物なんかだいたい外れていますよね(笑)。
私も52歳だけど、やっぱり20代の本当の心理はリアリティ持ってわかんないですよね。だから聞いて理解させていただくという感じです。
経営層の考える求める人物像と、現場が本当に必要としている人材にギャップがある場合があります。また、経営層は、求職者の最新のニーズや動向を把握しているとは限りません。枌谷さん自身も経営者でありながら、20代の求職者の本当に理解するのは難しいと話されていました。
現場の意見を取り入れるためには……
-
全社アンケート:会社のことを社員がどう見ているか、入社前にどんなことを求めていたか、入社してどんなギャップがあったか、などをアンケートで収集する。
ロールモデル社員へのインタビュー:求める人物像に近い社員にインタビューを行い、どんな企業の魅力を感じて入社を決めたのか、などを聞き出す。
現場の意見を積極的に取り入れ、求める人物像を明確に定義することで、より効果的な採用サイトを制作することができます。
NG⑦ 事業フェーズに合わない予算設定をする
 事業が黎明期の会社が、いきなり100ページも採用サイト用意するのは得策とは思えなくて、その会社は1ページでいいと思います。
事業が黎明期の会社が、いきなり100ページも採用サイト用意するのは得策とは思えなくて、その会社は1ページでいいと思います。
一方で、上場準備に入ったり、採用が年間数十名とか超え出すようになってきたり、エージェントへの支払いが数千万超えるみたいな会社は、ちゃんとした採用サイトを作ったほうが良いと思いますね。
「採用サイトに費用をかけたいと思っているが、いくらかければ良いかわからない」という場合は、「人材会社などに年間いくら払っていて、リニューアルすることで自然応募がいくら浮くのか」という計算をすると適切な予算が見えてきます。
黎明期の企業に関してはまずは必要最低限の情報に絞り、事業の成長に合わせて徐々にコンテンツを拡充していくのが良いでしょう。
NG⑧ 採用サイトだけですべてを解決しようとする
 採用サイト自体は認知チャネルになりません。認知チャネルが別にあって、それを効率化したり、加速させたりするチャネルです。
採用サイト自体は認知チャネルになりません。認知チャネルが別にあって、それを効率化したり、加速させたりするチャネルです。
そのため、採用サイトを作ったからといって、エントリー数がバコーンと上がったりしないんですよね。
そもそもの年収や労働条件を見直しましょうという採用サイト以外にも課題があったりします。
採用戦略を考えた上でどういったコンテンツを載せていくかを考えるようにしましょう。
求職者は、複数の情報源を比較検討しながら自分に合った企業を探していることがほとんどです。労働条件、福利厚生、会社の雰囲気など、さまざまな要素を総合的に判断して入社に至ります。
そのため、採用サイトを制作したからといって母集団が大きく増加する、内定受諾率が向上するなどといったことは見込めません。採用戦略の上で採用サイトがあることを念頭に置くようにしましょう。
また情報源も複数のメディアから収集していることがほとんどです。キャリアSNSや企業のSNSアカウント、社員のブログ、転職口コミサイトなど、さまざまなチャネルから収集しています。
採用サイトだけでなく、他のチャネルも活用し積極的に情報発信をおこなうことが重要です。
まとめ
ベイジ代表・枌谷さんが語る、「採用サイト制作でよくある8つのNGポイント」をご紹介しました。
採用サイトは企業と求職者を繋ぐ重要なツールです。「求職者のニーズにあった情報発信をすること」が何よりも大切だということを枌谷さんのお話を聞いて感じました。
NGポイント以外にも、採用サイトにかけるべき費用目安や、採用サイト制作の流れなど、さらに詳しく採用サイトについて伺っています。ぜひYouTubeにてチェックしてみてください!