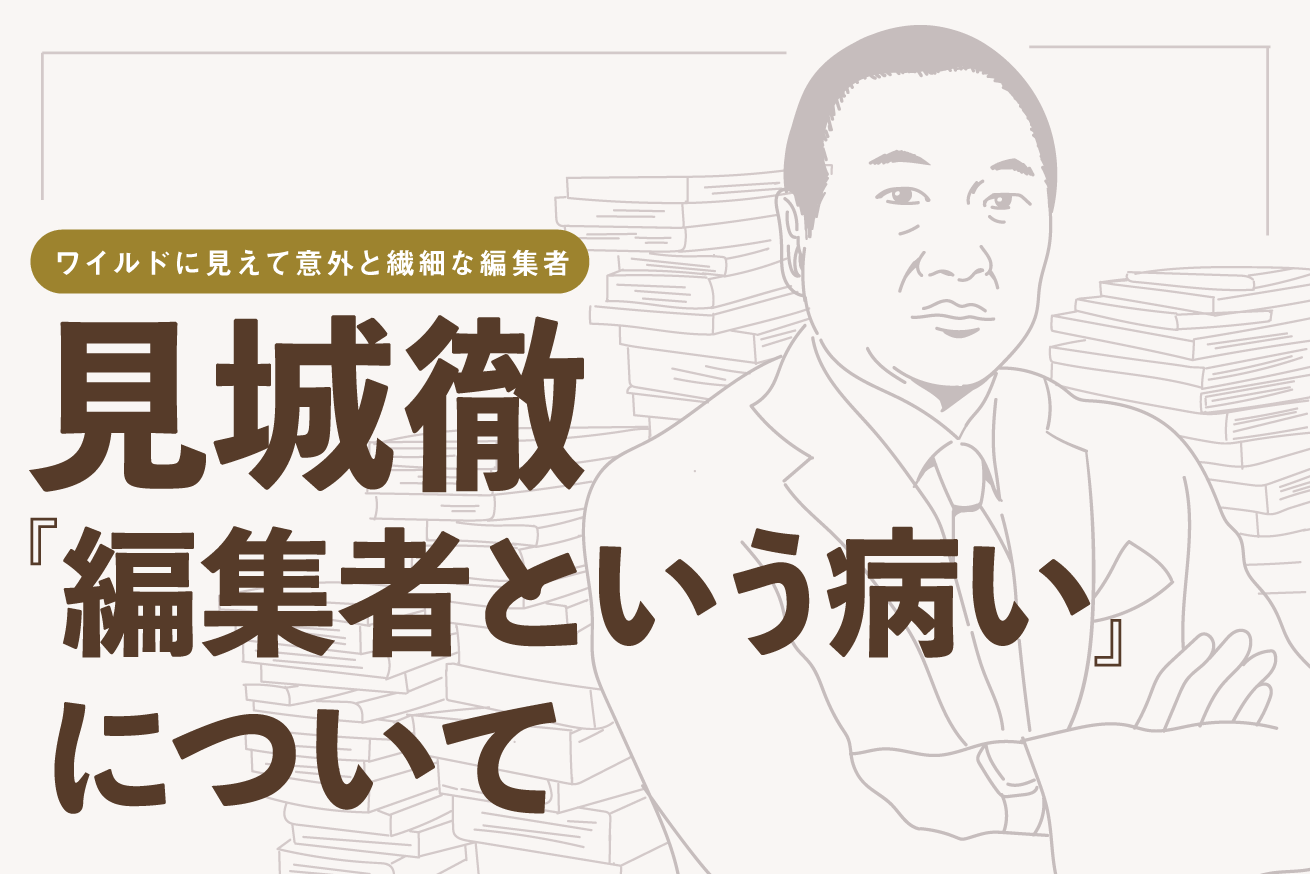こんにちは。LIGブログで記事広告の制作・進行を担当しているメディアディレクターのバンビです。
僕は前職では紙媒体での執筆業務(ライティング)をメインにやっており、編集の仕事を本格的にやるようになったのはLIGに入ってからです。まだまだ「編集」の仕事の全体像を掴めていないのが今の悩みです。
そこで、このLIGブログで月1冊、編集者の「レジェンド」の方々が書いた編集論の本を読み、自分が考えたことをアウトプットしていこうと思い立ちました。
1回目となる今回は、この本をテーマにしたいと思います。
編集者として数々のベストセラーを生み、自ら出版社・幻冬舎を立ち上げて経営者としても成功している見城徹氏が、編集観・仕事観を語った本です。
見城徹『編集者という病』とはどんな本か
幻冬舎を創業したことで知られる編集者・見城氏のインタビューとエッセイで構成されたノンフィクションで、初版は2007年に出版されています。石原慎太郎や中上健次、村上龍といった作家から、尾崎豊や坂本龍一、松任谷由実などの才能溢れるミュージシャンとの出会いや、どう考えながら編集者と向き合っているのかなどを語っています。
本書は「SOUL OF AUTHOR」「SOUL OF EDITOR」「SOUL OF PUBLISHER」の三章で構成され、第一章では見城氏がこれまで関わってきた作家や著名人たちとのエピソードがエッセイ形式で、第二・三章では主に対談形式で人生観や編集論が展開されています。
「売れなければ読者にとって必要ないコンテンツである」という、見城氏の考え方が凝縮された一冊です。
売れているコンテンツに備わる4つの条件
本書の序盤で見城氏は以下のように語っています。
僕は常々売れるコンテンツ(本であれテレビ番組であれ何であれ)は四つの要素を兼ね備えている、その必要条件を満たすものは必ずヒットすると思っています。
①オリジナリティがあること。
②明解であること。
③極端であること。
④癒着があること。
(出典:『編集者という病い』14ページ)
①②③まではたしかに……と思ったんですが、④の癒着があるというのは、どういうことなんでしょう……? 「癒着」という言葉にはマイナスなイメージがあります。しかし見城氏にとって、決して「癒着」はマイナスな表現ではなく、仕事をするうえで欠かせない要素であるようです。
ベストセラーとなった尾崎豊『誰かのクラクション』や郷ひろみ『ダディ』などの作品は、プライベートも含めて作家と四六時中一緒にいて議論を交わし、濃密な人間関係を築くことで初めて生まれたものだ、ということが語られています。
だけど、その人たちとは、すぐに仕事にならなくてもいいと思っていました。それは10年後かもしれないし、20年後かもしれないけれど、相手ときっちり結んで、信頼関係さえ築いていれば、かならずいつか仕事になる。むこうのほうから「いろんな出版社から申し込みがあるけど、自分はあなたとやりたい」といってきてくれるように持っていくのが僕の信条なんです。
(出典:『編集者という病い』168ページ)
10年、20年先のことまで考えながら周りの人と仕事をしたことがないので、正直この感覚がよくわからなかったのですが、たしかに信頼関係を築くことは、当たり前かつ基本的な行動だと思っています。僕の仕事でいえば、関わっている案件に全力を注いで結果を出し、「もう一度あなたと仕事がしたい」と思ってもらうことが、いまできる自分なりの信頼関係の築き方なのかもしれません。
恋愛をしない編集者はだめ!
ちなみにこの本には、見城氏の「恋愛」に関する考え方もハッキリと書かれています。
失恋を多くしていないやつはだめですよ。
(中略)
人間とは何かとか、人間の負の心理、暗黒の感情をずいぶんと学んできたし、恋愛からも学んできましたね。今は恋愛しかないでしょう。だから、編集者で恋愛しないやつはだめですよ。
(出典:『編集者という病い』197ページ)
うーん、なるほど……。
見城氏にとって女性は人生の要かもしれませんが、僕はバンビというあだ名のとおり草食系男子なので、編集者が恋愛しなきゃいけないというのがよくわかりません。正直、ちょっと昭和っぽく感じました。
しかし一理あるかも……とも思う部分もあります。失恋することで、自分に何が足りなかったのか、こうしたらもっと満足させられた、などを考えて次に活かせるはずです。
僕の目標は、「仕事はなんとかするから家のことお願い……」と言ってくれるような女性と出会い、専業主夫になることです。そのためにも、これからマッチングアプリなどを活用し、しっかりと経験値を積んでいきたいと思います。
死への恐怖と戦うために
非常に多くの仕事をこなしてきた見城氏ですが、なぜそこまで自分を追い込むのか、その動機についても語られています。
自分の人生が成功か失敗か、死ぬ瞬間、自分自身が決めるわけです。その瞬間のために僕は今、戦っている。
(中略)
時が経つことは誰も止められない。生老病死だよね。それを受け入れられるかどうかなんだけど、僕はダメなんです。生きている瞬間瞬間で自分を満たしてやらないと……。
(出典:『編集者という病い』196、197ページ)
「えっ、そうなの?」と僕は思ってしまいました。自分の人生が成功か失敗かは、死んだらどうでもいいことなのに……と感じました。
見城氏は、「死ぬ瞬間のために戦って、生きている自分を満たす」ということが仕事の原動力になっているように思います。僕が仕事をしているときの原動力ってなんだろう? と考えたとき、真っ先に浮かんできたのは「金」でした。
小さいことにくよくよするな! はウソ
正直第一章は自慢話のようで少し退屈でした(個人的な感想)。第二章以降は「劣等感のないやつはだめ」「四六時中作者と行動する(癒着?)」「最大のモチベーションは女」といった見城ワールドが満載です。
小さいことにくよくよするな! なんてウソだ。小さなことにくよくよせずに、大きなことをプロデュースできるできるわけがない。小さな約束を守れないやつに大きなことができるわけない。例えばトイレ掃除のおばちゃんに『永遠の仔』が読みたいと言われ、その日に在庫がなければ、おばちゃんの当番の日を手帳に書き残し、次の機会にちゃんと渡せなければダメだと思う。
(中略)
プロデュースの第一歩は小さな約束を必ず守ることだ。自分一人だけで全ては動かない。要求したものを受けいれてくれるのも人間なのだから、この人に頼まれたら断れない、この人にやれと言われたら懸命にやらざるを得ないと思われることが大切だと感じる。
(出典:『編集者という病い』221、222ページ)
見城氏は本書で「編集者は酒が飲めなきゃだめ」「失恋を多くしてないやつはだめ」と語っており、小さなことを気にしない破天荒で豪快な人間だと思っていたので、正直意外でした。
でも、小さなことにくよくよし続けた結果、あれだけのベストセラーを生み出すことにつながったのではないかと感じました。
僕の仕事でいえば、自分で決めた初稿提出のスケジュールを守れなければ、案件を進める資格はないという話だと思います。要するに、「仕事においては小さいことにくよくよしろ!」ということですね。僕がいまこの瞬間からでも実践できる心がけだと思いました。
見城氏にとっての編集観とは?
見城氏にとっての編集という仕事は、人生を捧げる覚悟を持って挑めということなのかもしれません。やっていることはワイルドに見えていても、実は小さなことの積み重ねがあるからこそ、結果的に大きな仕事をしているように見えているのかなと感じました。
というわけで、今回は見城徹氏の『編集者という病い』をテーマに書いてみました。今回は「編集者の仕事」をテーマにした本でしたが、次回は同じく幻冬舎の編集者を取り上げた本を考察したいと思います。よろしければ、時間があるときに読んでいただければ幸いです! ここまで読んでくださってありがとうございます。
以上、メディアディレクターのバンビがお届けしました!