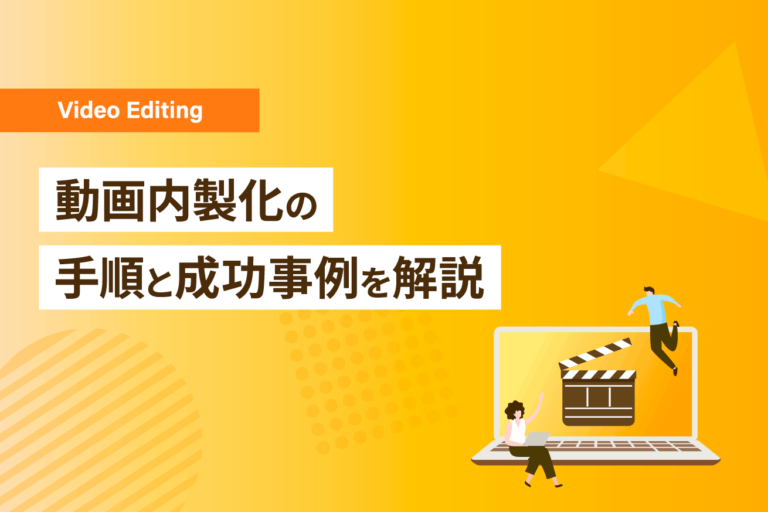「研修を外注したいけど、どの会社を選べばいいかわからない」「自社に合った内容かどうか判断が難しい……」
研修会社は数多く存在し、このようなお悩みを持つ人事・研修担当者の方も多いかと思います。厚生労働省の「令和6年度 能力開発基本調査」によると、能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は79.9%にも達しており、多くの企業が人材育成において課題を抱えていることがわかります。
そこで今回は、法人向けIT研修をおこなっている弊社の目線で、研修会社を選ぶ際に押さえるべき7つのポイントをご紹介します。研修を受ける役職別の選定基準からよくある失敗例と対策まで、人事・研修担当者が知っておくべき情報をまとめました。
- 未経験から現場レベルまで要望に応じてカスタマイズ可能
- オンライン・対面どちらも選択可能
- 受講料最大75%オフ、人材開発助成金の申請サポートあり!
「どんな研修会社を選べばいいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください!
研修会社の選び方で重要な7つのポイント
研修会社を選ぶ際には、複数の観点から総合的に判断する必要があります。ここでは、選定の際に押さえておくべき7つの重要ポイントを解説します。
- 💡研修会社選びのポイント
-
- 研修の目的と到達レベルが明確か
- カスタマイズ対応が可能か
- 研修スタイルが柔軟か
- 同業種での実績が豊富か
- 講師の質が高いか
- 費用対効果に見合っているか
- アフターフォローが充実しているか
①研修の目的と到達レベルが明確か
いきなり研修会社に問い合わせるのではなく、「何のために研修を行うのか」「受講者をどのレベルまで到達させたいのか」を明確にしましょう。
私は「あるべき姿」と「現状」のギャップを埋めるための施策の一つが研修だと考えています。まずは自社の現状を把握し、事前に整理しておくと研修会社側としても提案がしやすくなり、より良い研修につながる可能性が高くなります。
- 💡研修の目的として決めておきたいことの例
-
- どのような課題を解決したいのか?
- どのようなスキルを、どんなレベル感で身につけたいのか?
- 研修後、受講者にどのような行動変容を期待するのか?
- 研修の成果をどのように測定したいか?
目的と到達レベルが明確になれば、研修会社選定のための基準もおのずと決まってきます!
②カスタマイズ対応が可能か
研修プログラムは内容が固定(パッケージ化)されているものと、自社の状況に応じてカスタマイズ可能なものがあります。
研修内容をカスタマイズできる研修会社であれば、自社の課題や目的に応じた内容にできるのがメリットです。事前の打ち合わせで自社の状況をしっかりと伝え、それを研修内容に反映してくれる会社を選ぶことが重要です。
ちなみに、パッケージ化された研修は新卒研修やビジネスマナー、専門職における初歩的なスキルを教える場合に利用されており、カスタマイズ型よりも低コストで利用できる傾向があります。
③研修スタイルが柔軟か
研修のスタイルも重要な選定基準です。研修スタイルは主に対面、オンライン、eラーニング(動画研修)、ハイブリッド型の3種類があります。
| 研修スタイル | 特徴 |
|---|---|
| 対面研修 |
|
| オンライン研修 |
|
| eラーニング(動画研修) |
|
| ハイブリッド型 |
|
近年では、座学はオンライン、実践ワークは対面で直接指導というふうに、ハイブリッド型の研修も増えています。自社のニーズや受講者の状況(勤務地が分散している、業務の都合で集合が難しいなど)に合わせて、柔軟な研修スタイルが可能な会社を選びましょう。
④実績と経験が豊富か
「1,000社以上導入」「大手企業も利用」など、数や会社規模をアピールしている会社も多くありますが、同業種や類似企業での研修実績が豊富かを確認してみてください。業界特有の課題やニーズを理解しており、効果的な研修が期待できます。
- 確認すべき実績情報
-
- 研修実施件数
- 研修対象企業の業界・規模
- リピート利用している企業の割合
- 受講者満足度
- 具体的な成果事例
研修会社のWebサイトや資料で実績を確認し、不明な点は直接問い合わせて確認しましょう。
⑤講師の質が高いか
研修の質は、講師の質に大きく左右されます。研修会社に相談する際は、講師の経歴や実績を必ず確認しましょう。
- 💡講師に確認しておきたいポイント
-
- 実務経験:その分野での実務経験が豊富か
- 研修実績:講師としての経験が豊富で、多くの企業で研修を行っているか
- 受講者からの評価:過去のアンケートデータなどを見せてもらえるか
- 専門資格:関連する資格や認定を持っているか
- コミュニケーション力:分かりやすく教える能力があるか
研修会社によっては、講師のプロフィールや研修実績、受講者の感想を公開しています。不明な点は研修会社に直接尋ね、講師の質について納得できる情報を得てから契約しましょう。
⑥費用対効果に見合っているか
研修の費用は、内容、時間、受講人数、カスタマイズの有無などによって大きく異なります。重要なのは、費用の安さではなく費用対効果です。
費用対効果を測る一例として、カークパトリックの4段階評価モデルなどがあります。また、初期段階では金銭的コスト(外注費)と、社内リソースのコストの両面から評価する方法もあります。
たとえば、デザイナー職の新卒向けにソフトの基本的な使い方を教える研修を考えてみましょう。社内のデザイナーが講師を務めることも可能かもしれませんが、社内デザイナーの時給×拘束時間と外部研修会社への支払い額を比較してみてはいかがでしょう。外部に依頼した方が、金銭的にも、社員の生産性的にも、トータルでコスト削減になる可能性があります。
| 項目 | 社内実施 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 金銭的コスト | 社外への支出はない | 研修会社への支払いが発生 |
| 社内リソース | 講師役社員の業務時間を大きく消費 (準備+実施で数日〜数週間) |
担当者の調整業務のみ (数時間程度) |
| 研修の質 | 個人のノウハウによる | 初歩を押さえているが応用が難しい可能性あり |
| トータル評価 | 機会コストを含めると高コストになることも | コスト効率は良いが質の面で要検討 |
費用対効果を正しく評価するには、目に見える金銭だけでなく、社員の時間という見えないコストも含めて総合的に判断することが重要です。
⑦アフターフォローが充実しているか
研修内容ももちろん重要ですが、研修の効果を最大化するにはフォローアップが重要です。
- 確認すべきアフターフォロー内容
-
- 研修後の質問受付体制
- 受講者へのフィードバック提供
- 研修効果の測定サポート
- フォローアップ研修の実施
- 研修資料の提供(研修後も復習できる)
充実したアフターフォロー体制があれば、研修で学んだ内容を実務に活かしやすくなり、より高い研修効果が期待できます。
よくある失敗例と対策
研修会社選びでよくある失敗例を知っておくことで、同じ失敗を避けることができます。ここでは、典型的な5つの失敗パターンと、その対策を紹介します。
失敗例①:価格だけで選んでしまった
予算を重視するあまり、最も安い研修会社を選んだ結果「期待した効果が得られなかった……」という失敗はよく聞きます。
価格だけで判断すると、研修の質や講師の経験、サポート体制などが不十分な場合があります。結果的に、投資した時間とコストに見合った成果が得られず、かえって非効率になってしまいます。
💪対策
費用対効果で判断しましょう。研修内容、講師の質、提供される資料、アフターフォローなどを総合的に評価し、投資に見合った価値が得られるかを確認してください。
複数社から見積もりを取り、価格と内容のバランスを比較することをおすすめします。
失敗例②:自社の状況を十分に伝えなかった
研修会社は、依頼企業の状況を十分に理解していないと、最適な研修を提案できません。
必ず自社の課題や状況を事前に取りまとめておきましょう。詳しく伝えずにニーズに合わない内容になってしまうと、元も子もありません。
💪対策
研修会社との打ち合わせでは、以下の情報を詳しく伝えましょう!
- 自社の業界、事業内容、組織文化
- 研修の目的と背景
- 受講者のスキルレベルや経験
- 過去の研修の実施状況と課題
- 期待する成果と評価方法
失敗例③:研修の目的が曖昧なまま依頼した
初めて新卒が入社する中小企業やベンチャーの場合、「とりあえず新人研修をやらなければ」という漠然とした理由で研修を依頼することもありがちです。
研修の目的が明確でないと、適切な研修内容を選べず、効果測定もできません。結果的に、研修が形骸化してしまいます。
💪対策
少なくとも以下を明確にしたうえで、研修会社に相談しましょう!
- 研修前に明確にすべき事項
-
- 解決したい課題は何か
- 受講者に何を学んでほしいか
- 研修後、どのような行動変容を期待するか
- 研修の成果をどう測定するか
- どの程度の予算と時間をかけられるか
失敗例④:1社だけで決めてしまった
最初に見つけた研修会社や知り合いの経営者から聞いた会社に依頼すると、「他社の方が合っているのでは?」と後悔してしまうこともあります。
研修会社によって得意分野や提供内容が異なるため、複数社を比較検討することが重要です。
💪対策
最低でも2〜3社から見積もりと提案書を取り寄せ、以下の観点で比較してみてください。
| 比較項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 研修内容 | 自社のニーズに合っているか、カスタマイズの柔軟性 |
| 講師の質 | 経験、実績、専門性 |
| 費用 | 見積もり内訳、追加費用の有無 |
| 実績 | 同業種での実績、受講者満足度 |
| サポート体制 | アフターフォロー、質問対応 |
| 担当者の対応 | 提案力、レスポンスの速さ |
よくある質問(FAQ)
研修会社の選定に関してよくある質問をまとめました。
研修会社の費用相場はどれくらいですか?
産労総合研究所の「2024年度 教育研修費用の実態調査」によると、2023年度の従業員1人あたりの教育研修費用の平均は34,606円でした。
企業規模別では以下のような違いがあります。
| 企業規模 | 従業員1人あたりの教育研修費用(2023年度) |
|---|---|
| 大企業 (1,000人以上) |
41,050円 |
| 中堅企業 (300〜999人) |
32,268円 |
| 中小企業 (299人以下) |
31,087円 |
引用元:産労総合研究所「2024年度 教育研修費用の実態調査」
また、厚生労働省の「令和6年度 能力開発基本調査」では、OFF-JT費用の労働者一人当たり平均額は1.5万円と報告されています。
カスタマイズ対応や専門性の高い研修ほど費用は高くなります。複数社から見積もりを取り、費用対効果を比較することをおすすめします。
研修会社への依頼はいつから始めるべきですか?
研修実施予定日の2〜3ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
特に、以下の場合は早めの準備が必要です。
余裕を持って準備することで、複数の研修会社を比較検討でき、より良い選択ができます。
研修会社の選定から契約までの流れを教えてください
研修会社の選定から契約までは、一般的に以下の5つのステップで進めます。
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 1.目的と予算の明確化 | 研修の目的、対象者、期待する成果、予算、実施時期を明確化。社内で研修のニーズを整理し、関係者の合意を得ておく |
| 2.候補のリストアップ | 各社のWebサイトで実績や提供内容を確認する |
| 3.見積もり依頼と比較 | 候補企業に見積もりと提案書を依頼し、提案内容、費用、講師の経歴、実績などを比較して2〜3社に絞り込む |
| 4.面談・打ち合わせ | 絞り込んだ研修会社の担当者と直接面談し、詳細を詰める。可能であれば講師とも面談 |
| 5.最終選定と契約 | 提案内容、費用、担当者の対応、アフターフォローなどを総合的に判断して最終決定 |
オンライン研修と対面研修はどちらが効果的ですか?
オンライン研修と対面研修には、それぞれメリット・デメリットがあります。研修の目的や内容によって、適した形式を選ぶことが重要です。
| 対面研修 | オンライン研修 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 向いている研修 |
|
|
最近では、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型研修も増えています。それぞれの長所を活かした柔軟な研修形式を選べる研修会社を選ぶと良いでしょう。
研修の効果測定はどうすればよいですか?
研修の効果測定は、研修の価値を可視化し、次回の改善につなげるために重要です。代表的な効果測定の方法をご紹介します。
- カークパトリックの4段階評価モデル
-
研修効果の測定に広く使われているフレームワーク。以下4段階で評価をおこなう。
- 1.反応(Reaction)
研修直後のアンケートで、満足度や理解度を測定 - 2.学習(Learning)
テストやレポートで、知識やスキルの習得度を測定 - 3.行動(Behavior)
研修後1〜3ヶ月後に、実務での行動変容を観察・評価 - 4.結果(Results)
業績や生産性など、ビジネス成果への影響を測定
- 1.反応(Reaction)
具体的な測定方法
| タイミング | 測定方法 | 測定内容 |
|---|---|---|
| 研修直後 | アンケート調査 | 満足度、理解度、講師の評価 |
| 研修終了時 | テスト、ロールプレイ | 知識・スキルの習得度 |
| 1〜3ヶ月後 | 上司評価、行動観察 | 実務での行動変容 |
| 3〜6ヶ月後 | KPI測定、業績分析 | 業務成果への影響 |
研修会社によっては、効果測定のためのアンケートやフォローアップ研修を提供しているところもあります。効果測定の支援も含めて研修会社を選ぶと、研修の価値を最大化できます。
まとめ
研修会社選びは、企業の未来を担う人材を育てる重要な意思決定です。この記事で紹介した7つのポイントや選定の流れを参考に、自社の課題を解決できる最適なパートナーを見つけましょう。
- 未経験から現場レベルまで要望に応じてカスタマイズ可能
- オンライン・対面どちらも選択可能
- 受講料最大75%オフ、人材開発助成金の申請サポートあり!
「どんな研修会社を選べばいいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください!