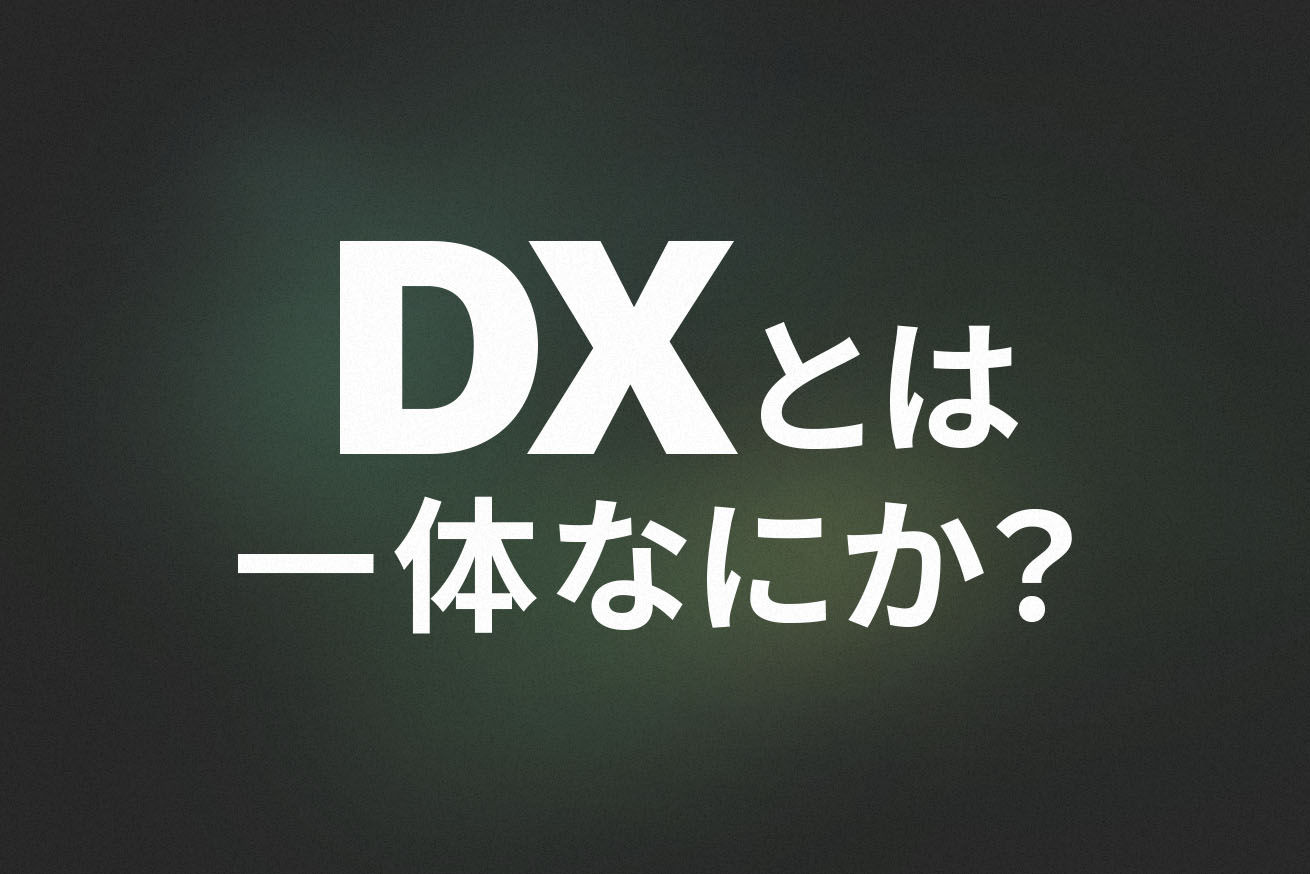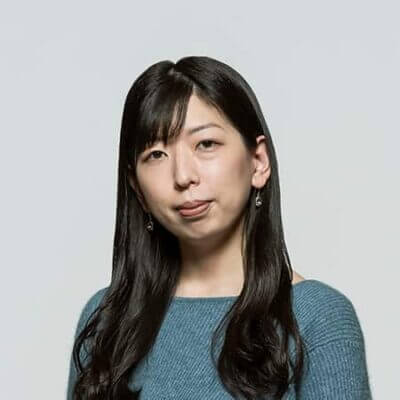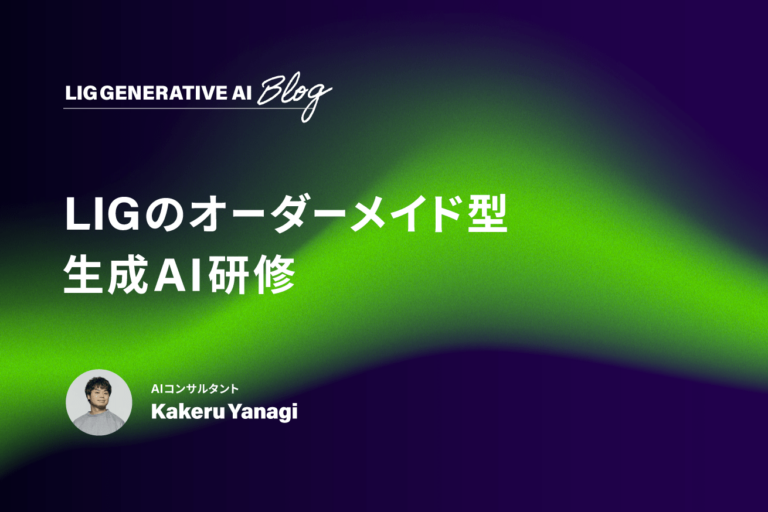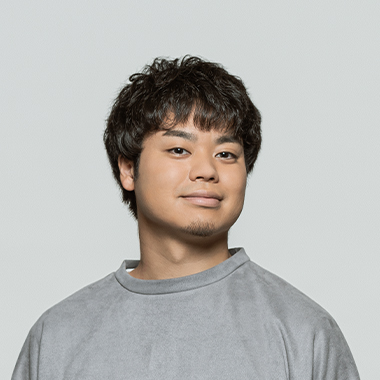LIGブログ編集長代理のまこりーぬです。
この2〜3年でよく耳にするようになった「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。「デジタルを活用した変革」だとざっくりは理解していても、いざ説明するのは難しく、つい言葉に詰まってしまいませんか?
そこで今回、私自身「DXとはなにか」を自分の言葉で説明できるようになるべくアレコレ調べた過程を記事にしました。「DXって、なに!?」とお困りのみなさんへ、少しでも参考となれば幸いです!
DXの定義
まずはDXを推進している経済産業省から言葉の定義を拾っていきましょう。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
平成30年12月 DX 推進ガイドライン 経済産業省より
……初っ端からカタカナ語が爆発していたらどうしようかと思いましたが、想像以上に易しい言葉で語られていて安心しました。一つひとつの言葉をしっかり読み込んでいくと、DXとはこうしたニュアンスを含む概念であることがわかります。
| デジタルを活用した変革 + 変化の激しいビジネス環境において企業が生き残るためのもの 業務プロセスだけでなく、ビジネスモデルや組織そのものを変革すること |
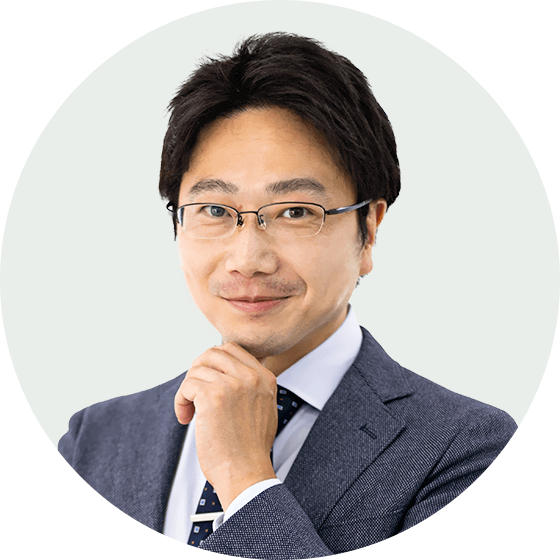 DXが叫ばれている背景、そして「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを理解すると、DXとはなにかを説明しやすくなると思いますよ。
DXが叫ばれている背景、そして「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを理解すると、DXとはなにかを説明しやすくなると思いますよ。 あ……そういえば社内にDXにめちゃくちゃ詳しい人いました……! てっペーさん、ぜひお知恵をご教示ください!!!(※てっペーさんは2021年にアクセンチュアからLIGへやってきたバリバリのコンサルタントです)
あ……そういえば社内にDXにめちゃくちゃ詳しい人いました……! てっペーさん、ぜひお知恵をご教示ください!!!(※てっペーさんは2021年にアクセンチュアからLIGへやってきたバリバリのコンサルタントです)DXがなぜ叫ばれるのか
 DXってもはやバズワードとも言えますが、なぜいま日本社会でこんなに叫ばれているんでしょうか?
DXってもはやバズワードとも言えますが、なぜいま日本社会でこんなに叫ばれているんでしょうか?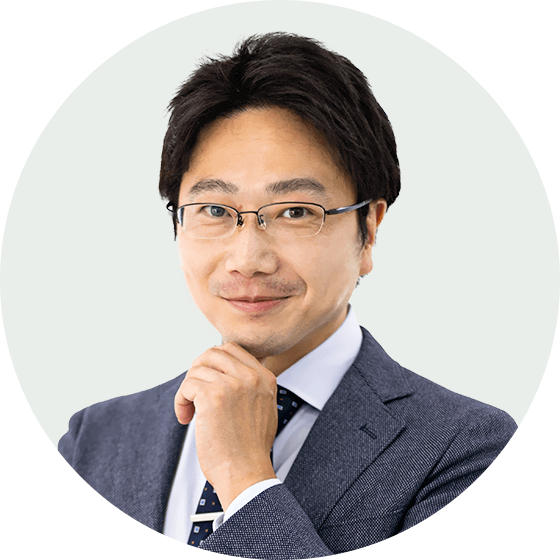 例をあげながら説明しましょうか。まこりーぬさん、一番最後にレンタルビデオショップへ足を運んだのはいつですか?
例をあげながら説明しましょうか。まこりーぬさん、一番最後にレンタルビデオショップへ足を運んだのはいつですか? えーっと、もう2年前くらいですかね。最近はNetflixでおなかいっぱいです。梨泰院クラスが好きです。
えーっと、もう2年前くらいですかね。最近はNetflixでおなかいっぱいです。梨泰院クラスが好きです。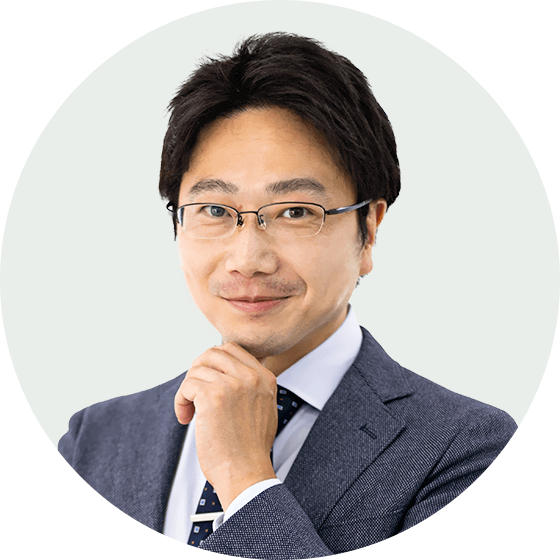 そうですよね。きっとほとんどの人はレンタルビデオショップを訪れる機会がガクッと減り、ビデオオンデマンドサービスを楽しんでいると思います。
そうですよね。きっとほとんどの人はレンタルビデオショップを訪れる機会がガクッと減り、ビデオオンデマンドサービスを楽しんでいると思います。
Netflixは「オンラインのDVDレンタルサービス」会社として1997年に創業し、延滞料のかからない借り放題プランを広めました。その後、通信技術の向上を見越して早々に配信サービスへ舵を切り、高画質の映像配信を実現しています。さらに視聴データをフル活用しておすすめコンテンツのレコメンド精度を高めたり、オリジナル作品の企画に還元してヒット作を続々と生み出したりしています。デジタルを活用して顧客価値を高め売上を伸ばしている、まさにDXを代表する企業です。
一方、こうした華々しい企業の裏側で、延滞料で稼いでいたレンタルビデオショップは当然ながら苦戦を強いられています。GAFAなど世界有数のデジタル企業がどんどん便利なサービスを生み出して既存のビジネスモデルを破壊していくなか、同じやり方でビジネスを続けているだけでは、企業はもう生き残ることができません。
 なるほど……「変化の激しいビジネス環境において企業が生き残るためにDXが必要」っていうのはこういうことなんですね……!
なるほど……「変化の激しいビジネス環境において企業が生き残るためにDXが必要」っていうのはこういうことなんですね……!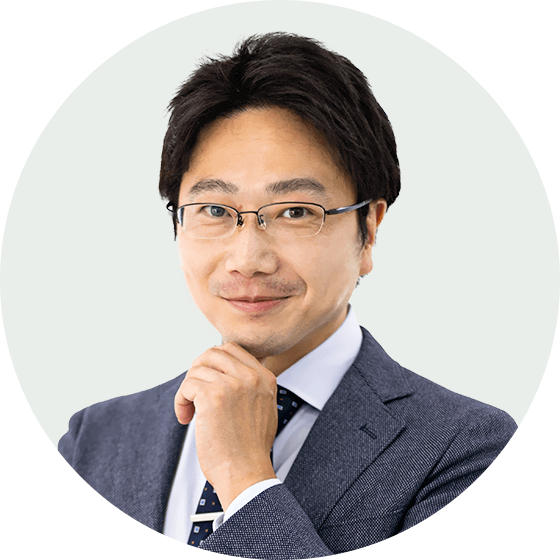 日本を代表する自動車産業ですら、いまや大手6社が束になってもテスラ1社の時価総額には敵いません。こうした危機感から経済産業省が「DX推進ガイドライン」を出し、「みんなでDX進めていこう!」と大号令をかけたわけです。経済産業省は東京証券取引所と共同で「DX銘柄」「DX注目企業」を選出し、DX推進企業に投資が集まるような図らいもおこなっています。
日本を代表する自動車産業ですら、いまや大手6社が束になってもテスラ1社の時価総額には敵いません。こうした危機感から経済産業省が「DX推進ガイドライン」を出し、「みんなでDX進めていこう!」と大号令をかけたわけです。経済産業省は東京証券取引所と共同で「DX銘柄」「DX注目企業」を選出し、DX推進企業に投資が集まるような図らいもおこなっています。 国をあげてなんとかしようという気持ちがひしひしと伝わってきます……!!! その結果「うちもDXしなきゃ! やばい!」という企業がたくさん生まれていったんですね。
国をあげてなんとかしようという気持ちがひしひしと伝わってきます……!!! その結果「うちもDXしなきゃ! やばい!」という企業がたくさん生まれていったんですね。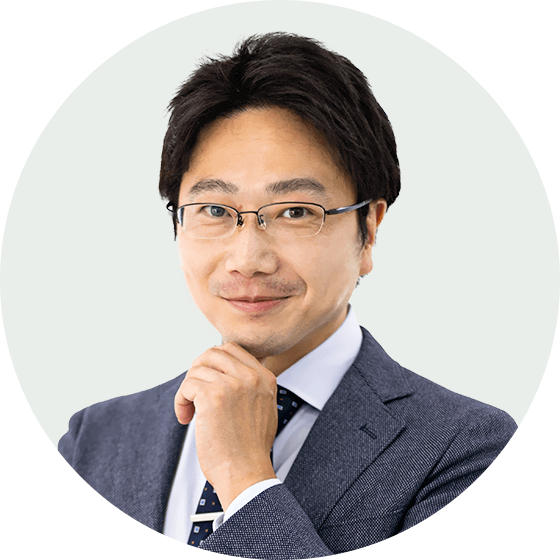 そうですね。「ハンコや請求書をデジタル化しよう」「データをAIで解析して新規事業を作ろう」といった企業はとても増えたと思います。しかし正直なところ、真にDXに成功している、つまりこれからの時代に生き残るだけの競争力を身につけた企業はまだかなり少ない印象です。
そうですね。「ハンコや請求書をデジタル化しよう」「データをAIで解析して新規事業を作ろう」といった企業はとても増えたと思います。しかし正直なところ、真にDXに成功している、つまりこれからの時代に生き残るだけの競争力を身につけた企業はまだかなり少ない印象です。 たしかに、ハンコが電子化するだけでは生き残れませんね……。
たしかに、ハンコが電子化するだけでは生き残れませんね……。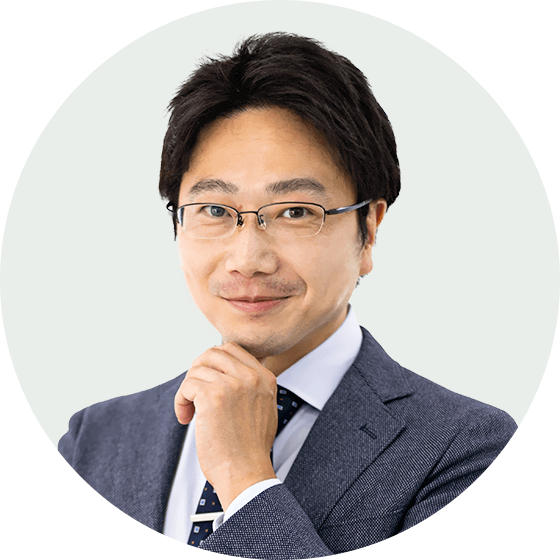 アナログな業務をデジタルに置換することは、DXのはじめの一歩として大事なんですけどね。属人化した業務を効率化すれば、顧客へ価値提供する業務にもっと時間を割けるようになりますから。
アナログな業務をデジタルに置換することは、DXのはじめの一歩として大事なんですけどね。属人化した業務を効率化すれば、顧客へ価値提供する業務にもっと時間を割けるようになりますから。デジタイゼーションとデジタライゼーション
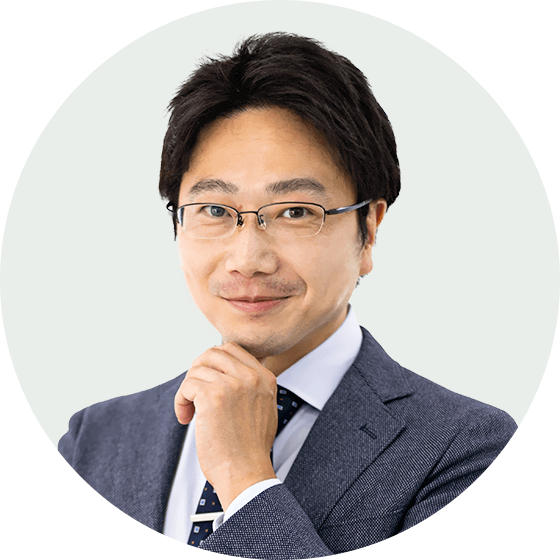 ちなみにアナログな業務をデジタルに置換することは「デジタイゼーション」と言います。
ちなみにアナログな業務をデジタルに置換することは「デジタイゼーション」と言います。 デジタイ……?
デジタイ……?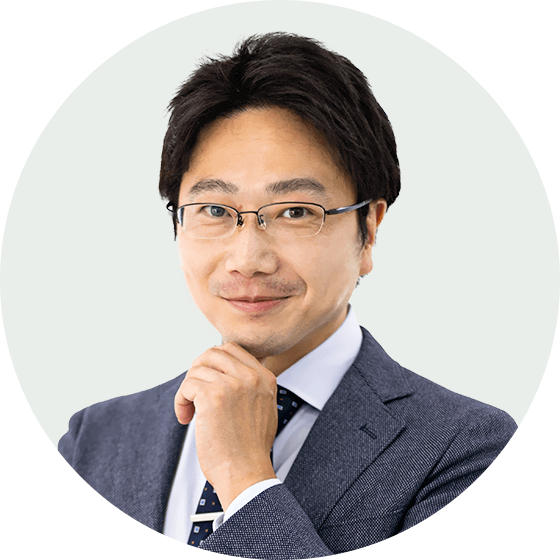 DXには「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3STEPがあるんですよ。ちなみに「デジタライゼーション」と「デジタルトランスフォーメーション」の切り分けは人によって超まちまちですが、こう考えるとわかりやすいと思います。
DXには「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3STEPがあるんですよ。ちなみに「デジタライゼーション」と「デジタルトランスフォーメーション」の切り分けは人によって超まちまちですが、こう考えるとわかりやすいと思います。- STEP1:デジタイゼーション
デジタルの力で業務を円滑化し、人的コストを削減する。
ex.ハンコや請求書の電子化、RPAで業務自動化、ノーコードでWeb制作STEP2:デジタライゼーション
デジタルの力で顧客体験を向上し、新たな事業を生み出す。
ex. ビデオオンデマンド、映像学習アプリ、ネットバンキングSTEP3:デジタルトランスフォーメーション(DX)
デジタイゼーション、デジタライゼーションを全社的・永続的におこない顧客体験を向上、新たな事業を生み出す。結果として企業の競争力が向上し、存在意義(パーパス)が定義される。
 なるほど、全部ごっちゃにDXだと思っていました。こうして見るとDXってビックリ壮大な話ですね。単なるデジタル化ではまったくなく、「生き残りをかけた企業大改革プロジェクト!」みたいな感じですね。
なるほど、全部ごっちゃにDXだと思っていました。こうして見るとDXってビックリ壮大な話ですね。単なるデジタル化ではまったくなく、「生き残りをかけた企業大改革プロジェクト!」みたいな感じですね。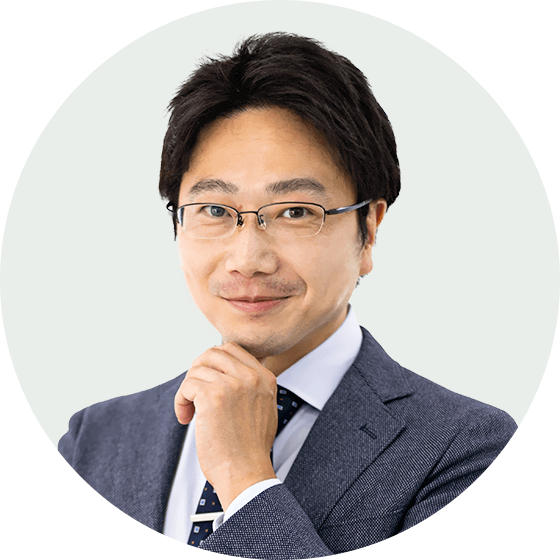 そう、壮大なんですよ。変革するためには既存のビジネスや組織風土を根本から見直す必要があるため、DXは「ディスラプション(破壊)」とセットだと語る人もたくさんいます。
そう、壮大なんですよ。変革するためには既存のビジネスや組織風土を根本から見直す必要があるため、DXは「ディスラプション(破壊)」とセットだと語る人もたくさんいます。DX推進に必要なものはなにか
 だいぶDXの理解が深まってきましたが、なんというかその、推進するの難しすぎませんか?
だいぶDXの理解が深まってきましたが、なんというかその、推進するの難しすぎませんか?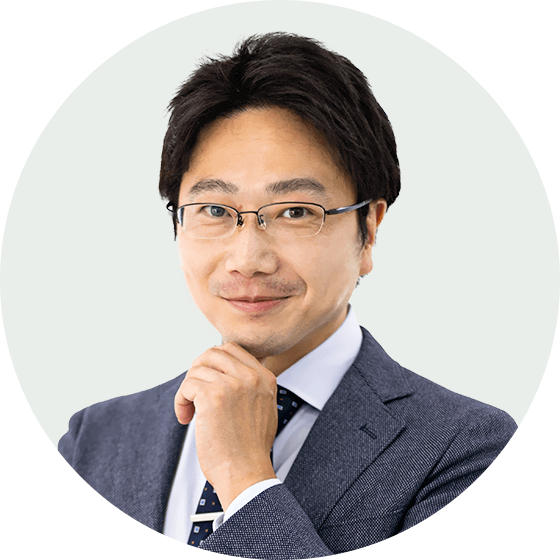 難しいですよ。難しいんですけど、「顧客への価値提供を最大限に高めて、選ばれる企業になりましょう!」と解釈すれば、ちょっとがんばれそうな気がしませんか?
難しいですよ。難しいんですけど、「顧客への価値提供を最大限に高めて、選ばれる企業になりましょう!」と解釈すれば、ちょっとがんばれそうな気がしませんか? たしかに。なんならいままでの企業活動も目指す場所は基本的にそこですもんね。いままでの延長線上で考えずに、もっと顧客視点をもって、使える技術を最大限使って、大胆に変えていきましょう! ってことなのか……。
たしかに。なんならいままでの企業活動も目指す場所は基本的にそこですもんね。いままでの延長線上で考えずに、もっと顧客視点をもって、使える技術を最大限使って、大胆に変えていきましょう! ってことなのか……。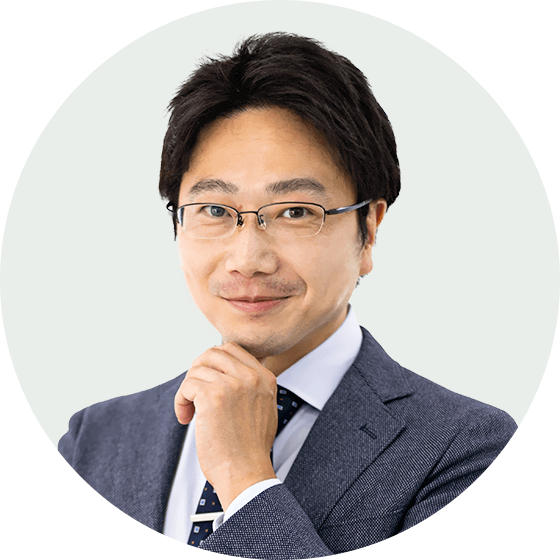 そうです。よってDX推進に必要なのは、IT人材の確保よりもまず、経営者が「うちは変わるぞ」と覚悟を決めて旗を立てることですよね。とくに縦割組織が強い日本企業においては、一部門だけの力で企業の大変革なんてできません。
そうです。よってDX推進に必要なのは、IT人材の確保よりもまず、経営者が「うちは変わるぞ」と覚悟を決めて旗を立てることですよね。とくに縦割組織が強い日本企業においては、一部門だけの力で企業の大変革なんてできません。
その次は、エンジニアやデザイナー、パートナー会社を束ねて、現場社員ともうまく連携しながら物事を動かしていくプロジェクトマネージャーが必要です。このポジションにはビジネスへの理解と、最低限エンジニアとコミュニケーションがとれる技術の知見、そして社内調整力が求められます。……「そんなことができるPM、社内にいない!」という場合、私の古巣のようなコンサルティング会社が支援に入ります。
 なるほど、このポジションにいらっしゃったんですね。
なるほど、このポジションにいらっしゃったんですね。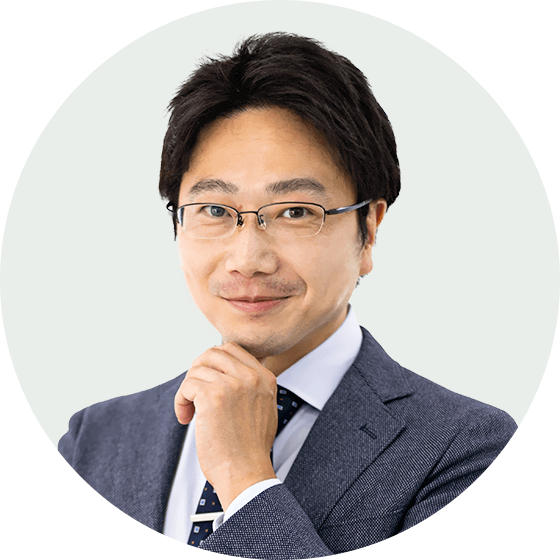 はい。あと必要なのはエンジニアやデザイナーといったクリエイティブ人材ですね。経済産業省が出した有名なレポート「ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開」で「IT人材が足りない!」と叫ばれたこともあり、エンジニア不足についてはみなさんよく理解されていると思います。
はい。あと必要なのはエンジニアやデザイナーといったクリエイティブ人材ですね。経済産業省が出した有名なレポート「ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開」で「IT人材が足りない!」と叫ばれたこともあり、エンジニア不足についてはみなさんよく理解されていると思います。 「レガシーシステムの保守運用に時間とられてるけど、そんなことやってる場合じゃねー!!!」ってやつですね。読みました。
「レガシーシステムの保守運用に時間とられてるけど、そんなことやってる場合じゃねー!!!」ってやつですね。読みました。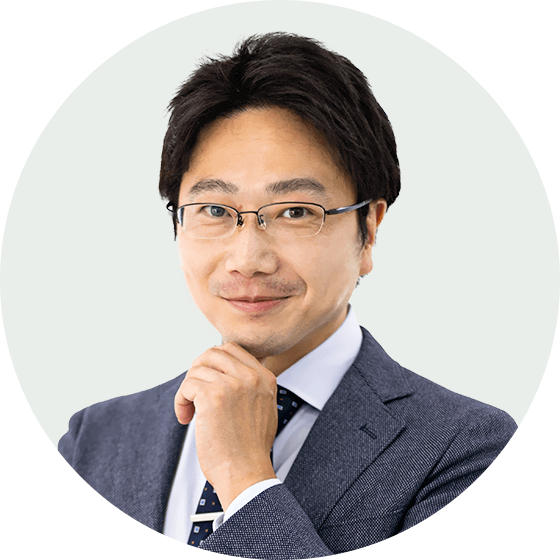 それです。一方、意外と軽視されているのはデザイナーの存在です。DXとは、顧客への価値提供を高めて選ばれる企業となることです。そのためには、なにをやるにしても顧客にとって心地よい体験をデザインする力が欠かせません。
それです。一方、意外と軽視されているのはデザイナーの存在です。DXとは、顧客への価値提供を高めて選ばれる企業となることです。そのためには、なにをやるにしても顧客にとって心地よい体験をデザインする力が欠かせません。
そこで私は、弊社LIGが長年積み上げてきたデザインのノウハウと、東南アジアの豊富なエンジニア人材を活かして、お客様のDXを推進しようとここに転職してきたわけです。
 なるほど……! 非常によく理解できました。てっペーさん、ありがとうございます!!!
なるほど……! 非常によく理解できました。てっペーさん、ありがとうございます!!!まとめ:つまりDXとはなにか
いままでの話を踏まえて、自分の言葉でDXを説明するとこうなりました!
| DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、 データやデジタル技術を活用して顧客に対する提供価値を最大限に高め、変化の激しいビジネス環境でも生き残れる企業へ変革すること |
「データやデジタル技術を活用しよう!」という手段が先行してしまうと、どの方向に進んだらいいのかわからず明後日の方向に邁進してしまいそうですが、既存のビジネスモデルにとらわれずに顧客に対する提供価値を高めることに邁進すると考えると、やるべきことはもっとハッキリと見えてきそうですね。
私はまずは顧客を知るところから、そして世の中にあるDX成功事例をもっとインプットすることでヒントを得るところからスタートしようと思います!!!
おまけ:おすすめのDX参考書籍
複数冊読んだなかでもおすすめできる書籍を紹介します! Web記事よりも体系だってまとまっているため、DXについてもっと理解を深めたい場合はおすすめです。
総務部DX課 岬ましろ
Kaizen Platform須藤さんの著書です。「DXの現場ってこういう感じなのね〜」とイメージが湧きやすく、物語形式で進むので導入書としておすすめです。ちなみに私はマンガだと思って買いました。小説でした。
マッキンゼーが解き明かす 生き残るためのDX
たくさんの企業のDXを支援しているコンサルティング会社ならではの「成功・失敗の共通項」が信頼できる情報でした。内容が難しかったらどうしようと思いながらページをめくりましたが、わかりやすくてすらすら読めます。
……これからはLIGブログでもDXに関連する記事もどんどん出していきますので、こうご期待ください! 以上、まこりーぬでした!