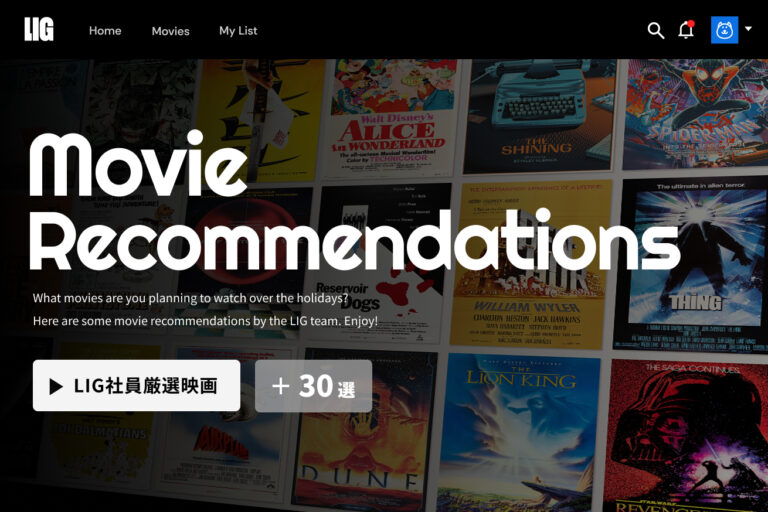LIG Copywriterのひゃくいち(@tanabe101)です。
先日、とある外部メディアへ記事を書くことになり、「著者プロフィール」が必要とのことで、座右の銘である「踏みつけたくなるウンコを求めて」を提出しました。
すると、「ごはんを食べながらスマホで記事を読んでいる人もいるから」と却下されることに。座右の銘が放送禁止になる人間をはじめて見つけることができた瞬間でした。とりあえず、この記事については、ごはんを食べながらスマホでお読みにならないでいただけたら幸いです。
今回のことで不意に思い出したのですが、実は7年ほど前にも、ウンコというコトバを使って怒られたことがありました。

そのころ、わたしが働いていたのは、かなりセクシーな業界。コピーライターとして日々、セクシーなコンテンツにセクシーなキャッチコピーを書いていました。その会社のコピーライター部の先輩に三村さん(仮名)という男がいたわけです。
三村さんはその業界では名の知れた人物らしく、現場あがりのたたき上げ。現場では伝説的な売り上げを生み出していたそうですが、コトバを扱った仕事をしたいとコピーライター部へ転籍してきたとのことでした。いまだに「現場」がどこのなにを意味するのかは知りませんが。
入社してからというものの三村さんは徹底的にわたしのことを無視しました。あとで聞いたところによると、「生半可な気持ちでこの業界へ飛び込んできた奴なのかどうかを見極めて、もしそうだったら半殺しにしようと思ってた」とのことです。

そんな不穏な空気を無意識に察知したのか、わたしは「これまでにないセクシー用語を世界に生み出そう」と積極的な感じでコピーライター部へ提案。というのも、その頃は、過去のキャッチコピーや文言をそのままコピペして上書きするような面白みのない作業に陥っていたからです。
コピーライター部のなかで勉強会を開催し、各季節ごとにユーザーへ刺さる新たなオトナのコトバを連日連夜、考えることに。この記事においては、一文字たりとも内容を書き起こすことは許されないだろうオトナな会議が続きました。
そんな中で、三村さんもわたしのことを徐々に受け入れてくれるように。当時、三村さんは30歳。25歳だったわたしの兄貴分のような存在でした。
三村さんは背が異様に高く、肌がドス黒く、目は血で淀み、声は低く、仕事中からウイスキーを隠れて舐めはじめ、夜になるとわたしの席へやってきて「行くぞ」と声をかけます。こちらの予定などは一切気にしない誘いかたが不思議と心地よく、わたしもついつい「行きましょう!」となってしまうわけです。

毎夜目指すは、西新宿にあったオフィスの窓から見える新宿・歌舞伎町、の奥の奥。歌舞伎町には何度か通っていたわたしではありますが、いかに表面的な歌舞伎町しか見ていなかったのかを思い知らせてくれるような。そんなところへ三村さんはいつも連れて行ってくれました。
三村さんは退勤時にはすでに軽く酔っ払っているわけですが、会社を出ると隣のコンビニに入り、缶ビールを3本ほど買ってイッキするのがお決まり。歌舞伎町に遊びなれた三村さんではありますが、しっかり酔ってからでないと歌舞伎町で今夜も出会うであろう人たちとのコミュニケーションがうまいことできない。そんなシャイな人でもありました。

道を歩くと見ず知らずの人たちが三村さんへ気軽に挨拶し、その隣に立っている冴えない男(わたし)のことをジロリとにらみつけていきます。そのたびに三村さんは「オレの新しい恋人」と紹介してかばって(?)くれるのですが、真に受けた人たちも少なくなく。その界隈では「三村さんの連れは、オンナには興味がないらしい」との見方が強まることとなり、面倒なのでわたしもそのキャラクター設定に合わせることにしました。
なので、いつも行くロックバーで「ひゃくいちの前なら問題ないか」と衣服を脱ぎ捨てて踊り狂っていた女性陣のみなさまには、ここで深くお詫び申し上げます。

そのロックバーはかなり狭く、カウンターが数席と、奥に個室がひとつ。カウンター席の背後には、スペースに対する比率がおかしい巨大なスピーカーが客の背中と触れるように並び、心臓が不整脈を起こしかねないほどの爆音で鳴っています。そのスピーカーの上で、誰かしらが勝手に踊りだすわけです。最初に来たときは慣れない異世界をまえに体調を急速に壊し、カウンターの片隅でひたすら脂汗を垂らしていたのを覚えています。
三村さんはそこの常連で、いつもタンカレーのロックを片手に、店内の人たちに声をかけていきます。海外の人たちの姿も多いのですが、なんともスムーズなコミュニケーション。ただ、よく考えたら、三村さんって英語はできないんですよね。で、あとで聞いたら「音がデカすぎて相手がなに言ってるのかなんてお互いに聞こえてないから問題ない」とのこと。コミュニケーションの真髄です。

三村さんは、この店に来るといつもよりも饒舌になってわたしに語りはじめるのですが、もちろん何を言っているのかはまったく聞こえません。そこで、ある日、「あそこはもうやめましょうよ。聞こえないし、話せないし。おれ、ロックにも興味ないんですよね」と三村さんに言うと、「おれもロックになんて興味ないよ」とのこと。
たしかに、ロックバーの店長から「何か聴きますか?」と爆音のなかジェスチャーでリクエスト曲を聞かれるたびに、三村さんはいつも適当にCD棚を指差していた気がします。それなのになんでわざわざ、あんなコアなロックバーへいくのだろう。結局、最後まで意味がわかりませんでした。
とりあえず、そのあとに「ですよね、ロックなんてウンコですよね」と言ったあとからの記憶は曖昧です。ボコボコにされて薄れゆく意識のなかで聞いた、「ウンコのことをウンコってコトバで表現するような奴は失せろ」という妙な捨て台詞だけが印象に残っています。

もう一度、あの店へ行ってみることにしました。
写真を撮ることは許されませんでしたが、店内はあの頃よりも少し落ち着いた雰囲気に。音楽のボリュームが「少し大きめ」くらいにまで下がっているのです。
店長の姿はなく、カウンター席に座ると若い男の子が「何にしますか?」と聞いてきます。ここで店員の声をしっかりと聞けたのは初めてのことかもしれません。タンカレーのロックも店長が作ってくれていたものよりは少し薄めに感じられます。
流れる音楽も意味不明なシャウトが延々と続くものではなく、ロックに詳しくないわたしでも名前くらいは聞いたことのあるバンドのものが、当時はなかったディスプレイに映像とともに流されています。客層もだいぶ変わっていて、あの当時と同じスピーカーの上にはおしゃれな外国の酒ビンが並び、踊り狂うことはできません。
どうして、三村さんが、あんなロックバーへ通おうとしていたのか。その理由が、少し分かった気がします。
恋しくなってしまったのか、「三村さんは今も来てるの?」と店員へついつい聞いてしまいました。三村さんとは、ボコボコにされたあともしばらく遊んではいたのですが、今はもう何年も会っていません。もちろん、新しい連絡先も知りません。
店員から返ってきたのは「えっと、誰のことですか?」とのコトバ。「背が異様に高くてさ、いつも泥酔しててさ、震えた手でタンカレーばっか飲んでるさ、今はもう40歳手前の男なんだけど」。そこまで言うと「ああ……」としばらく黙り込んでから、言いにくそうな顔で「京都へ行ったみたいですよ」との答えが。
「え、なんで、京都?」
「……あそこには坂本龍馬の像があるからって」
「は?」
「……朝・昼・夜と毎日でも拝めるから良いって」
「なんだそれ。龍馬像って東京にもあるのに」
「……へえ」
「品川かどっかにあるんだよ」
「……へえ」
「うん」
「…………」
「…………」
「…………」

京都へ行ってみることにしました。
三村さんを見かけたら「踏みつけたくなるウンコを求めてっていう座右の銘をメディアに載せようとしたら、下品だからやめろって怒られちゃいましたよ、どう思います?」。そんな風に話してみるつもりです。

もしかしたら「ウンコのことをウンコってコトバで表現するような奴は失せろ」と、またもやボコボコにされてしまうかもしれませんね。


もう、生きてはいないのだと思います。